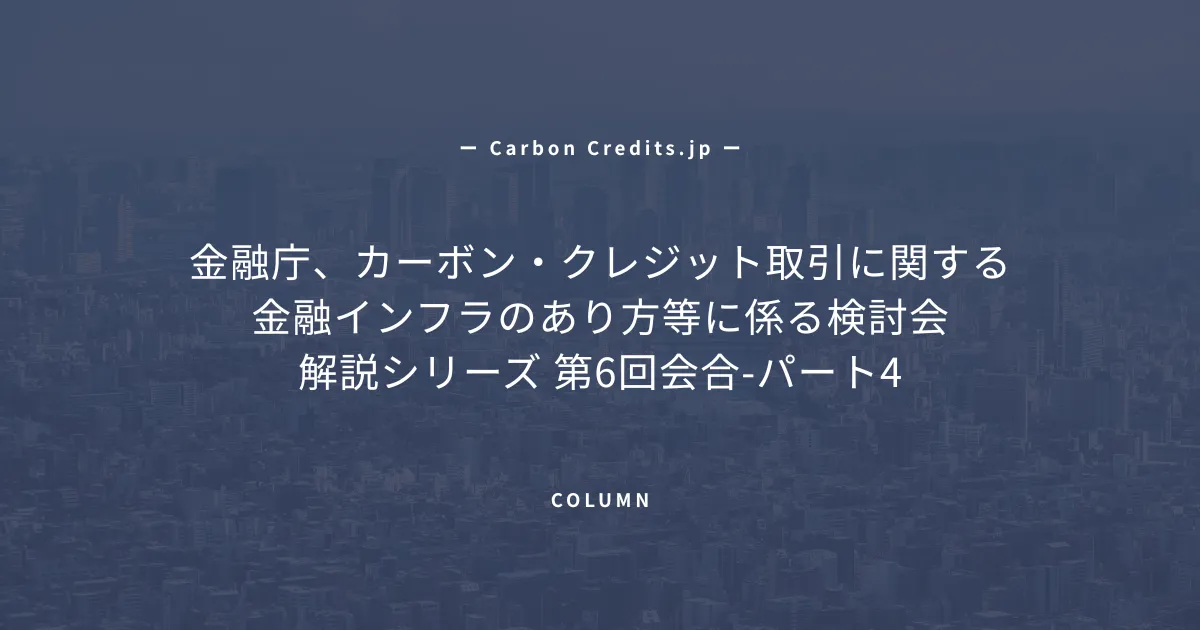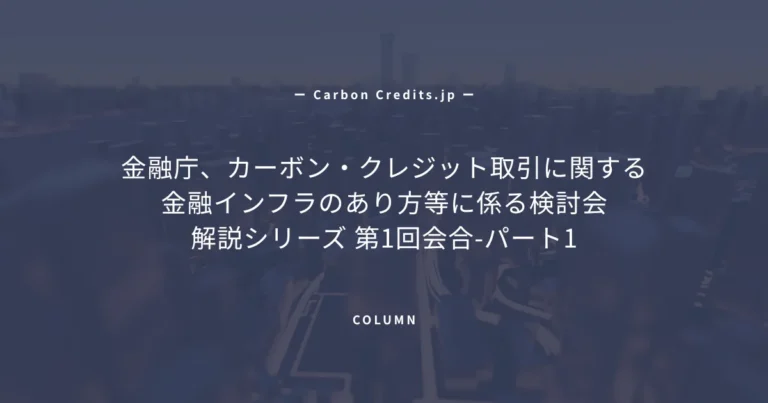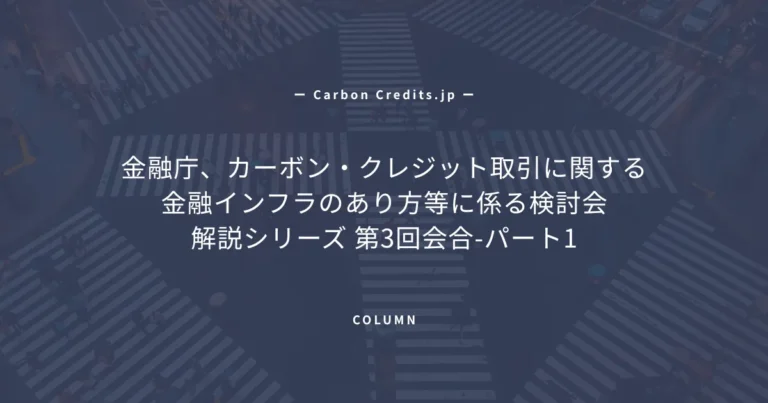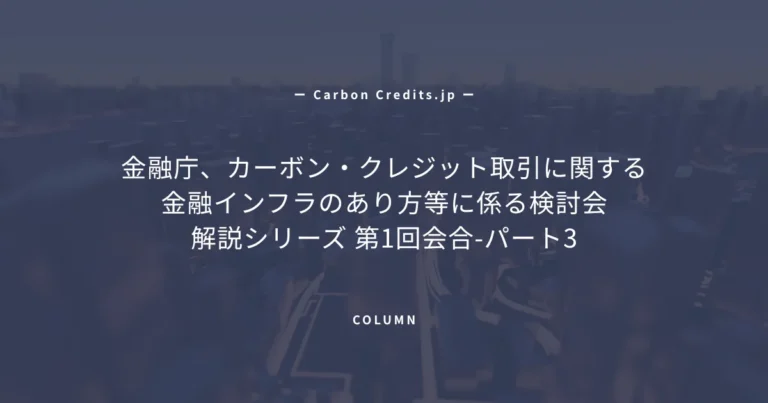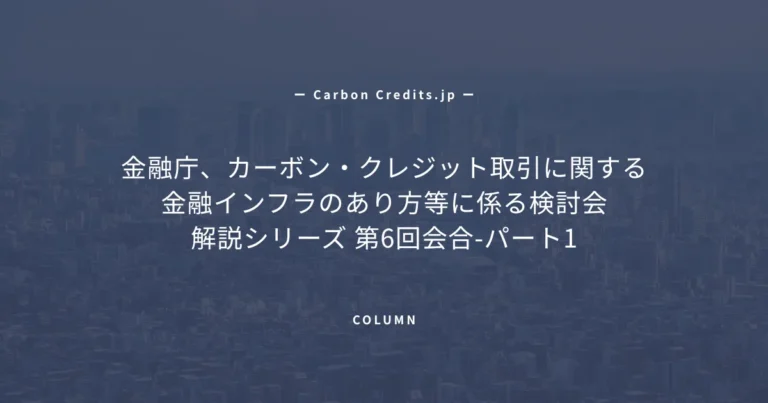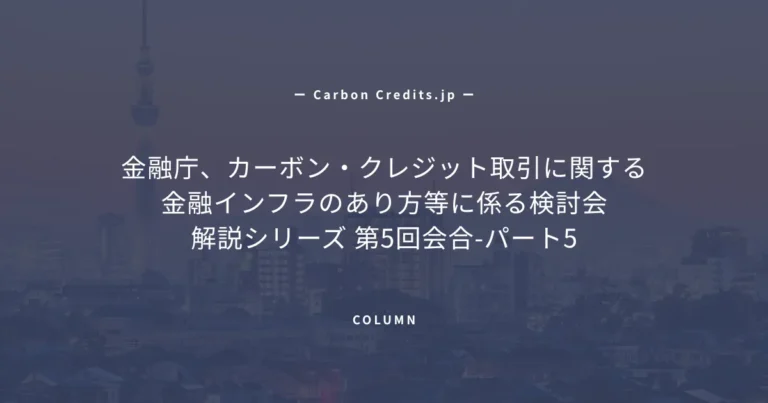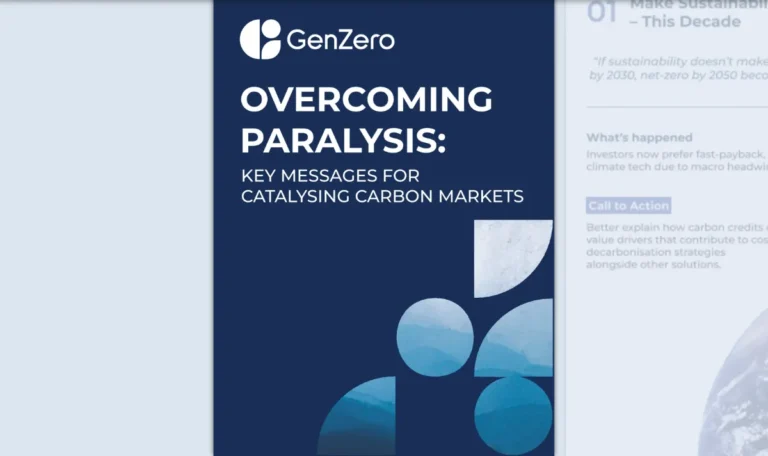金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第6回パート4
パート4では、商社・コンサル・機関投資家のメンバーから、用語の再整理と情報提供フレームの拡充が議論された。各発言を軸に論点を集約する。
需要サイドから見た 「二層構造」
分類の基準は買主の利用目的
メンバーから「自主的購入=ボランタリー」「制度的義務を果たす購入=コンプライアンス」で整理しているという例が示された。「例えば、現行のJ-クレジットはボランタリーだが、2026年度以降はGX-ETS補完枠に組み込まれればコンプライアンス化する。」といった整理だ。VerraやGold Standardのクレジットであっても、シンガポールの炭素税の代物弁済やCORSIA向けに用いればコンプライアンス扱いと言えるという整理だ。
説明責任の射程に限界
報告書は「カーボンクレジットを組み込んだ商品の販売先でも適切説明を」と記すが、仲介者が二次流通先での説明まで担保するのは実務上困難であるという主張があがった。過剰規制で市場を窒息させないバランスが要請された形だ。
インフラ章の再編と「クロスカット」視点
登録簿・取引所・多様な仲介者の役割分担と相互連携を一枚図で示すべきという意見が上がった。その上で、登録簿に関しては「正確性」を具体化、例えばシリアル番号公開、二重計上防止、サイバーセキュリティなどの要件を満たす必要があると指摘。
また、情報を束ねる公開プラットフォーム、評価機関の格付や取引所出来高を集約表示する場が透明性向上の鍵という意見も挙げられた。
リテラシー向上と伝わる文体
キャパシティビルディング≒リテラシーを明示し、キーワードとして挿入することが提案され、キャパシティビルディングの重要性が強調された。
また、政府・業界団体・仲介者・取引所が連携してFAQや事例集を提供すべきといった意見や、用語集を添付し、非専門投資家の理解を支援すべきといった意見も挙げられた。
まとめ
パート4は実務家の肌感覚が前面に出た。定義と責任分担を曖昧にしたままでは、市場拡大フェーズで混乱が生じるという危機感が共有され、報告書はより具体的な設計図へとアップデートを迫られている。
次回以降、図解や用語集を伴う改訂案が提示され、議論は最終局面へと進むだろう。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第6回)議事録.令和7年4月11日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第6回)議事次第.令和7年4月11日