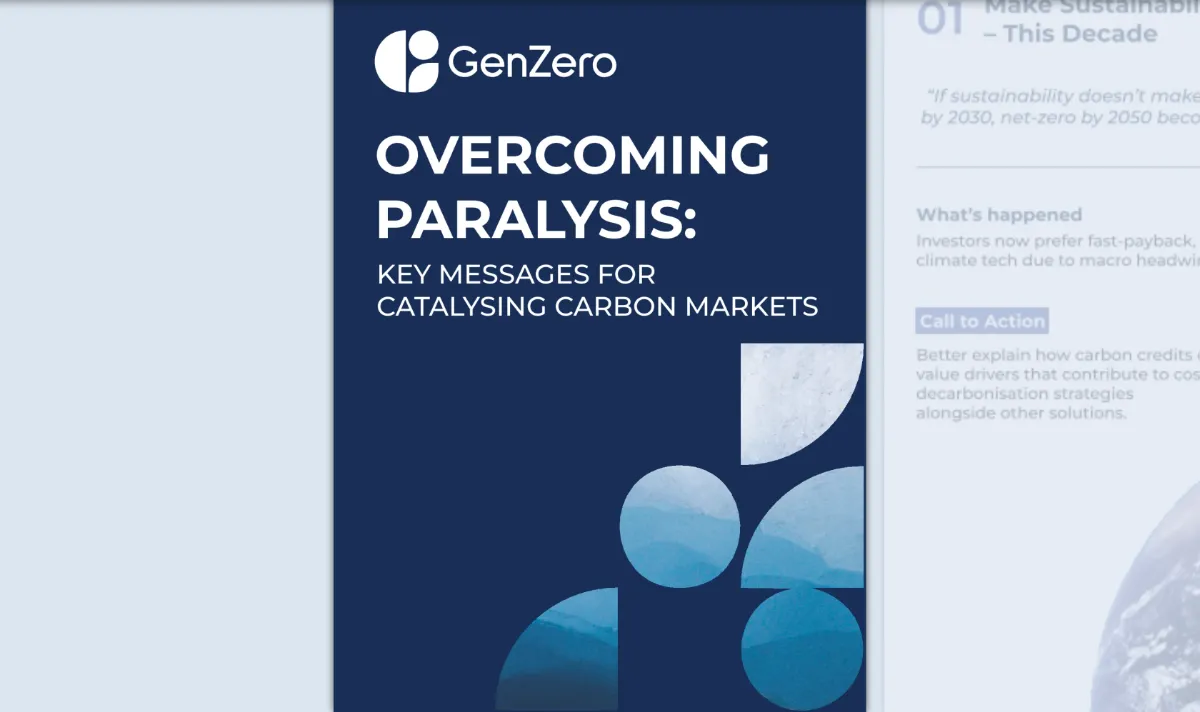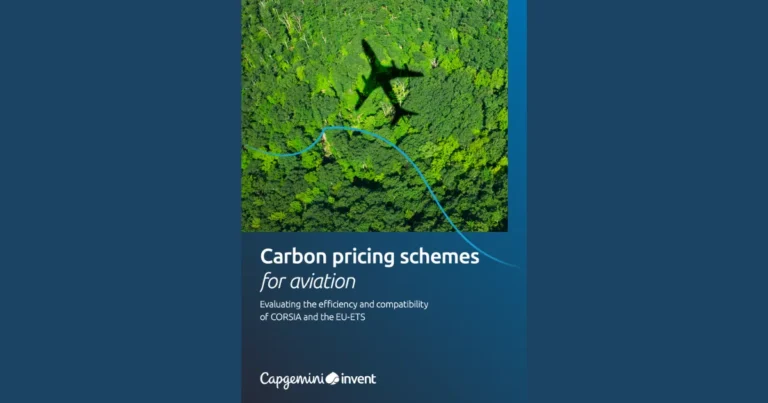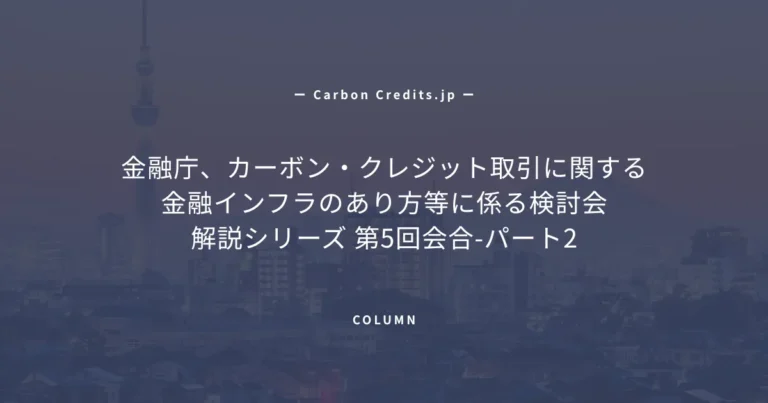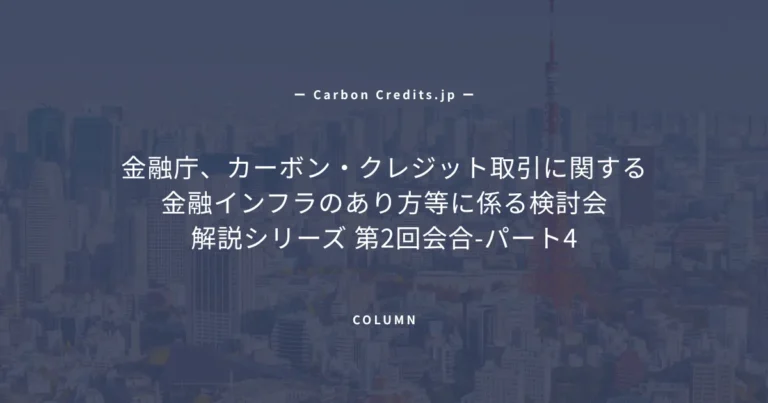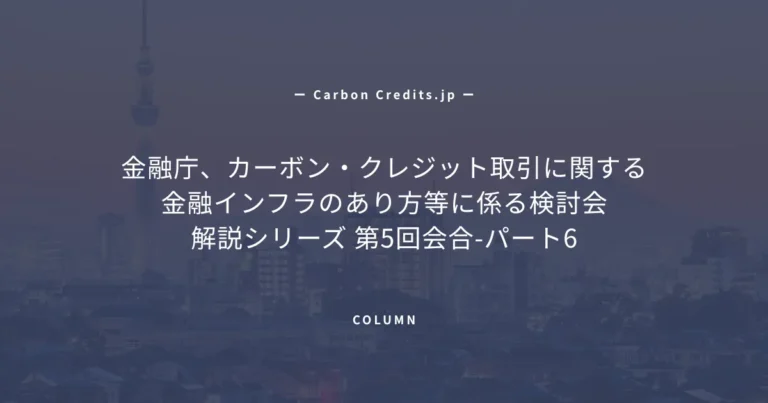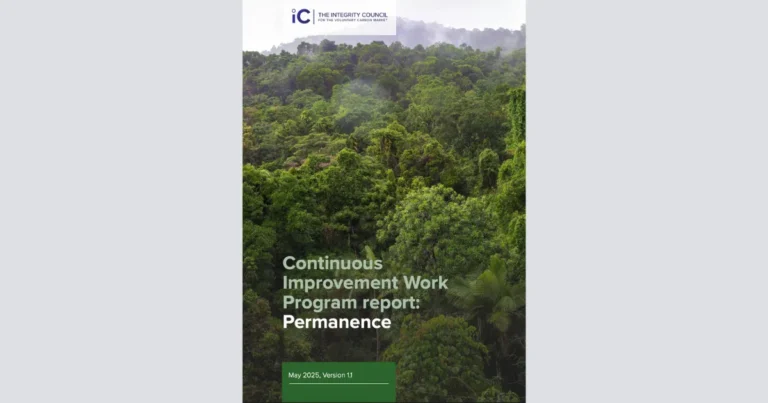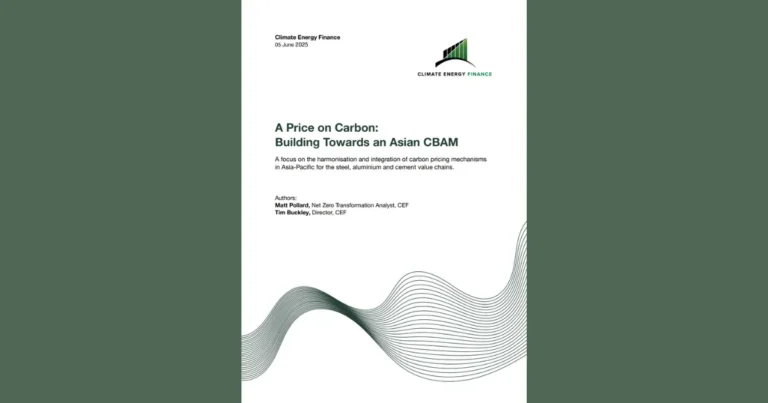GenZeroは、「カーボンクレジットマーケットの再活性化に向けた6つの行動メッセージ」をまとめたガイドを発表した。マクロ経済の逆風や規制の不確実性により、世界的な脱炭素投資が減速する中、炭素市場の信頼と資本の流れを取り戻すことが、ネットゼロ実現の前提条件であると強調している。
「持続可能性」に経済合理性を 2030年までの商業モデル確立を提案
レポートは、「持続可能性が2030年までに商業的合理性を持たなければ、2050年ネットゼロは絵に描いた餅になる」と指摘。単なるオフセット手段ではなく、炭素クレジットは脱炭素戦略における即効性ある“価値創出型資産”であることを企業に理解させる必要性を強調している。
SAFやトランジションクレジットへの資金再配分を訴え
2023年のカーボンクレジット関連投資額は89億ドルから65億ドルへと減少(MSCI調査)。その一方で、SAF(持続可能な航空燃料)やトランジションクレジットなど、新たなプロジェクト類型への需要は急増している。レポートは、こうしたカテゴリーに「触媒的資本」を集中的に誘導する必要があると提言した。
規制の明確化が市場再生の前提条件に
企業による脱炭素行動の停滞は、「SBTiやISOなどの基準に対する解釈のばらつき」によるものが大きい。レポートは、市場ルールの整合化と、信頼性評価・検証体制の構築支援を軸とする規制整備の重要性を訴えている。「普遍的合意を待つより、まずは明確な規制の枠組みを設けよ」という現場感覚に即した姿勢が特徴だ。
国際クレジットとArticle6の整合性を政策に
EUが2040年温室効果ガス(GHG)90%削減目標に向け、国際クレジットの使用を検討しているという報道を受け、レポートはArticle6と民間基準の整合性を取るべきだと主張。CORSIAやEU ETSのような制度と連携しながら、先進国から新興国への資金移転を加速する仕組みが必要とされている。
VCMIやISO準拠の「主張ガイドライン」策定を後押し
企業の多くが「グリーンウォッシュ批判」への不安から脱炭素行動に二の足を踏む「グリーンハッシング」状態にある。こうした現状を打破するため、VCMIの「Scope 3 Action Code」やISOのネットゼロガイドラインに基づく整合的な主張枠組みを推進すべきとした。特に中小企業にとっては、炭素会計と開示の簡素化が喫緊の課題とされる。
削減vs除去、自然vs技術の「偽りの二項対立」を超えて
報告書の最後に強調されたのは、「どちらかではなく両方」という視点だ。除去(removal)を優先する風潮が広がる一方で、森林保護やSAFなどの削減(reduction)案件が資金流出に直面している。これは短期的な気候効果を損なうリスクでもある。すべての高信頼プロジェクトが価値を持つという前提に立ち、市場や政策が偏らないよう調整する必要性が提言されている。
まとめ
GenZeroはレポートの冒頭で「麻痺状態を打破しなければ、炭素市場は縮小の一途をたどる」と警鐘を鳴らす。同時に、持続可能性を「正義」から「投資対象」に転換させる道筋を示したことは、日本企業や政府にとっても有益な示唆となるだろう。
参照:https://genzero.co/overcoming-paralysis-key-messages-for-catalysing-carbon-markets/