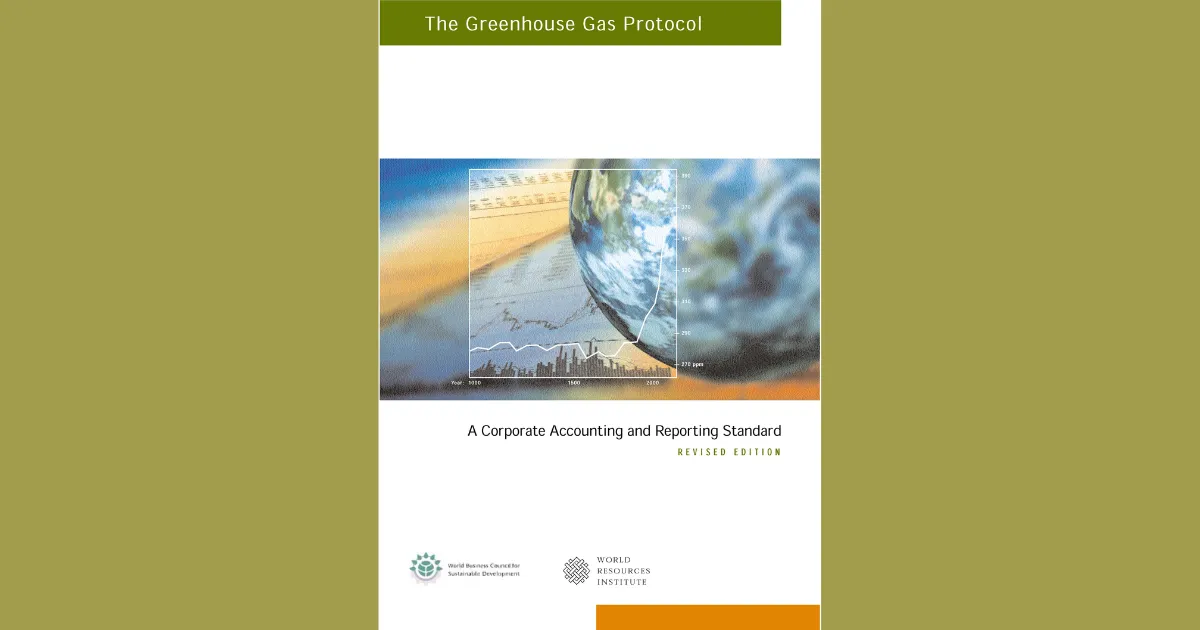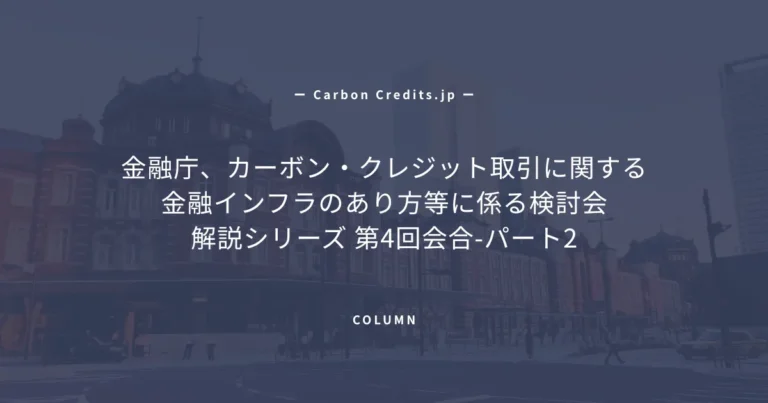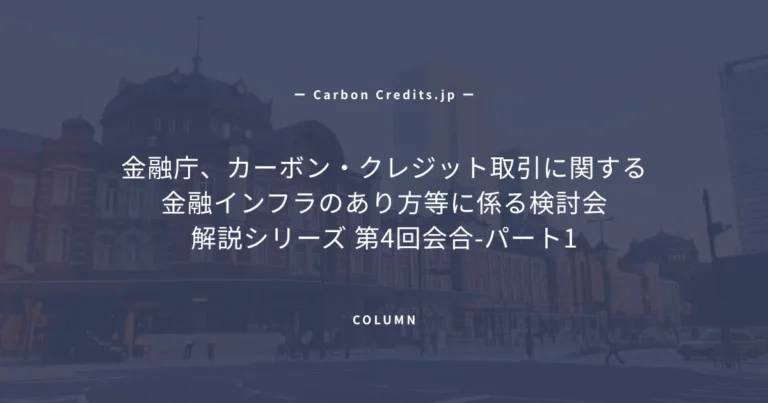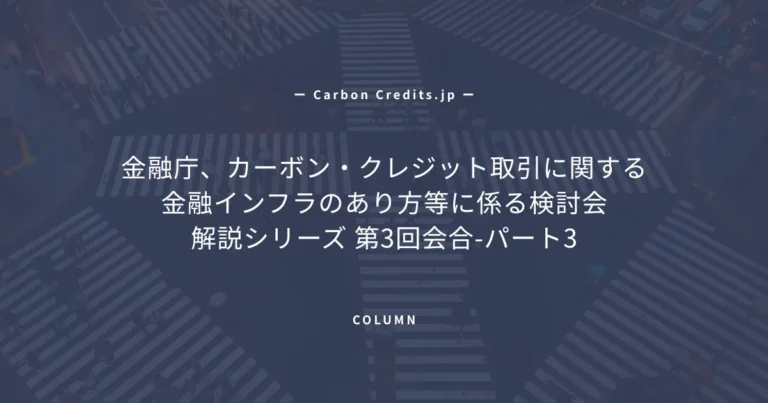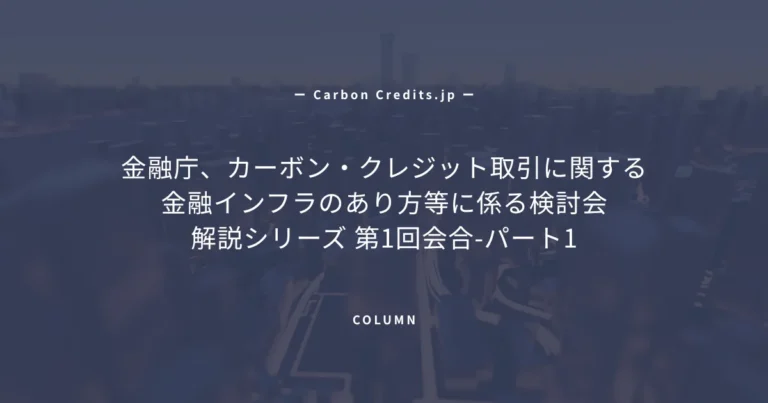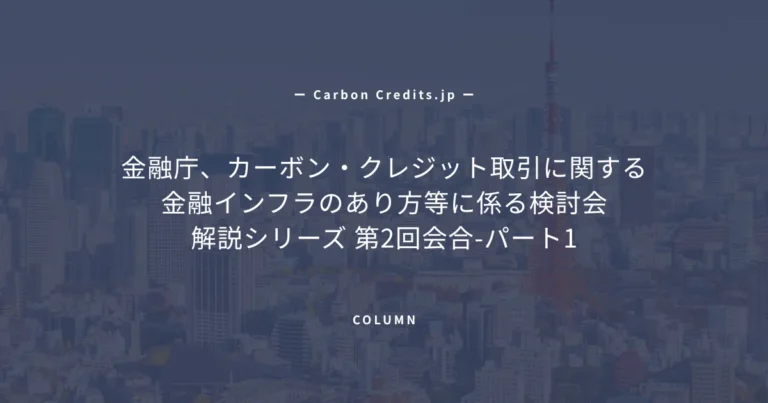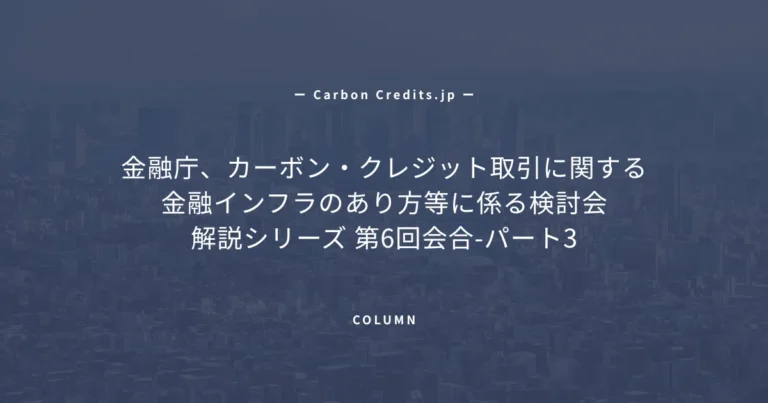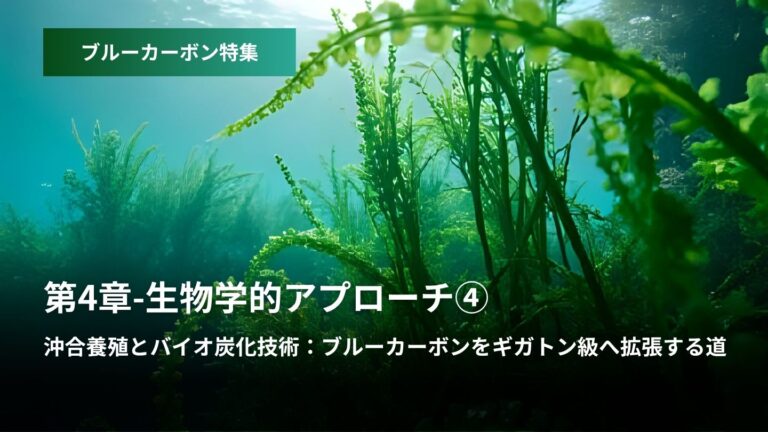カーボンクレジットやカーボンオフセットといった温室効果ガス(GHG)の削減手段が、企業の気候変動対策の一環として注目されています。しかし、これらの仕組みが有効に機能するためには、削減量の算定と報告に対する明確なルールと枠組みが不可欠です。
本コラムでは、国際的に最も広く用いられているGHG会計の枠組み「GHGプロトコル」のA Corporate Accounting and Reporting Standard(以下コーポレートスタンダード)では、どのようにしてカーボンクレジットとカーボンオフセットの信頼性と実効性を担保しているのかについて詳述します。
GHGプロトコルとは何か、カーボンクレジットの出発点
GHGプロトコルは、世界資源研究所(WRI)と持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)が共同で策定した、GHG排出量の会計と報告に関する国際的な標準です。
その目的は「企業がGHG排出インベントリを正確かつ一貫して作成し、公的・私的報告や政策対応に活用できるようにすること」です。
このプロトコルは、CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6の6種類のGHGを対象にしています。これらのガスの排出量を組織レベルで定量化し、報告するための指針を提供します。
排出削減の信頼性を担保する5つの原則
コーポレートスタンダードはGHGプロトコルの中でも、特にScope 1,2の算定方法を中心としたガイダンスであり、企業のGHG会計と報告を「関連性(Relevance)」「完全性(Completeness)」「一貫性(Consistency)」「透明性(Transparency)」「正確性(Accuracy)」の5つの原則に基づいて行うことを求めています。
たとえば「完全性」については、以下のように明記されています。
“選定したインベントリ境界内に含まれるすべての温室効果ガス(GHG)の排出源と活動を算定し、報告すること。特定の項目を除外する場合は、その除外内容を開示し、合理的な根拠を示すこと。”(p.7)
このような原則は、カーボンオフセットの対象となる排出量の信頼性を担保する上で重要です。
オフセットとスコープの関係
GHGプロトコルでは、排出源を以下の3つのスコープに分類します。
カーボンオフセットは、これら各Scopeの排出を相殺する形で用いられます。しかし、実際の排出削減は他者のプロジェクトによるものであり、その成果を自社の削減として記載するには明確な区分と説明が必要です。GHGプロトコルでは、こうしたクレジットの扱いについて以下のように示しています。
“企業は、自らが選定したインベントリ境界内の実際の排出量(物理的排出量)を、実施したGHG取引とは分けて独立に報告することが重要である。GHG取引は、任意情報として企業のGHG公開報告書に記載されるべきであり、これは削減目標または企業インベントリとの関連で報告される。”(p.58-61)
つまり、カーボンオフセット実施前の数値と適用後の数値は、それぞれ分けて報告するべきであるということになります。
“購入または販売されたオフセットやクレジットの信頼性に関する適切な情報も報告に含めるべきである。”(p.58-61)
つまり、仮にカーボンオフセット実施後の数値を報告する場合は、そのクレジットの「詳細な情報」と一緒に報告するべきであるということになります。
“企業が自社の事業活動によってGHG排出量を削減する内部プロジェクトを実施した場合、その削減量は通常、企業のインベントリ境界内で捉えられる。これらの削減量は、売却・外部取引されたり、オフセットやクレジットとして利用される場合を除いて、別途報告する必要はない。”(p.58-61)
つまり、自社内で削減されたGHGは当然、自社のScope 1,2に反映されるため、あえて削減量を別で報告する必要はない。その上で、仮にその削減によってカーボンクレジットを創出し、外部に販売した場合には、その「販売に関する詳細」を報告する必要があるということになります。
総じて、カーボンオフセットの削減効果は、企業のGHG排出量の直接的な減少とは別に取り扱う必要があります。
カーボンクレジット利用時の報告のあり方
GHGプロトコルでは、オフセットの利用を報告する場合において、第三者の信頼を得るために「報告の透明性」を厳格に求めています。Chapter 9では、以下のような指針があります。
“インベントリ境界外で購入または開発されたオフセットに関する情報は、GHGの貯留・除去(吸収系)プロジェクトと排出削減プロジェクト(回避系)に分類して記載すること。さらに、これらのオフセットが第三者によって検証・認証されているかどうか、およびCDM(クリーン開発メカニズム)やJI(共同実施)などの外部GHG制度によって承認されているかを明記すること。”(p.66)
つまり、オフセットに使用したカーボンクレジットの詳細を報告すべきであるということになります。
“インベントリ境界内の排出源で生じた削減量が第三者にオフセットとして販売・移転された場合、その情報も報告すること。これらの削減量が検証・認証されているか、外部制度により承認されているかを明記すること。”(p.66)
つまり、カーボンクレジットを創出・販売した場合は、その創出プロジェクトの詳細も報告するべきであるということになります。
このような報告要件は、オフセットの乱用や二重計上(ダブルカウント)を防ぎ、排出削減の実効性を担保するために不可欠です。
本コラムでは、カーボンクレジットとカーボンオフセットの信頼性を支えるGHGプロトコルコーポレートスタンダードでの扱いについて解説しました。
GHGプロトコルコーポレートスタンダードは、削減量の正確な算定と報告のガイドラインを示しています。企業が真に持続可能な気候戦略を進めるためには、プロトコルのガイドラインに沿って、排出の可視化、削減、オフセットを一体的に実行する姿勢が求められます。