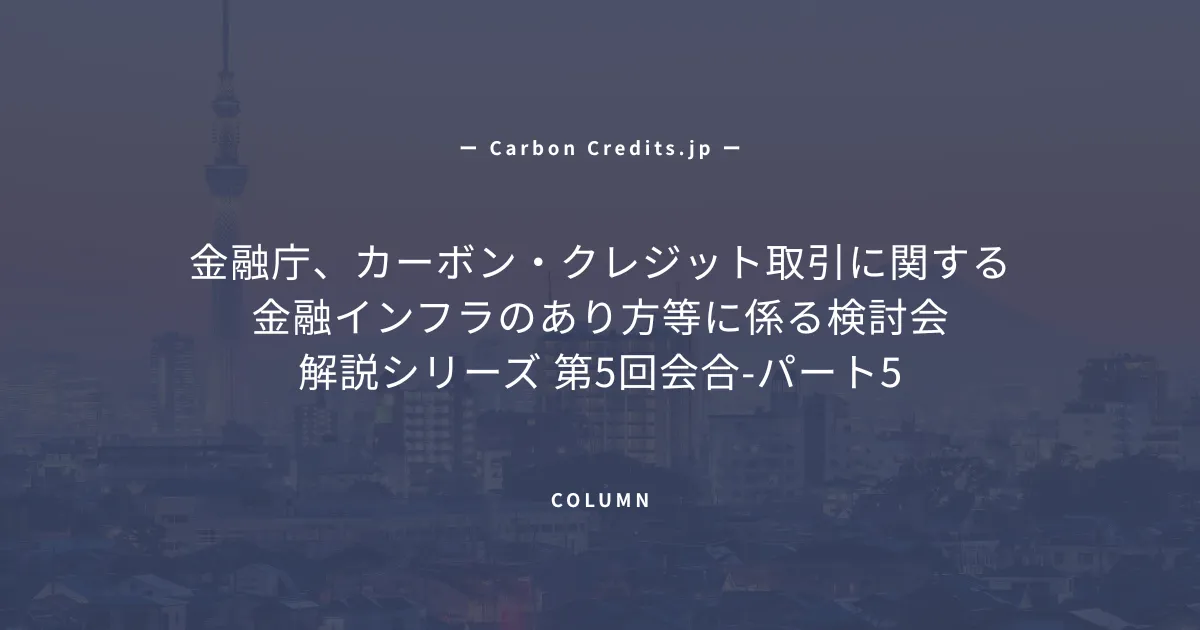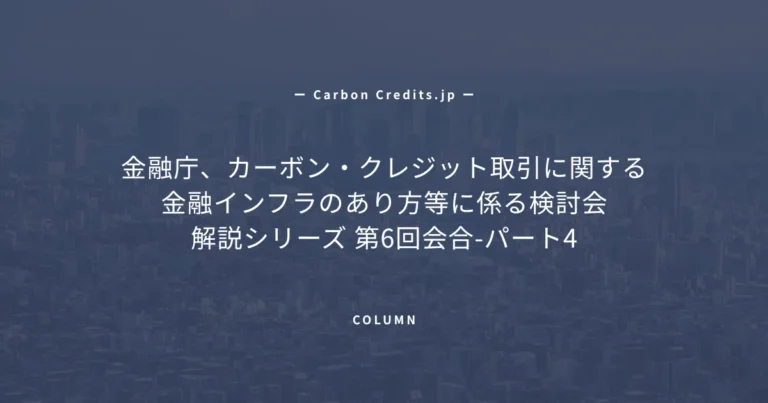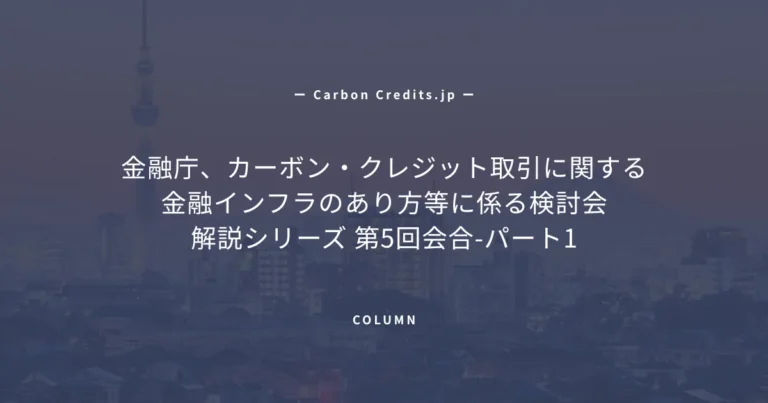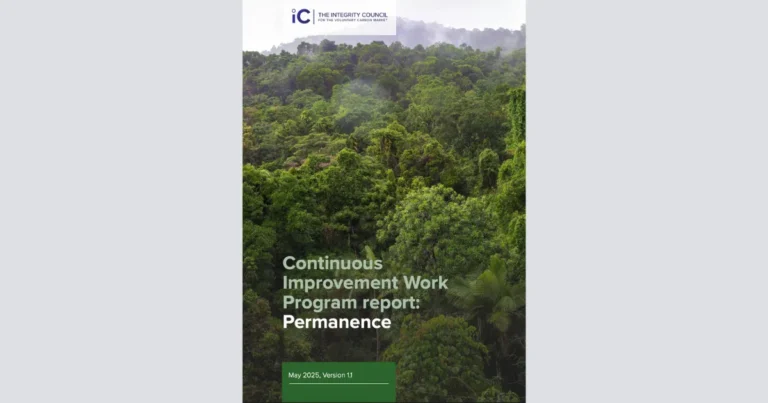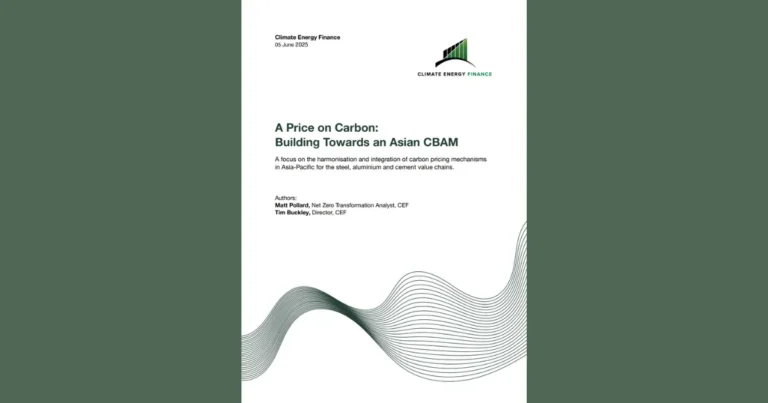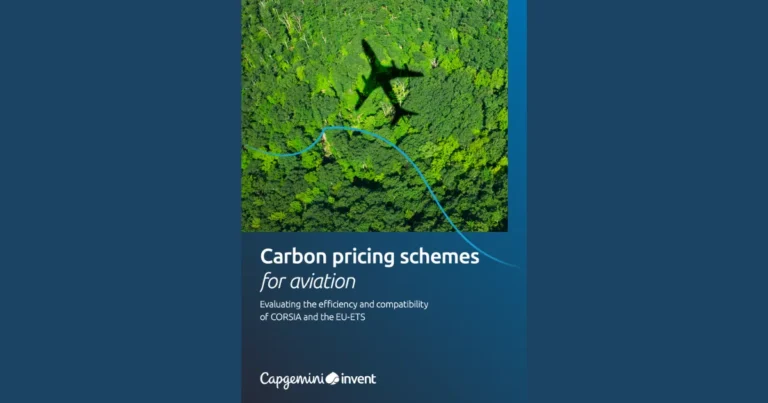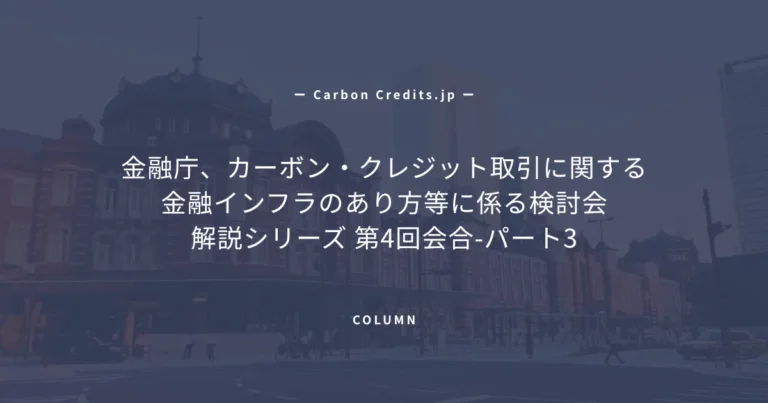金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第5回パート5
第5回検討会の後半では、ENEOSが登壇し、「排出者」であり「供給者」の立場から、提言を行なった。
ENEOSは、カーボンクレジット市場で需要と供給の両面を担う企業として、同社の全体戦略と課題を語った。本稿では、ENEOSグループのカーボンニュートラルに向けた取組を網羅的に整理する。
巨大排出事業者としての自覚
ENEOSグループは石油精製・販売を中核とする6社体制で、連結売上高15.1兆円・従業員約4.4万人を擁する国内最大級の総合エネルギー企業である。国内燃料販売シェアは約50%に達し、11か所の製油所だけで、グループGHG排出量の9割以上を占めるという 。
同社は年間3,000万トンのScope 1、Scope2排出に加え、顧客の燃焼分を含むScope3が1億8,000万トン、 Scope1,2,3合計で2億1,000万トンのCO2排出に関与している。
これは日本全体の排出量の約2割に相当し、同社の動向が日本のNDC達成を左右するとの認識を示した 。
カーボンニュートラル基本計画(2023年5月公表)
ENEOSは2040年度までにScope1,2をカーボンニュートラル化し、2030年度には13年比46%削減を掲げる。達成の鍵は①自社排出の削減/固定化、②社会(顧客)の排出削減への貢献という二本柱に置かれる。
排出削減ロードマップと年500万トンクレジット創出目標
自社排出量は基準年36百万トンから2040年に実質ゼロへ。
自然吸収(森林由来)のカーボンクレジットで年5百万トンを創出し、残余分をカーボンオフセットするシナリオを描く。同時にBECCS、DACCSなどのCCSによる人為的固定化も並走する。
GX-ETSへの対応と課題
2026年に本格導入されるGX-ETSでは、年間10万トン以上排出する事業者に排出枠義務が課せられ、適格クレジット(J-クレジット・JCM)が償却に利用できる。
ただし創出量は不足しており、使用上限も未確定のままだ。多排出企業のENEOSは「どの程度オフセットに使えるかの早期明示が不可欠」と訴えた。
適格クレジット創出、国内外で森林・ブルーカーボンを拡充
国内では自治体・森林組合と協働し、6案件・総面積4万haで累計95万トンのJ-クレジット創出にめどをつけた。海外でも住友林業が北米で組成する森林ファンドへ1億ドル出資し、ボランタリーカーボンクレジットの確保も進め、天然藻場再生によるブルーカーボンクレジットの実証も始動したと説明した。
ボランタリークレジット活用、重油×DACCSで海運大手に提供
需要家向けには、燃料油にDACCS由来カーボンクレジットを付与するカーボンオフセット商品を展開。船舶用重油にカーボンクレジットを組み合わせ、日本郵船に販売するなど、運輸部門の実需に対応した例が紹介された。
市場形成に向けた懸念と提言
適格クレジット側では「方法論拡充と創出量拡大」、ボランタリー側では「認知度向上と環境価値の可視化」が急務と整理した。
その上で、
- 国力強化につながる市場設計:地域の供給者と製造業の需要者が合理的に合意できるシンプルなエコシステムの構築
- 質と価格の予見性の確保:需要者が安心できる品質情報の提供と、実需を伴わない投機的取引の排除
を金融インフラ整備の二大論点として挙げた。
「エネルギー供給」と「カーボンニュートラル」の両立へ
ENEOSは、140年近く日本のエネルギーを支えてきた責任を果たしつつ、トランジションを通じてカーボンニュートラル社会を実現する決意を改めて表明した。
巨大排出源である同社が自らカーボンクレジット創出を加速し、需給両面で市場を牽引できるか、その成否は日本のGX実装と地域経済の強靭化を左右するだろう。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事録.令和7年2月25日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事次第.令和7年2月21日