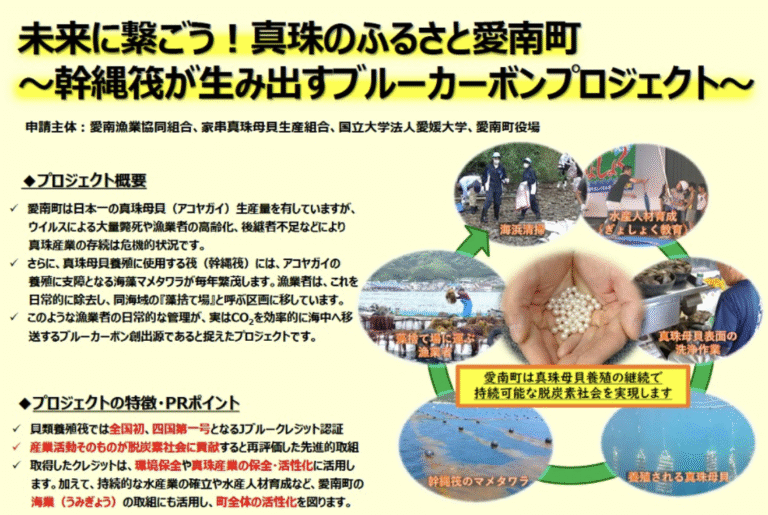富士通は11月26日、水中ドローンとAI画像解析を組み合わせ、ブルーカーボンの定量化時間を従来比で100分の1に短縮する新技術を開発したと発表した。愛媛県宇和海での実証実験において、同社はこの技術を用いて算出したデータに基づき、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が認証する「Jブルークレジット®」の取得に成功しており、高品質な炭素除去(CDR)クレジットの創出を加速させる測定・報告・検証(MRV)ソリューションとして実用化を目指す。
認証率95%の精度を実証
今回発表された技術は、海洋の状態をデジタル空間上に再現する「海洋デジタルツイン」の一環として開発されたエンドツーエンドシステムである。富士通は、一般社団法人宇和海環境生物研究所や愛媛県宇和島市などと連携し、宇和海における藻場のブルーカーボン定量化を実施した。
特筆すべきは、算出されたデータの信頼性である。同システムを用いてJBEにクレジット認証を申請した結果、申請量の95%が認定されるという高い認証率でJブルークレジット®を獲得した。これは、同社の技術がカーボンクレジット市場において求められる厳格なMRV基準を満たし得ることを示唆している。
自動化で「1ヘクタール30分」を実現
開発されたシステムの中核を成すのは、以下の3つの要素技術である。
- 水中ドローン自動航行制御技術
海流や波の影響下でも、位置誤差±50センチメートル以内での安定航行を実現し、測定漏れを防ぐ。 - 藻場定量化技術
濁った海中でもAIによる画像鮮明化を行い、海藻・海草の種類と被度(海底を覆う割合)を85%以上の精度で認識する。 - 藻場創出シミュレーション技術
環境変化や人為的介入による生態系への影響を予測し、保全施策の効果を事前検証する。
これらを統合することで、従来は専門ダイバーによる潜水調査で1ヘクタールあたり約2日間を要していた計測・定量化作業を、わずか約30分で完了させることが可能となった。
信頼性の高いカーボンクレジット創出へ
ブルーカーボンは、大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収・貯留する有力なCDR手法として世界的に注目されている。しかし、そのクレジット化にあたっては、広大な海域における正確な炭素吸収量の計測(MRV)にかかるコストと労力が大きな障壁となっていた。
従来の手法では、海中の濁りや複雑な地形によりデータの精度確保に限界があり、人手による解析はスケーラビリティ(拡張性)を欠いていた。富士通の新技術は、これらの課題をデジタル技術で解決し、科学的根拠に基づいた「質の高いクレジット」の効率的な発行を支援するものである。
2027年のビジネス化を標榜
富士通は、本システムを2025年11月27日から神戸で開催される「Techno-Ocean 2025」に出展する。今後は、各自治体や企業と連携して実海域での適用を広げ、藻場の回復・保全やクレジット認証取得を支援していく方針だ。
また、同技術の適用範囲を洋上風力発電施設の環境調査などにも拡大し、2027年までに環境保全と経済成長を両立するビジネスとしての確立を目指すとしている。