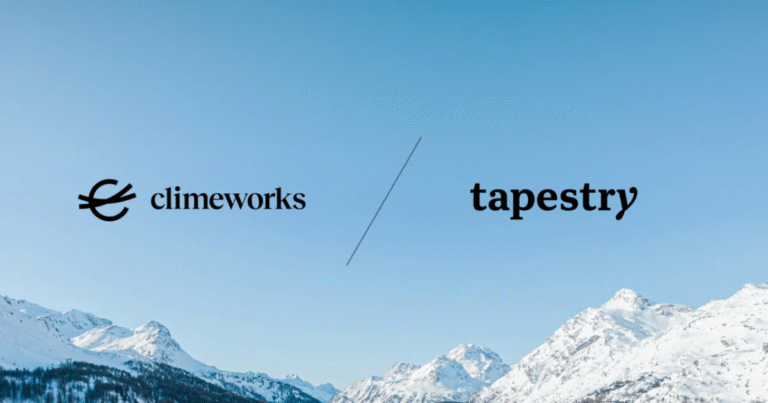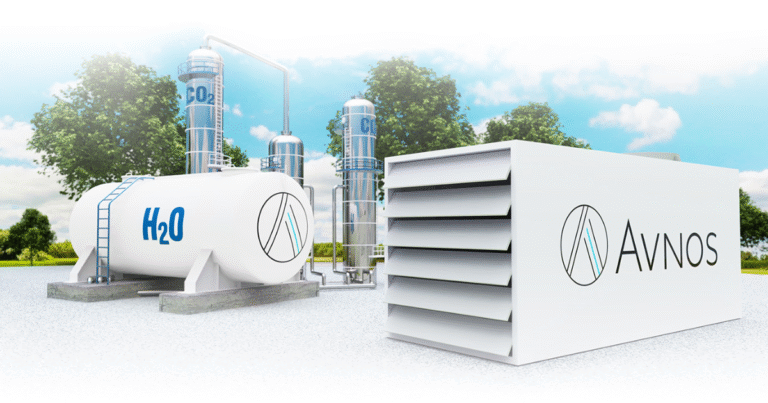米エネルギー経済・財務分析研究所(IEEFA)は2025年11月24日、アジア地域のカーボンプライシングに関する最新のファクトシートを公開した。同研究所は、世界の温室効果ガス(GHG)排出量の50%以上を占めるアジア地域において、現在の炭素価格が「著しく低水準」であると警告。パリ協定の目標を達成するためには、現状のトンあたり20ドル(約3,080円)未満から、2030年までに50〜100ドル(約7,700〜15,400円)の水準へ引き上げる必要があるとの試算を示した。
低すぎる価格設定とCDR投資への障壁
IEEFAの報告書によると、アジア各国で導入されている炭素税や排出量取引制度(ETS)の価格水準は、脱炭素化やクリーン技術への投資を促すには不十分な状態にある。
現在、地域内の炭素価格は概ねトンあたり20ドル(約3,080円)を下回っている。これに対し、IEEFAは以下の段階的な価格引き上げを提言した。
- 初期価格:トンあたり15〜25ドル(約2,300〜3,850円)
- 年間上昇幅:毎年10〜15ドル(約1,540〜2,300円)ずつ引き上げ
- 2030年目標:トンあたり50〜100ドル(約7,700〜15,400円)
この価格是正は、炭素除去(CDR)技術や高品質なカーボンクレジットプロジェクトへの資金流入を加速させるためにも極めて重要だ。現在の低価格帯では、大気中のCO2を直接回収する技術(DAC)など、高コストなCDR技術の商用化が進まない恐れがあるためだ。
「原単位方式」から「総量規制」への転換を
報告書は価格面だけでなく、市場設計の構造的な欠陥についても言及している。特に、中国やインドネシアなどで採用されている「原単位方式(生産量あたりの排出量上限)」のキャップ設定について、経済成長に伴い総排出量が増加するリスクがあると指摘した。
IEEFAは、より確実な排出削減を実現するために以下の施策を推奨している。
- 絶対量キャップの導入
原単位方式ではなく、排出総量を制限する絶対量キャップ(総量規制)への移行。 - 無償割当の廃止
排出枠の無償配分(グランドファザリング等)から、競争入札(オークション)方式への転換。 - 対象セクターの拡大
発電部門だけでなく、産業界全体への適用拡大。
アジア主要国の現状と課題
報告書では、アジア各国の制度状況も整理された。各国とも制度導入は進んでいるものの、カバレッジや規制強度にはばらつきが見られる。
韓国
排出量取引制度(ETS)により国全体の排出量の79%をカバー。絶対量(ボリューム)ベースのキャップを採用し、対象は685事業者に及ぶ。
中国
世界最大級のETSを運用し、電力、鉄鋼、セメント、アルミニウム部門を対象にCO2排出量の60%をカバー。ただし、キャップ設定は原単位方式に留まる。
日本
国レベルの「地球温暖化対策税(炭素税)」と、東京都・埼玉県による地域レベルのETSが併存。国全体のGHG排出量の70%をカバーしているとされるが、価格インセンティブの弱さが課題として残る。
インドネシア
発電部門を対象としたETSを開始し、排出量の24%をカバー。原単位方式を採用。
シンガポール
製造業等を対象とした炭素税で排出量の70%をカバー。
補助金撤廃と社会的配慮の両立
カーボンプライシングの実効性を高めるための補完的な政策として、IEEFAは化石燃料補助金の段階的な廃止を強く求めた。補助金の存在が炭素価格のシグナルを相殺し、脱炭素化のインセンティブを弱めているためだ。
一方で、炭素価格の上昇が低所得層への負担増とならないよう、炭素税収等を現金給付や還付という形で家計に再分配する「歳入リサイクル」の仕組みを設計・統合することも不可欠であると結論付けた。
アジア地域におけるカーボンプライシングの厳格化は、同地域にサプライチェーンを持つ日本企業にとって、コスト構造の抜本的な見直しを迫るものとなる。今後の各国の制度改定の動向が注視される。
参考:https://ieefa.org/resources/fact-sheet-carbon-pricing-asia-challenges-and-recommendations