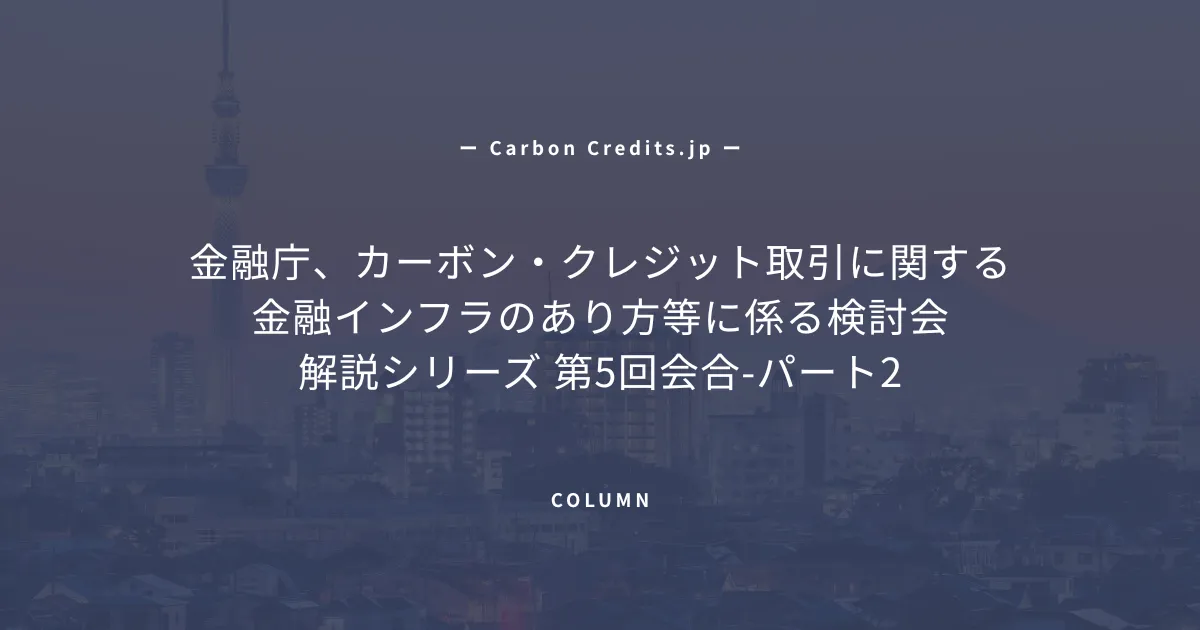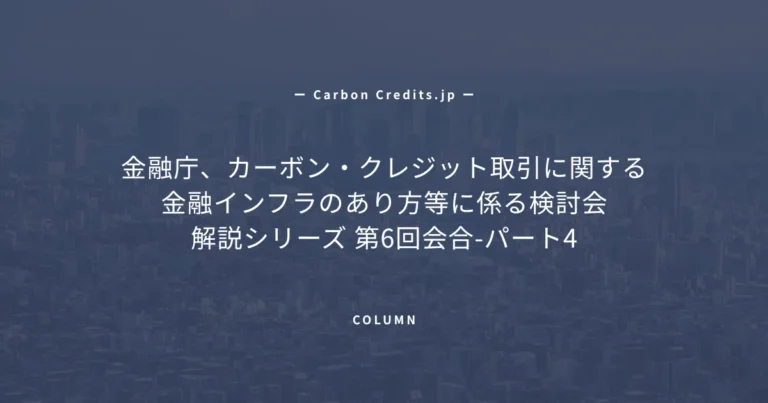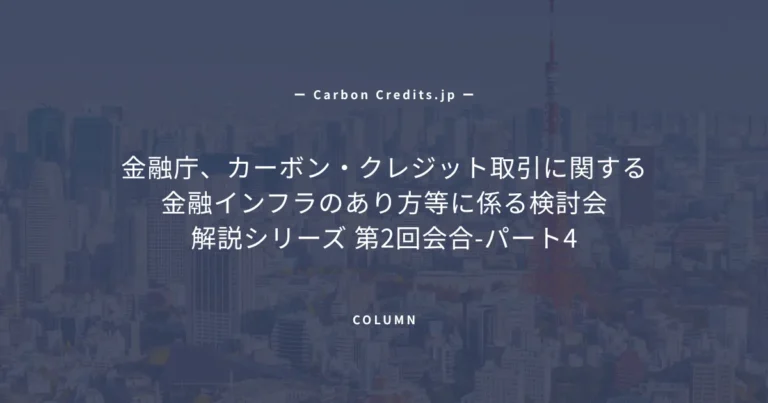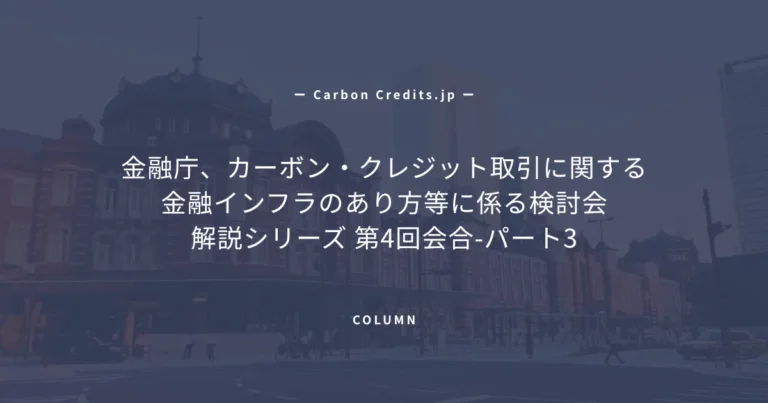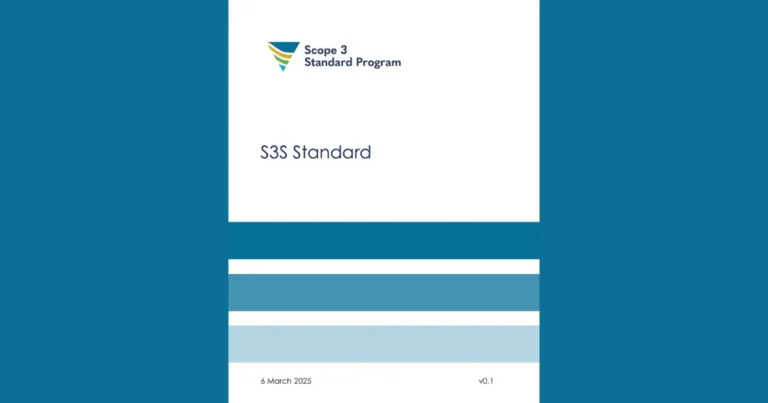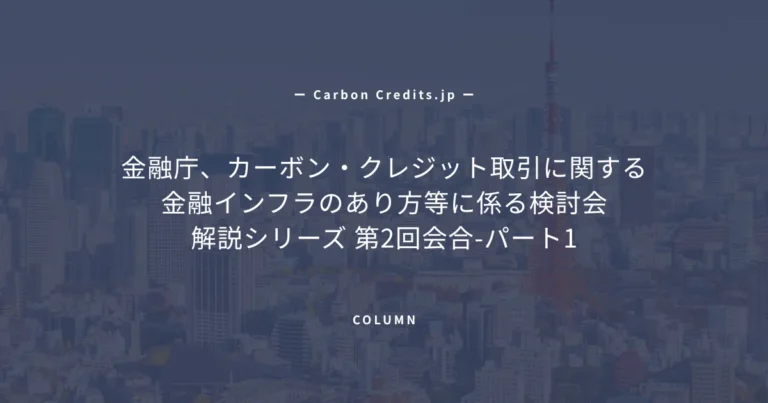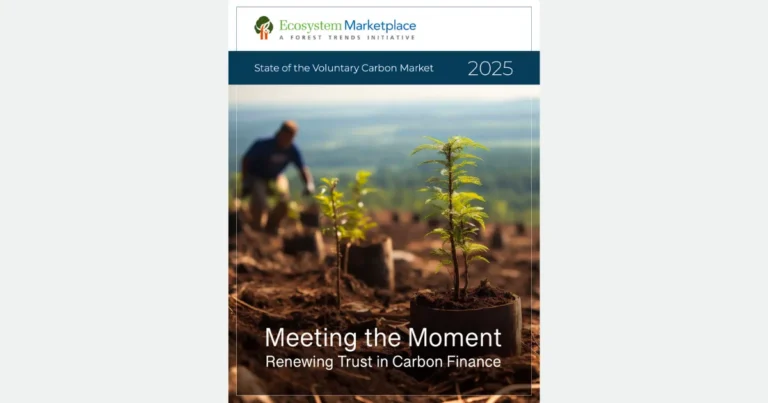金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第5回パート2
今回の検討会では、供給側の品質基準を担うIntegrity Council for the Voluntary Carbon Market(ICVCM)と、需要側でクレジット利用の開示基準を策定するVoluntary Carbon Markets Integrity Initiative(VCMI)が登壇し、グローバル市場で整合性を確保する最新フレームワークを詳細に解説した。
以下では両者のプレゼンテーションと配布資料を突き合わせ、日本の制度設計にも資する形で網羅的に整理する。
ICVCM「Core Carbon Principles(CCPs)」で供給側の品質を底上げ
ICVCMはまず、ICVCMの使命を「民間資金を質の高い排出削減・除去プロジェクトへ振り向け、2050年ネットゼロ実現を後押しすること」と説明した。
ICVCMは10項目からなるコアカーボン原則(CCPs)を基準に、プログラム認証(CCP-Eligible)と方法論認証(CCP-Approved)を「二重チェック方式(Two-Tick)」で行っていると説明。このCCPラベルは両方の認証を満たしたカーボンクレジットのみに付与され、高品質であるラベルとなる。
既にAmerican Carbon Registry(ACR)、Architecture for REDD+ Transactions (ART)、Climate Action Reserve(CAR)、Gold Standard、Verra、Isometricの6プログラムがCCP-Eligibleとなり 、方法論では、埋立ガス(LFG)、ガス漏れ検知(LDAR)、ODS破壊、REDD+、ARRなど計約5,050万t-CO2分がCCP-Approvedに到達。
市場全体の38%が既に評価対象となり、2025年前半には主要方法論の審査完了を目指していると説明した。
また継続的改善(CIWP)では、パリ協定第6.2条対応や社会的セーフガードの強化に続き、2025年にdMRV(デジタルMRV)やVVB監督、再エネ基準の見直しなどを着手予定。規制当局の受容も進み、米CFTCのデリバティブ上場指針やシンガポールMASの移行クレジット要件など、主要国がCCPsを参照基準に採用し始めていることを強調した。
VCMI 企業のクレジット利用を透明化する「Claims Code」
VCMIは、VCMIが策定したClaims Code of Practiceを用いて「クレジット使用と排出削減努力の一体的な報告枠組み」を提供すると説明した。コードは四つのステップから成る。
- ステップ1:基礎基準
企業はGHGインベントリ開示、科学的根拠に基づく短期目標、2050年ネットゼロ誓約などを満たさねばならない。 - ステップ2:クレームの選択
残存排出量の10–50%を補完する「Silver」、50–100%の「Gold」、100%超を毎年補完する「Platinum」の3区分で進捗を示す。 - ステップ3:質の高いクレジット購入と詳細開示
企業は購入・償却量、プロジェクトID、方法論、対応するArticle 6調整有無などを公開し、2026年以降はCCPラベル付与を必須とする。 - ステップ4:第三者保証
Scope 1,2排出は限定保証、その他指標は公開情報に基づく保証を要求し、MRAフレームワークで報告・審査プロセスを規定する。
VCMIはこれら基準をCSRD・IFRS・GRIなど既存開示制度とマッピング済みで、金融規制当局の開示ルールへの組込みを促進している点が特徴だ。
日本の検討会への示唆
今回示されたICVCMとVCMIの両輪は、供給側で「質の担保」を、需要側で「透明な利用と主張」を保証する国際的メタスタンダードとして機能しつつある。
日本がボランタリーカーボンクレジット市場を制度化するに当たっては、
- 国内J-クレジットなどがCCP適合を見据えて方法論をアップグレードできるか。
- 上場企業・金融機関がVCMI基準に沿った開示・保証体制を構築し、国際投資家の信頼を確保できるか。
- パリ協定6.2/6.4メカニズムとの整合をどう図るか。
といった論点が避けて通れない。
ICVCMが示したダブルチェック方式やVCMIのクレーム区分は、今後政府が設計する国内制度の「品質ラベル」および「利用ルール」のベンチマークとして活用できるだろう。特に、再エネクレジットが現行基準を満たさないと判断された事実は、日本の非化石証書制度にも直接的な警鐘を鳴らしている。
まとめ
ICVCMはCCPラベルの拡大とメソドロジー改善を、VCMIは企業報告と第三者保証の標準化を推進し、両者が連動することでボランタリーカーボンクレジット市場の信頼性を飛躍的に高めつつある。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事録.令和7年2月25日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事次第.令和7年2月21日