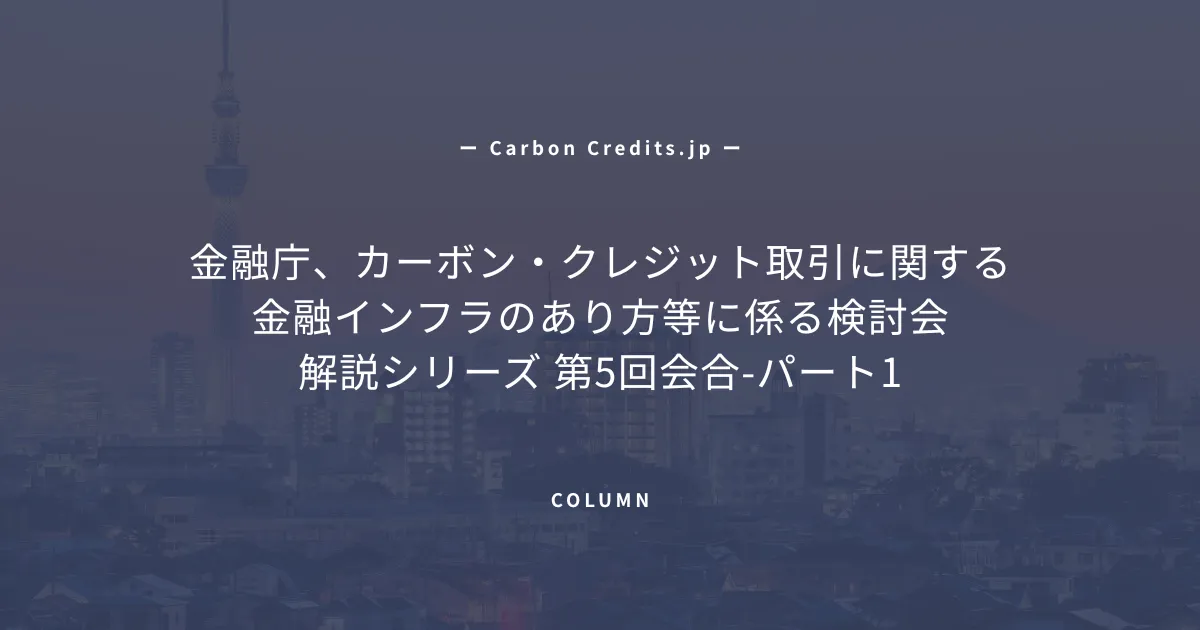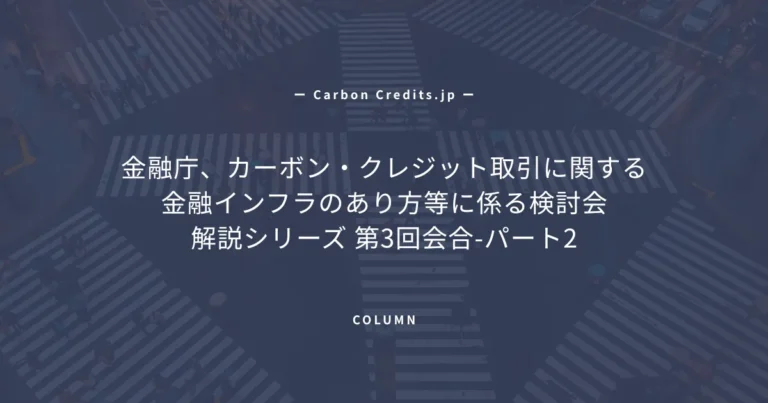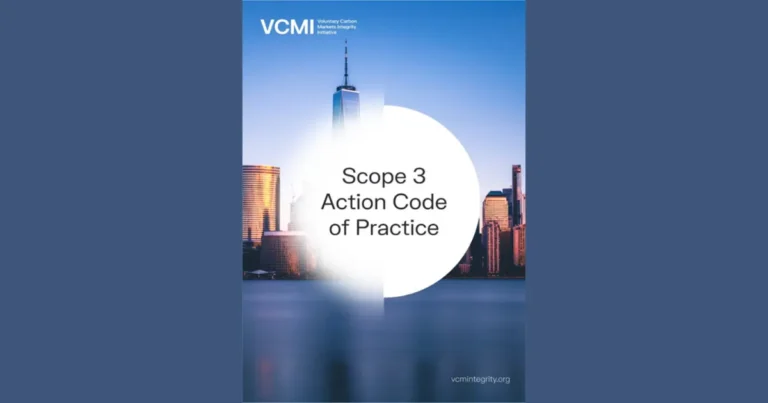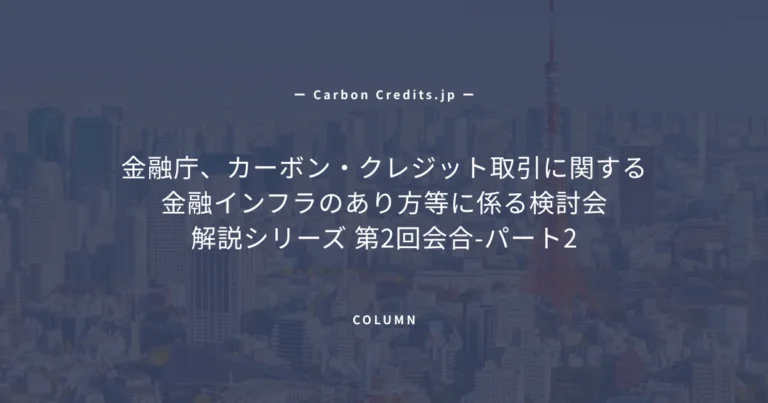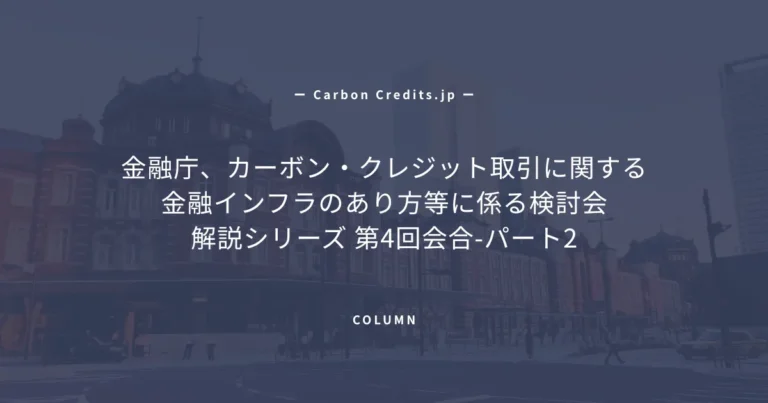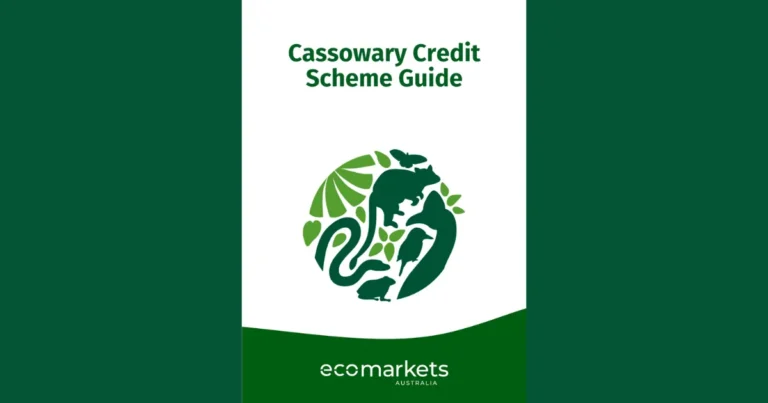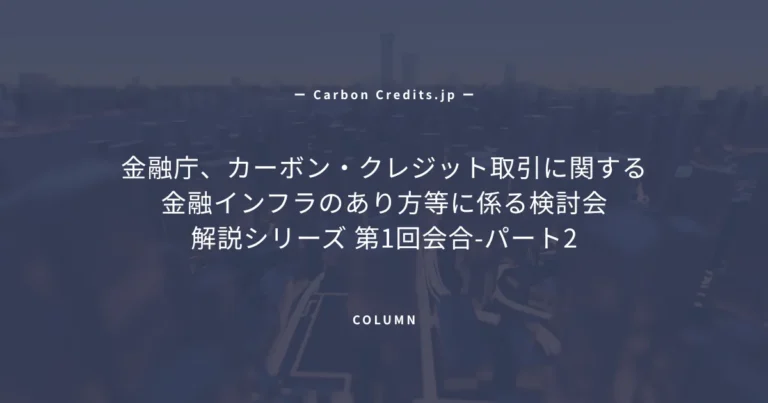金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第5回パート1
2025年2月25日、金融庁は「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)を開催し、これまでの議論を総括するとともに、国際動向と整合的なハイレベル原則の策定に向けた今後の工程表を提示した。
今回はICVCM、VCMI、ISDA、ENEOSが登壇し、市場インテグリティ確保やインターオペラビリティ拡大に関する先行事例を共有する場とも位置づけられた。
検討会設置の背景とこれまでの歩み
パリ協定以降、ボランタリーカーボンクレジット市場は急拡大し、2030年には世界規模で5,000億ドルに達するとの試算もある。こうした拡大の一方で、取引インフラの併存や二重計上リスクが顕在化していることから、金融庁は2024年6月に本検討会を発足させ、金融機関・商社・保険会社・テック企業・取引所など幅広い主体の取組と課題をストックテークしてきた。
過去4回の討議では、
- ①質の担保と購入企業のレピュテーションリスクへの手当
- ②需要拡大に資する制度的位置づけ
- ③供給不足と組成負担
- ④説明責任と投資家保護
- ⑤技術系/自然系クレジットの特性差
- ⑥市場標準化やデジタル化の意義
などの論点が議論されてきた。
国際ルール形成の潮流
事務局説明はまず、IOSCO最終報告書が示す21項目のグッドプラクティスを再掲し、規制枠組み・発行市場・流通市場・クレジット使用開示の各局面で取引の透明性と健全性を確保する必要性を確認した。
さらに米国ホワイトハウスが2024年5月に公表した「Responsible Participation Principles」、英国政府が2024年11月「Voluntary Carbon & Nature Market Integrity Principles」など、主要国が相次いで高水準のボランタリーカーボンクレジットに関する原則を公表している事実を紹介し、日本も同等の指針整備を急ぐ必要があると強調した。
論点整理からハイレベル原則へ
検討会の目的は「透明性・健全性向上による投資家保護の確保」と位置づけられている。そのうえで事務局は、厳格な取引規制をいきなり導入するのではなく、市場黎明期に適したソフトロー型の論点整理を先行させ、将来的な高位原則策定につなげる2段階アプローチを提示した。
論点は①基本事項、②仲介者・売主、③取引所・インフラ、④買主の4領域に整理され、情報開示、利益相反防止、適合性確認、リスク管理、標準化、デリバティブ取扱い、評価機関の透明性などがキーワードとして整理された。
スケジュール感
素案公表は2025年4月、取りまとめは同年5〜6月を目指す工程が示された。このタイムラインは、2026年度本格稼働予定のGX-ETS(排出量取引制度)を念頭に、民間のボランタリーカーボンクレジット市場の信頼性を制度実装前に底上げする狙いがある。
技術革新と市場拡大への示唆
前回までの議論で注目を集めたブロックチェーンやスマートコントラクトの活用は、カーボンクレジットの一意性担保やダブルカウント(二重計上)防止、取引コスト削減、小口取引の実現に資するソリューションとして改めて紹介された。
API連携による登録簿間接続やデジタル化は、発行手続き短縮と市場流動性向上に直結するため、今後の論点整理でも重要テーマとなる見通しだ。
今回提示された討議ポイント
事務局は参加者に対し、
- ①国際イニシアティブが日本市場の実務に与える示唆
- ②売手・買手双方から見た需給課題と情報開示の留意点
- ③取りまとめ案の妥当性
の3点について意見集約を求めた。
第5回会合は、世界的に加速する規制・原則整備の波を日本市場にどう取り込み、黎明期特有のリスクを抑えつつ流通量を拡大するかという実務的課題に向き合う機会と位置付けられた。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事録.令和7年2月25日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事次第.令和7年2月21日