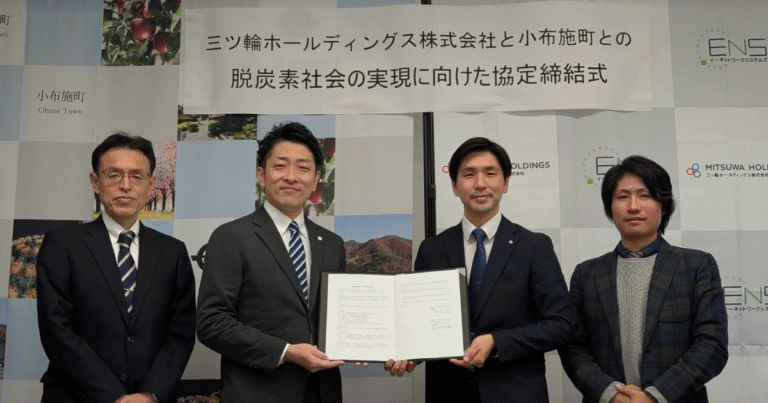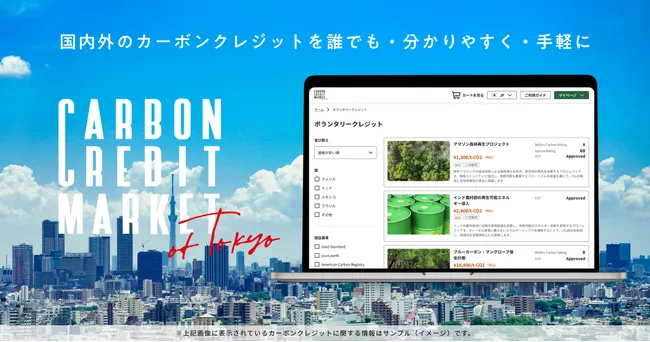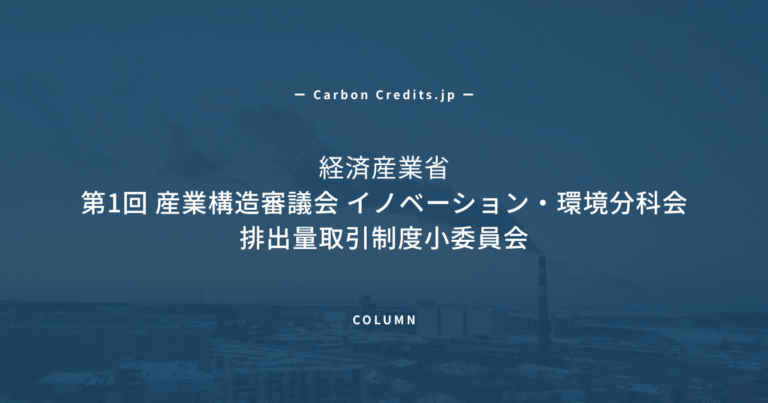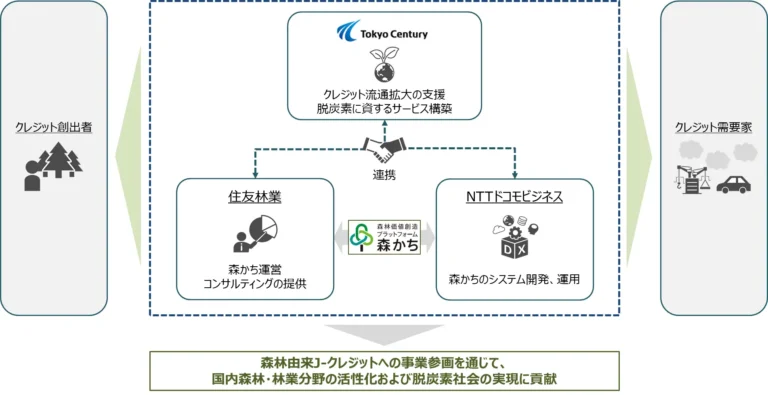農業分野のカーボンクレジット創出を手がけるJizokuは11月10日、2025年度に深刻な渇水が発生している地域では、農業系カーボンクレジットの創出を行わないと発表した。水稲の中干しが実施できない環境では、温室効果ガス削減の「追加性」が満たされないためで、同社は食料生産と地域農業の持続性を優先する判断を下した。
Jizokuはこれまで、水田の中干し(一定期間、田の水を抜いて地表を乾かす工程)を適切に管理することでメタン排出を削減し、カーボンクレジットを創出してきた。前身である一般社団法人Coの事業を含め、農業分野での排出削減プロジェクトを推進してきた。
しかし、2025年度は記録的な降水量不足により、一部地域で水稲栽培に必要な水の確保が困難となっている。このような状況で中干しを行えば収量が著しく減少する恐れがあり、地域の食料供給や農家の生計を脅かしかねない。さらに、既に水田が乾燥している場合には、中干しによる排出削減効果を追加的に得ることはできず、国際的な基準で求められる「追加性(additionality)」を欠くクレジットが生じる。
同社はこの判断について「クレジット創出を目的化するのではなく、地域の営農と環境の持続可能性を両立させる」と説明している。対象地域の水田では中干しを行わず、収量確保を優先した栽培管理を支援する方針だ。
Jizokuは今後、
- 安定した食料生産と農家の営農継続を最優先すること
- 周辺環境や地域の水資源との調和を図ること
- 長期的に高品質なカーボンクレジットを安定的に創出する体制を維持すること
を基本方針として掲げている。
片岡代表は「カーボンクレジットは“数”ではなく“質”で評価されるべきだ。まず地域の農家と食卓を守ることが、持続可能な社会への第一歩だ」と述べた。
同社はまた、渇水や気候変動リスクを踏まえ、今後は気象条件に応じた柔軟な運営を行うとともに、衛星データや生物多様性評価を組み合わせた「農業×環境データ」型のプロジェクト設計を進める方針を示した。
カーボンクレジット市場では、プロジェクトが本来の活動を超えて温室効果ガス削減を実現しているかを示す「追加性」が重要な基準とされる。農業分野では、気候条件によって削減効果の確実性が左右されやすく、国際的にも検証手法の精緻化が求められている。Jizokuの今回の対応は、クレジットの信頼性を重視する動きとして注目される。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000147505.html