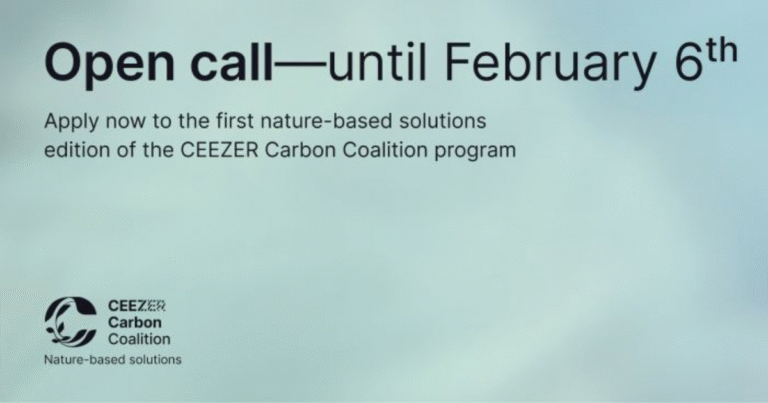東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)は10月23日、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)での炭素市場構築に関する国際会合(AZEC-DCM)」の成果レポートを公表した。報告書は、2025年5月と8月に開催された2回の国際会合の議論を総括したもので、温室効果ガス(GHG)の可視化と「十全性の高い炭素市場」の整備を両輪とする政策協調の方向性を示した。
AZECは日本やASEAN諸国、豪州など11カ国で構成され、脱炭素・経済成長・エネルギー安全保障を三本柱に掲げる地域連携枠組みである。今回の報告書では、サプライチェーン全体でのGHG排出「見える化」を進めることが、国際競争力の維持とカーボンプライシング導入の前提条件であると強調した。各国の排出量報告制度や民間企業による算定プラットフォーム整備を通じ、データの透明性を高めることが不可欠とされた。
会合では、シンガポールの炭素税、インドネシアの石炭火力向け排出量取引制度(ETS)、日本のGX-ETSなど、アジア各国のカーボンプライシング政策を比較。いずれも「脱炭素投資と価格付けを一体的に進める政策ミックス」が有効であるとの認識で一致した。
炭素市場の質的向上に向けては、パリ協定第6条に基づく制度的整備が焦点となった。各国が国内登録簿の構築を進め、二重計上を防止し、透明性を確保する体制づくりを急ぐ。日本が主導する二国間クレジット制度(JCM)は31カ国に拡大し、世界で280件超のプロジェクトを支援。2030年度までに累計1億トン、2040年度までに2億トンのCO2削減を目指す。
レポートでは、農業や炭素回収・貯留(CCS)など新たな削減分野への展開も明記。特に稲作メタン削減技術「間断灌漑(AWD)」やバイオ炭のJCM手法が導入され、フィリピンやベトナムなどで試行が始まった。さらに、移行クレジットを活用した石炭火力の早期退役モデルや、アジア域内でのブルーカーボン・プロジェクト創出も議論された。
ERIAは、域内各国が制度整備段階に差はあるものの、透明性・整合性・信頼性の確立こそが市場拡大の鍵だと指摘。次回の第3回AZEC首脳会合(2026年予定)に向け、共通指標や登録簿の相互運用性確保など具体的課題を整理する方針を示した。
参考:https://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251023002/20251023002.html
参考:https://www.eria.org/database-and-programmes/topic/asia-zero-emission-center/publications/azec-international-conference-to-develop-carbon-market-azec-dcm