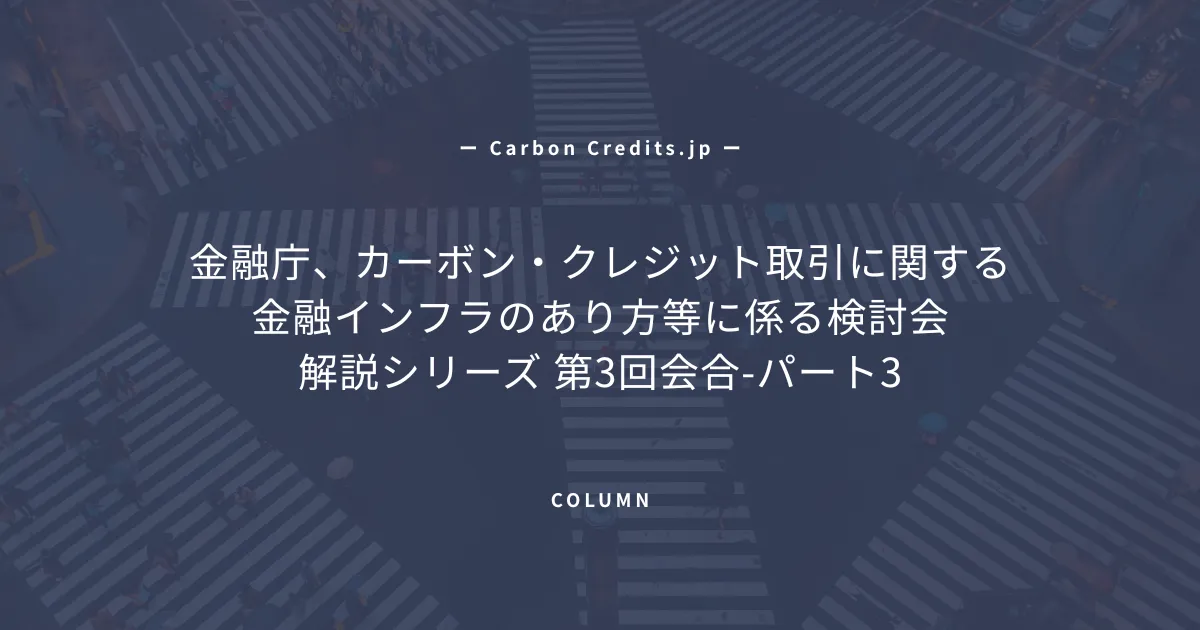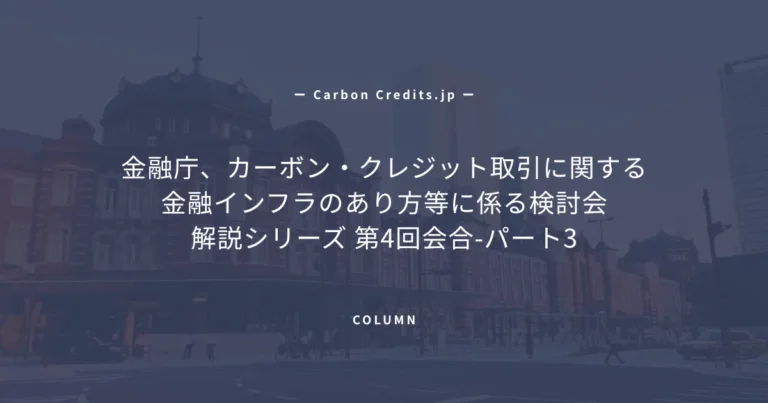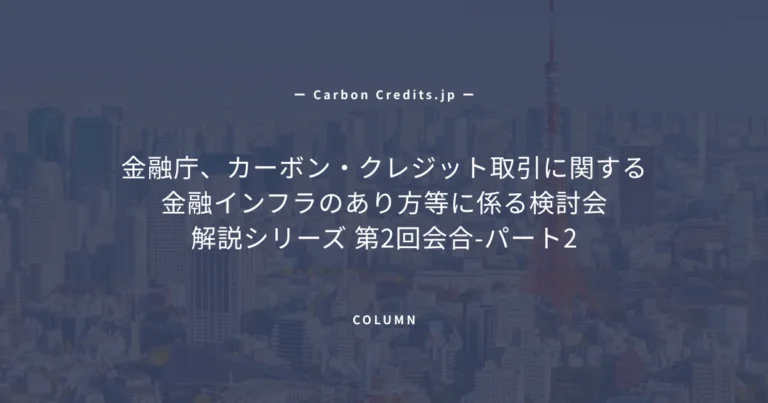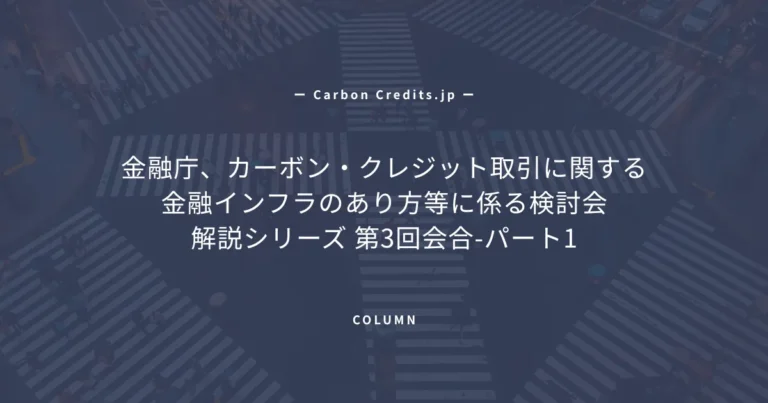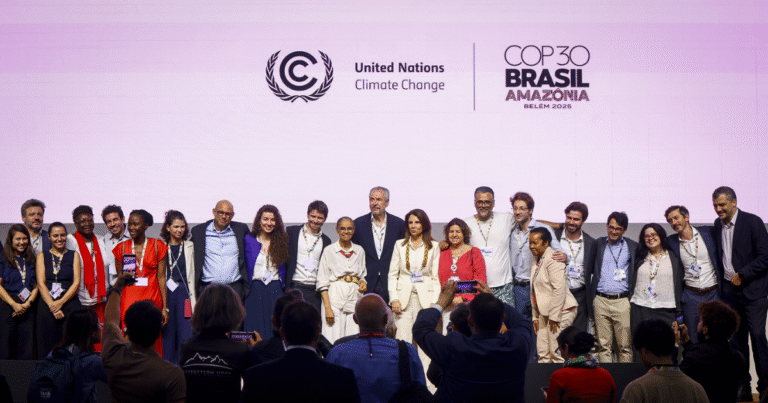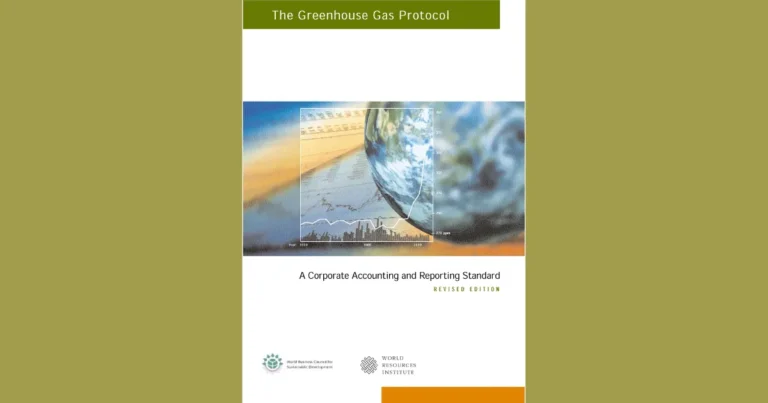金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第3回パート3
2024年11月19日開催の「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第3回)」後半パートでは、法的位置づけの明確化から国際連携、保険商品やリテラシー向上策まで、日本のカーボンクレジット市場拡大に不可欠な論点が縦横に議論された。
第3回会合では、参加メンバーから以下2点が主要論点として提示された。
- 相対取引に関する投資家・顧客保護の在り方
- クレジット信用補完(保険・評価等)の現状と課題
相対取引に関する投資家・顧客保護
相対取引の拡大には、法的位置づけの明確化と最低限の品質基準、そして仲介者による丁寧な情報提供が必須となる。
法的位置づけの曖昧さ
課題として、現在ボランタリーカーボンクレジットは金融商品か否かが未整理の状況が挙げられた。この点については、金融庁・経産省の横断的検討が求められる。現在、GX排出量取引制度研究会では排出枠の扱いが議論中だが、ボランタリーカーボンクレジットについてはは射程外であり、将来的な法改正の余地が残っている。
品質担保と標準化
IOSCO報告書では、特にデューデリジェンス、取引仲介者の説明責任、市場データの開示が鍵と整理され、品質担保においてはICVCMのコアカーボン原則(CCPs)など国際基準を活用し、国内ガイドラインを整備することで重複規制を回避する必要がある。
リテラシー向上と説明責任
また説明責任として、仲介者・販売者は「クレジット」「非化石証書」「内部削減」の選択肢を整理した上で顧客に提示する必要があることが指摘された。
前提として、企業の排出削減優先順位が①自社削減→②サプライチェーン削減→③カーボンオフセットであり、オフセットはあくまで最終手段であることをを明示する必要性も指摘された。
規制アプローチの検討軸
規制については、二軸で検討する必要がある。
- ハードロー:ライセンス制・登録制で仲介者を監督する選択肢。
- ソフトロー:業界指針や自主ガイドラインで対応し、市場のイノベーションを阻害しない手法。
市場実態(取引主体の規模・目的)を把握した上で段階的に適用することが現実的である。
カーボンクレジット信用補完サービス
保険・第三者評価は市場信頼性を高める有力手段である一方で、リスク評価モデルと再保険体制の整備が不可欠だ。
保険需要拡大の背景
グリーンウォッシング批判の高まり、プロジェクト失敗リスク(森林火災、CCS設備故障など)が企業の不安要因として挙げられる。東京海上日動火災はレピュテーションリスク補償を提供していることを説明し、関連事例として欧州での再保険も進展し、ロイズ組合も商品認可を拡大中といった情報が共有された。
保険引受けにおける課題
保険引受けにおける課題としては、カーボンクレジット種別が多様かつ流通量が少ないためリスク母数が不足する点が挙げられ、また、山火事、機器故障、納品遅延など既存保険で扱うリスクに分解し、確率モデルを適用する方針などが提案された。
評価・格付けサービス
また、保険会社の内部評価だけでなく、専門評価機関(BeZero等)が提供する格付けを併用し、投資家が複眼的にリスクを判断する必要性について指摘された。一方で、利用者は「100%依拠」せず、自社の気候戦略との整合性を確認するべきといった指摘も挙げられた。
今後の論点
再保険マーケット拡大の必要性について、欧州大手再保険会社と国内保険会社の協調がカギとされた。また衛星データ・IoTを活用したデジタルMRV(dMRV)により保険金支払いの客観性を向上を目指す、 監査・保証・保険の重複コストを抑え、カーボンクレジット本体への投資を促進を目指す必要性についても整理された。
まとめ
本コラムでは、相対取引の投資家・顧客保護とクレジット信用補完の課題を整理した。
市場拡大に向けては、ボランタリーカーボンクレジットの法的位置づけと最低限の品質基準を明確化すること、仲介者によるリテラシー向上と透明な情報開示を徹底すること、保険・評価サービスを組み合わせた信用補完スキームを整備すること、が不可欠と結論付けられる。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)議事録.令和6年11月19日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)議事次第.令和6年11月18日