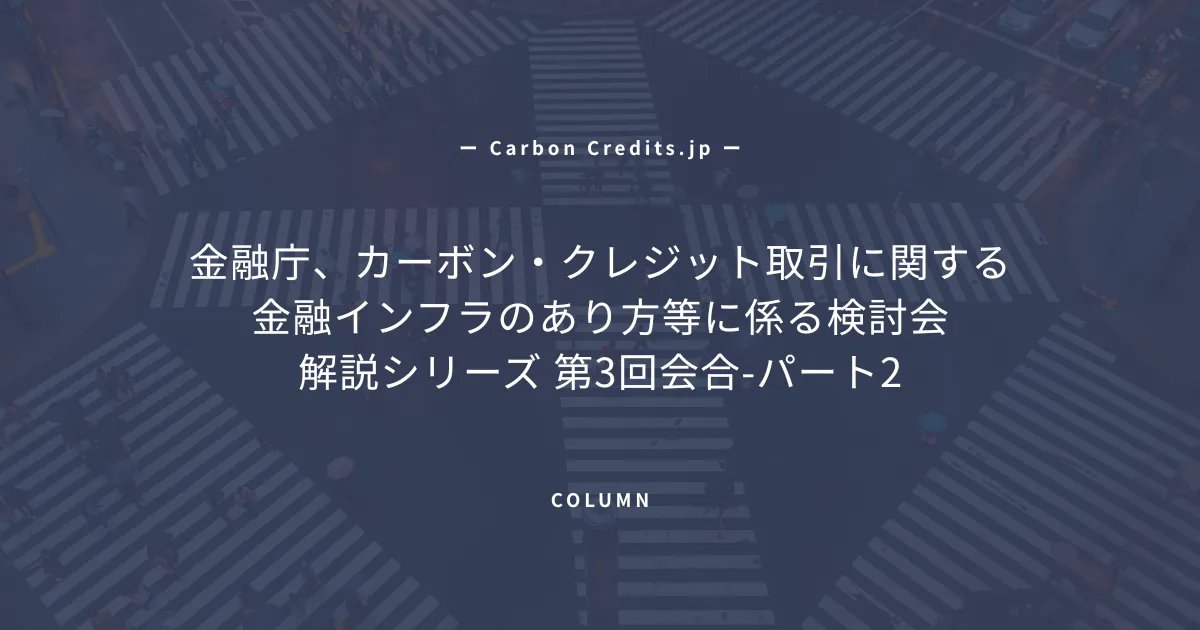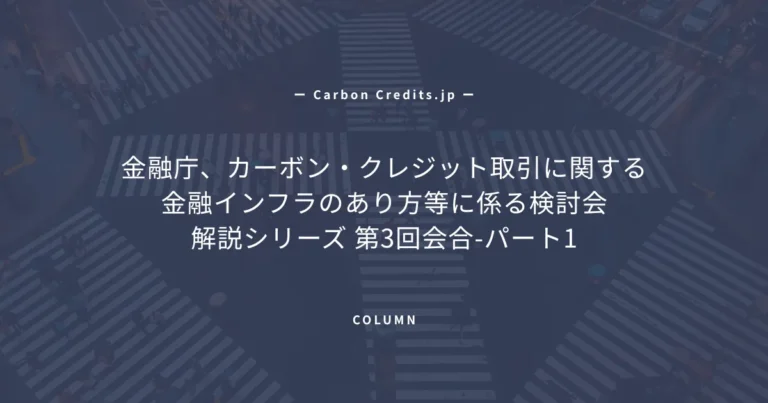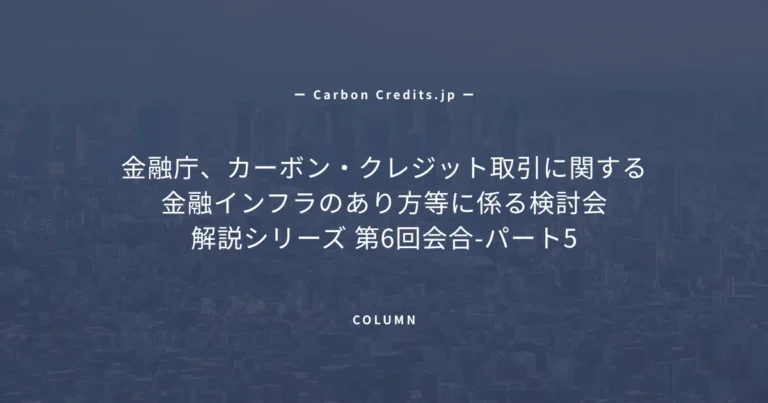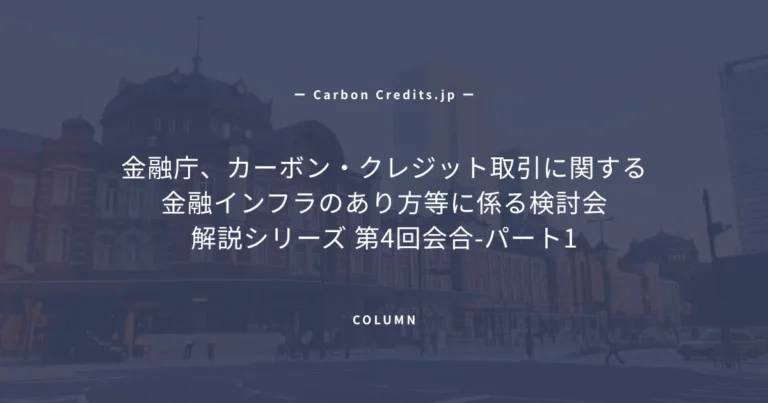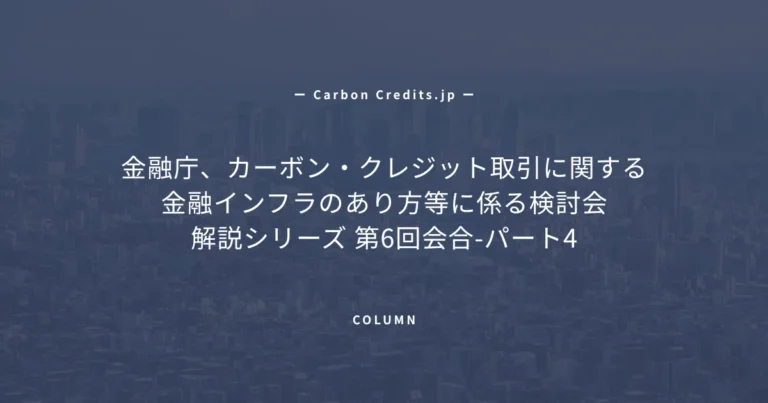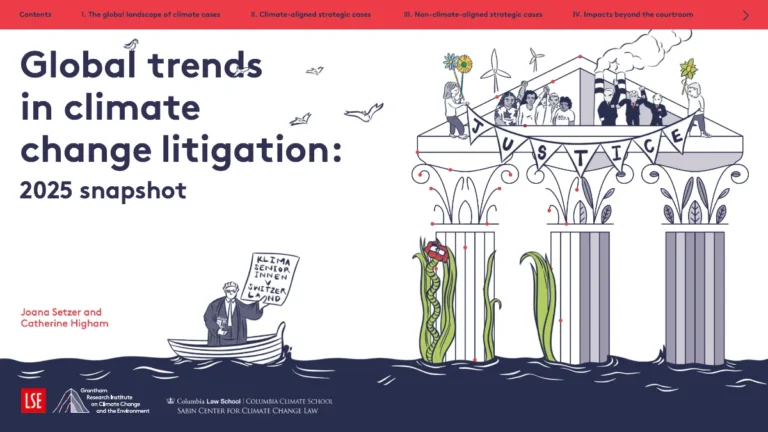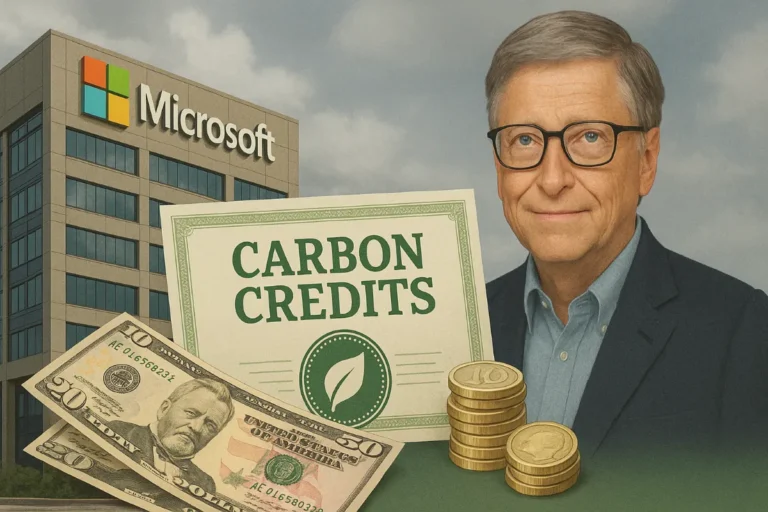金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第3回パート2
2024年11月19日に開催された第3回検討会では、証券・商社・保険の3社、大和証券、三菱商事、東京海上日動火災保険が、それぞれプレゼンテーションを行い、日本のボランタリーカーボンクレジット市場及びコンプライアンスカーボンクレジット市場を金融面からどう底上げするかについて最新の取り組みを共有した。
本稿では各社発表の要点を網羅的に整理し、市場形成に向けた論点を整理する。
大和証券「流動性と価格発見を支えるマーケットメイカー」
大和証券は、京都議定書時代にクレジット連動債(CO2Lボンド)を組成した頃からカーボンファイナンスに関与してきたと説明。
同社のタイムラインを見ると、2015年にEU ETSへの参入を皮切りに、2022年のGXリーグ賛同を経て、2023年のJPXカーボン・クレジット市場開設時に唯一の証券系マーケットメイカーとして参画、24年度も制度に再登録している。
市場創造を後押しするため、欧州再エネファイナンスに強みを持つGreen Giraffeへの出資や、Aquila Capitalとの戦略提携など海外プレーヤーとの協業も進めており、M&Aアドバイザリー機能と再エネ投資商品の開発力を強化し、国内外双方で資金循環を起こす狙いを説明した。
参考:株式会社大和証券グループ本社.Green Giraffe への出資について.2019年10月 30日
参考:大和エナジー・インフラ株式会社.Aquila Capitalの資産運用子会社とコメルツ銀行の戦略的資本提携.2024年1月25日
商品面では、政府のGX移行債フレームワーク策定を支援したほか、脱炭素投資信託などのアセットマネジメント商品も継続的にローンチ。CO2Lボンド以来築いてきた「利息とクレジット価格を結び付ける仕組み」を新たなファンド設計に展開することで、長期資金を炭素削減プロジェクトへ導く姿勢だ。
国内市場では、取引実証段階から板を提供しており、「適正価格が示されれば排出削減インセンティブが可視化される」として、EU ETSの価格変動要因分析で培ったリスクヘッジ手法を国内市場にも移植する計画を説明した。
三菱商事「NextGen CDR Facility でニワトリ卵のジレンマを解消」
三菱商事は、世界最大のカーボンクレジット開発会社South Poleと共同で2022年に立ち上げたNextGen CDR Facilityを軸にプレゼンを行った。
参考:三菱商事株式会社.革新的な炭素除去技術の普及・促進を目的としたNextGen CDR Facilityについて.2023年4月26日
まず、IPCC AR6データに基づき、2050年時点でも50〜160億tの残余排出が見込まれ、その60〜70%(約100億t)が技術由来の除去で埋められる必要があるというファクトを提示した。その上で、現状の供給パイプラインは2030年ニーズを大きく下回り、需給ギャップは最大10倍規模に拡大する恐れがあるとし、その背景には「大量購入があればコストを下げられる」とする供給側と、「価格が下がれば大量購入する」とする需要側のニワトリ卵問題があり、プロジェクトの FID(最終投資決定)が進まない点を指摘した。
打開策として同社は、政府の財政的インセンティブに加え、民間がプレミアム価格で長期購入コミットメントを出す二層構えを提案。NextGenはこの民間インセンティブ部分を「需要集約→長期オフテイク→資金安定供給」というスキームで具現化し、BCG、Swiss Re、商船三井など5社から購入コミットを集め、長期契約を締結している。同ファシリティはプロジェクトサイドにも資金を先行注入し、コストカーブを早期に下げるエコシステム構築を目指す戦略を説明した。
東京海上日動「保険でクレジット取引の信頼と裾野を広げる」
損害保険大手の東京海上日動は、保険商品の開発を通じてカーボンクレジット市場の安心と拡大を支えるアプローチを示した。
企業購入リスクをカバー
同社は 「カーボンクレジット・レピュテーション費用保険」 を国内で初めて開発。これは企業が購入したカーボンクレジットの品質を巡りグリーンウォッシング批判を受けた場合、危機管理コンサル費用やネット投稿削除費用、緊急会見費用などを補償するというものだ。
参考:東京海上日動火災保険株式会社.【国内初】カーボンクレジットの購入企業向け専用保険の開発.2024年7月19日
背景には情報開示の厳格化と市場規模500億ドル(2030年予測)の拡大があり、企業価値毀損リスクを軽減することで需要側の参入障壁を下げる狙いだ。
同保険はレピュテーション、価値毀損、規制変更など複合リスクを射程に置く設計で、保険料をテコに市場信頼性を引き上げを目指す戦略と説明した。
生活密着型クレジット創出スキーム
さらに、自動車保険のテレマティクス機能を活用し、安全運転で削減した燃料由来CO2を J-クレジット化し、売却益を契約者へ電子クーポンで還元するスキームも紹介。登録は 2024年8月で、個人向け保険を入り口にカーボンクレジット創出と消費者インセンティブを循環させる国内初の試みである。
三業態の役割分担が見えた
今回の3社発表は、
- 証券が「流動性と価格発見」、
- 商社が「長期オフテイクによる供給側の投資確度向上」、
- 保険が「取引リスクの低減と小口創出の裾野拡大」
という補完関係を浮かび上がらせた。
議論はまだ制度設計段階だが、各社の民間イニシアティブが重層的に市場機能を補強し、結果としてGX-ETSを含む国内のカーボンククレジット市場の厚みを増す構図が描かれつつある。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)議事録.令和6年11月19日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)議事次第.令和6年11月18日