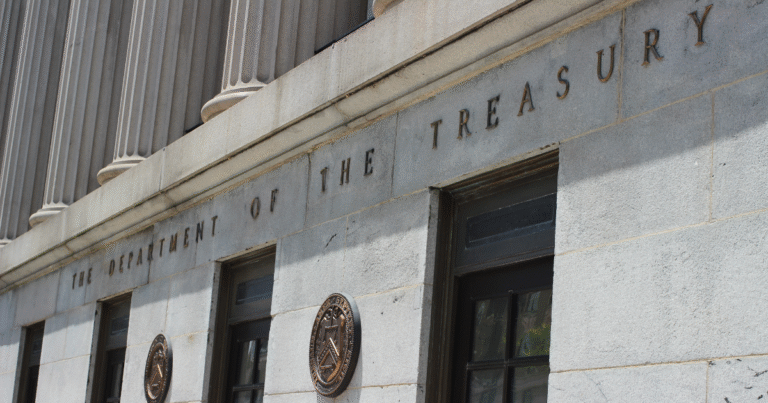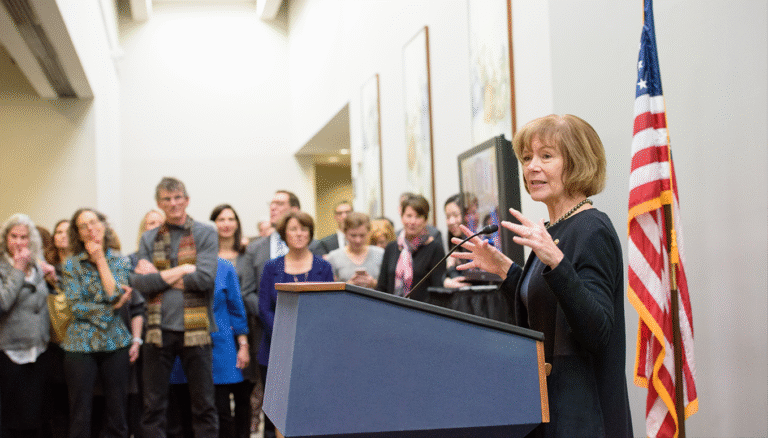国際海事機関(IMO)は10月17日、ロンドンで開催された臨時の海洋環境保護委員会(MEPC)において、国際海運に対する炭素価格制度(カーボンプライシング)の導入をめぐる決定を1年間延期することを決めた。米国とサウジアラビアが強く反対し、57か国が延期案に賛成、49か国が反対、70か国が棄権した。次回会合は2026年10月に再開される予定である。
今回の議題は、IMOが4月に承認した「ネットゼロ枠組み(Net Zero Framework, NZF)」の採択であった。これは、船舶の温室効果ガス(GHG)排出を2050年までに実質ゼロとすることを目指すもので、燃料の炭素強度基準とグローバルなGHG排出価格メカニズムの2本柱で構成されている。
米国が「制裁」を示唆 EU・太平洋諸国の主導に反発
この枠組みでは、総トン数5,000トンを超える船舶に対し、2008年比で2035年までに30%、2040年までに65%のGHG排出強度削減を義務付ける方針だった。基準を下回った船舶には2028年以降、排出量1トン当たり最大380ドル(約5万9,000円)の課金が予定されていた。削減目標を上回る事業者は、カーボンクレジットを発行・取引できる仕組みも提案されていた。
しかし、トランプ米大統領はこの案を「グリーン新税詐欺」と非難し、米国は交渉から離脱。支持国に対し「制裁・ビザ制限・港湾料金の引き上げ」などを警告した。サウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)、中国も米国側に立ち、採決を1年延期する動議を提出した。
環境団体と島嶼国が反発 「脱炭素化の勢いが後退」
主導してきた欧州連合(EU)やCOP30ホスト国のブラジル、気候変動の影響が大きい太平洋島嶼国は、炭素価格導入で得られる収入を「低炭素燃料導入支援」や「途上国支援基金」に充てる構想を支持していたが、今回の決定で進展は後退した。IMOのアルセニオ・ドミンゲス事務局長は「この混乱を繰り返してはならない」と述べ、加盟国に協調を呼びかけた。
オランダの金融機関INGの輸送・物流担当上級エコノミスト、リコ・ルーマン氏は「合意形成の時間は得られたが、勢いが失われつつある。最悪の場合、制度そのものが頓挫しかねない」と懸念を示した。
「海運版カーボンクレジット市場」創設は暗礁に
NZFは、排出超過船舶に「補償単位(remedial units)」の購入を義務付け、排出削減達成船舶が余剰分を売却できる市場を創出する構想だった。これにより、国際的な「海運版カーボンクレジット市場」が形成され、IMO主導の「ネットゼロ基金」を通じて、燃料転換と開発支援を促す仕組みが想定されていた。
しかし、主要排出国の政治的対立により、制度の実施は再び不透明になった。専門家の間では、「炭素価格なしでは海運業の排出は増え続け、IMOの気候戦略の信頼性が問われる」との指摘が相次ぐ。
IMOは10月20〜24日に予定される温室効果ガス削減作業部会で、実施ガイドラインの検討を続行する予定だが、制度化は少なくとも2026年以降に持ち越される見通しである。