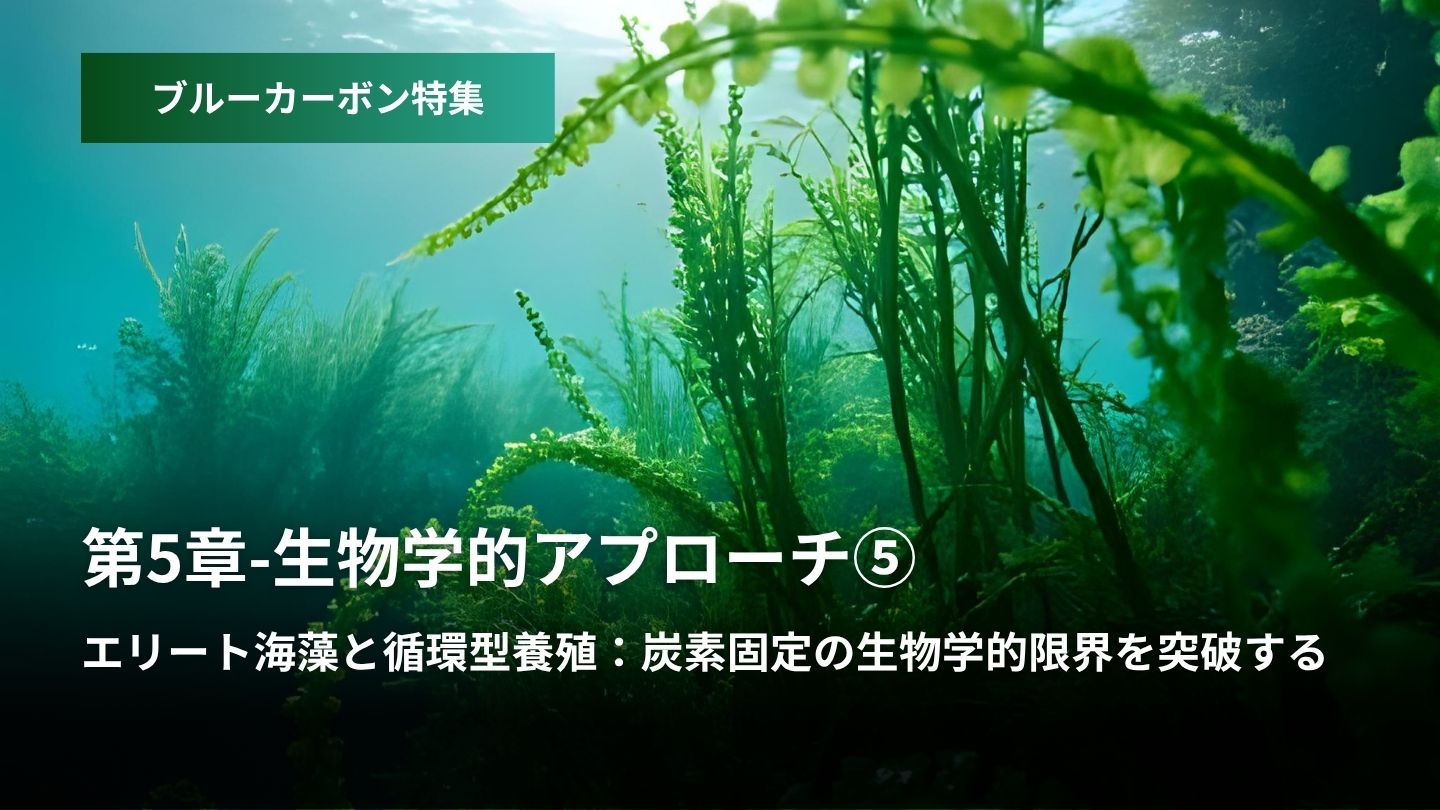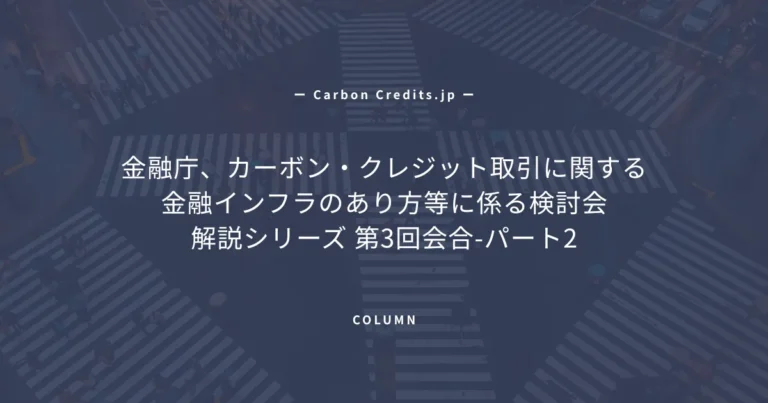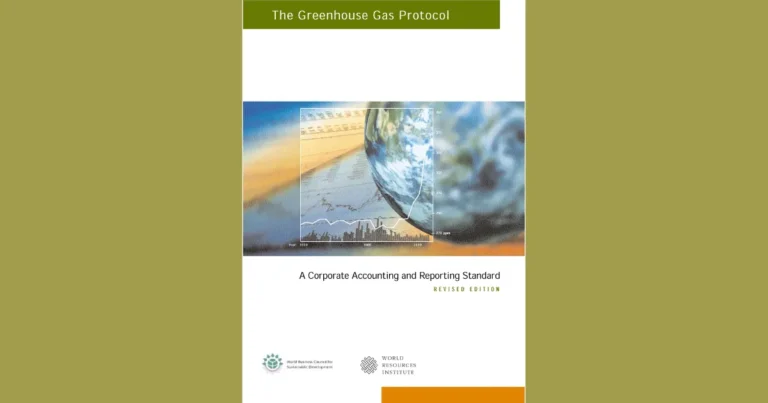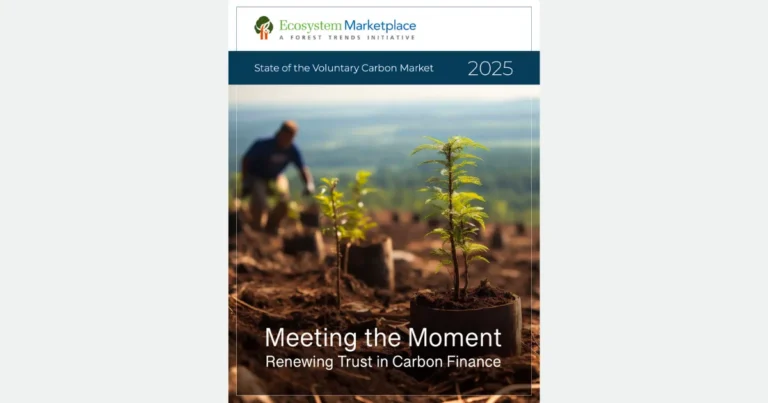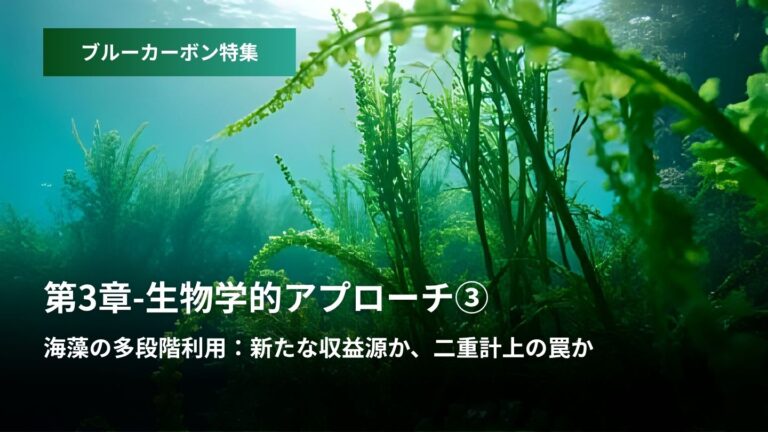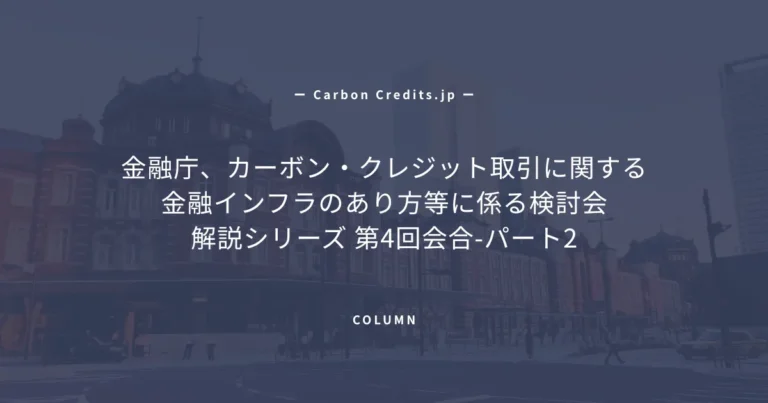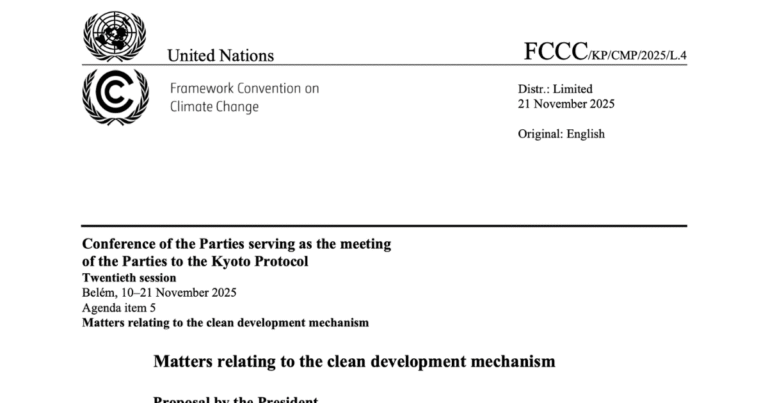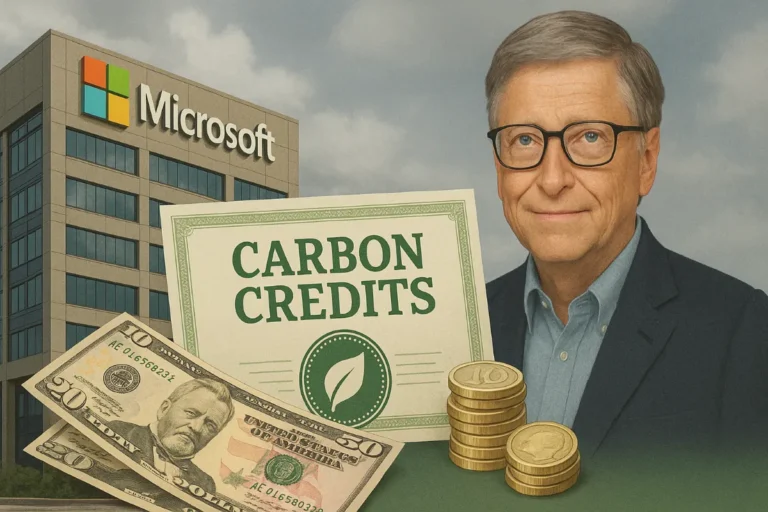【キーワード定義】
- 育種(Breeding):生物の遺伝的性質を利用して、より優れた形質(例:成長が速い、環境ストレスに強い)を持つ品種を人為的に作り出すこと。
- IMTA(Integrated Multi-Trophic Aquaculture / 統合多栄養段階養殖):複数の栄養段階にある生物(例:魚類、海藻、貝類)を同じ場所で同時に養殖するシステム。ある生物の排出物(排泄物や残餌)を別の生物の栄養源として利用し、環境負荷を低減しつつ生産性を高める。
- 生物生産性(Biological Productivity):特定の生態系において、生物(特に植物や藻類)が光合成によって有機物を生産する速度や量。カーボンクレジット創出の経済性に直結する。
【導入】
前章では、「沖合養殖」と「バイオ炭化技術」を組み合わせることで、ブルーカーボンをギガトン級の炭素除去(CDR)産業へとスケールアップさせる道筋を示した。
しかし、この壮大な工学的システムの経済性は、最終的に入力となる「海藻」自身の性能、すなわち生物生産性に依存する。単位面積あたり、いかに効率よく炭素を固定できるか。
この生物学的な根本効率を高めない限り、大規模な設備投資を正当化することは難しい。本章では、生物学的アプローチの最終章として、海藻の性能を極限まで引き出す「育種」と、養殖システム全体を最適化する「IMTA」を探求する。
【1. 科学的原理と国際的文文脈】
このアプローチは、炭素固定の「エンジン」である生物そのものを改良し、その「稼働環境」を最適化することを目指す。
育種
陸上の農業と同様に、海藻においても、より望ましい形質を持つ個体を選抜・交配することで、優れた品種を創り出すことが可能である。目標となる形質は、①単純な成長速度、②高い炭素含有率、③病気や高水温への耐性、④沖合の過酷な環境に耐える強靭さ、など多岐にわたる。
近年では、ゲノム編集技術などのバイオテクノロジーを活用し、特定の遺伝子を改変することで開発期間を短縮する研究も進んでいる。
IMTA
これは「海の循環型農業」とも言えるモデルである。例えば、魚類(給餌種)を養殖すると、その排泄物や食べ残しの餌によって、海域の窒素やリンの濃度が上昇し、富栄養化の原因となる。しかし、この窒素やリンは、海藻(吸収種)にとっては成長に不可欠な栄養塩である。
そこで、魚の養殖場の隣で海藻を育てることで、海藻は豊富な栄養を得て通常より速く成長し、同時に海水を浄化する。さらに、底層に沈む有機物をナマコや貝類(堆積物食者)が消費すれば、生態系全体として無駄のない、持続可能な生産システムが完成する。
国際動向
カナダやノルウェー、チリなど、大規模なサケ養殖が盛んな国々では、IMTAは環境負荷を低減する次世代の養殖モデルとして国家レベルで研究開発が推進されている。
また、世界の研究機関が連携し、主要な海藻種のゲノム解読を進めており、炭素固定能力に関わる遺伝子の特定競争が始まっている。これらの基礎研究が、将来の「エリート海藻」開発の基盤となる。
【2. カーボンクレジット化の論点】
生産性を高めるこれらのアプローチは、クレジットの「量」を増やす上で魅力的だが、新たな論点も生む。
追加性(Additionality)
育種によって開発された新品種やIMTAモデルを導入することが、従来の養殖方法(ベースライン)と比較して、どれだけ「追加的」な炭素吸収量を生み出すのかを定量的に証明する必要がある。特に育種の場合、「その品種を使わなければ達成できなかった吸収量」を明確に示さなければならない。
システム境界の複雑化
IMTAの場合、MRVのシステム境界をどこに設定するかが問題となる。純粋な海藻の炭素固定量だけを計上するのか、あるいは魚類養殖による環境負荷(富栄養化)の低減といった便益も評価に含めるのか。後者を含めるとダブルカウントのリスクが生じるため、通常は海藻バイオマスに固定された炭素量のみがCDRクレジットの対象となる。
遺伝子組換え生物(GMO)への懸念
ゲノム編集などの先端技術を利用した場合、その生物の環境への影響や社会受容性が課題となる可能性がある。クレジット認証機関や購入者が、GMO由来のクレジットをどう評価するかは、まだ未知数な部分が大きい。
【3. 日本市場の展開と政策環境】
日本は、ノリやワカメ、コンブといった食用の海藻で世界トップクラスの育種技術と長い歴史を持つ。この知見の応用が期待される。
日本市場
国内の各都道府県の水産試験場では、古くから地域環境に適した海藻の品種改良が行われてきた。これらの既存の研究基盤を、カーボンクレジット創出という新たな目的に向けて活用する動きが出始めている。IMTAに関しても、カキ養殖と海藻養殖を組み合わせるなど、伝統的な漁業の中にその原型を見出すことができる。
政府は「みどりの食料システム戦略」の中で、持続可能な養殖業の推進を掲げており、IMTAモデルの導入は政策的な後押しを受けやすい環境にある。ただし、異なる魚種の養殖を同じ海域で行うには、漁業権の調整など、法制度上の課題をクリアする必要がある。
【4. 経済的実行可能性とリスク】
生産性の向上は、プロジェクトのROI(投資対効果)を直接的に改善する。
コスト構造
育種には長期的な研究開発投資が必要となる。一方、IMTAはシステムが複雑になる分、管理コストや専門知識が余計に必要となる。しかし、魚介類などの高付加価値産品を同時に販売できるため、カーボンクレジット価格の変動に強い多角的な収益構造を築けるという大きなメリットがある。
収益性
単位面積あたりのバイオマス収量が増加すれば、それだけ多くのカーボンクレジットを創出でき、収益性が向上する。IMTAの場合、「高品質な魚+海藻+クレジット」という複数の収益源の組み合わせにより、プロジェクト全体のリスクを分散できる。
リスク要因
育種した品種が自然の生態系に流出し、遺伝子汚染を引き起こす環境リスク。また、IMTAでは、一部の生物で発生した病気がシステム全体に広がるリスクも考慮する必要がある。
【5. 今後の展望とシリーズの総括】
育種とIMTAは、生物学的アプローチによる炭素固定の効率を最大化するための、いわば「最後の詰め」の技術である。これまでの章で見てきた、永続性の担保(第2章)、ダブルカウントの回避(第3章)、大規模化(第4章)といった課題をクリアした上で、この生物学的生産性の向上が実現して初めて、ブルーカーボンは経済的に成立する産業となりうる。
これにて、生物の光合成という生命活動を起点とする「生物学的アプローチ」の探求は一区切りとなる。しかし、海洋におけるCDRの方法はこれだけではない。生命に頼るのではなく、海洋の広大な化学的ポテンシャルに直接働きかけるアプローチも存在する。次なるシリーズでは、この「化学的アプローチ」の第一歩として、海にアルカリを加えてCO2吸収能力を高める「海洋アルカリ化」の原理と課題を解説していく。
【ブルーカーボンクレジット創出への接続】
認証スキームとの関係
これらの技術は、プロジェクトの追加性を証明する上で強力な根拠となる。ベースラインとの比較において、育種やIMTAがもたらす生産性向上が、プロジェクトの妥当性を支える。
クレジット発行プロセスにおける役割
プロジェクト設計書(PDD)において、採用する品種の優位性や、IMTAモデルによる物質循環の効率性を定量的に記述することが求められる。これは、プロジェクトが生み出すクレジット量の算定の根幹をなす部分である。
生物学的アプローチが、太陽光エネルギーを生物を介して炭素固定に利用するのに対し、次から探る化学的アプローチは、鉱物や電気化学的なエネルギーを用いて海洋の炭酸システムに直接介入し、炭素を除去する。これは、ブルーカーボンにおける全く異なる、そして巨大な可能性を秘めた技術体系である。