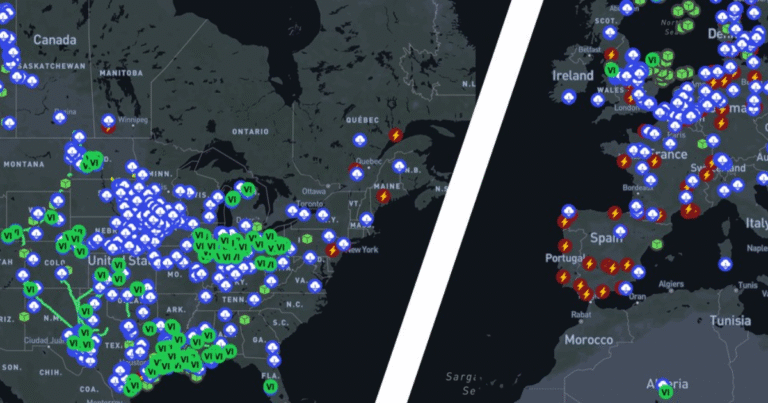オーストラリア政府は9月18日、2035年までに温室効果ガス(GHG)排出量を2005年比62〜70%削減する新たな国家目標を発表した。2050年のネットゼロ実現に向けた中間ステップとして位置付けられ、同時に包括的な「ネットゼロ計画」と6分野別ロードマップも公表された。これには、炭素除去(CDR)の大規模拡大が柱として盛り込まれている。
今回の削減幅は、気候変動庁(Climate Change Authority)の独立助言に基づき決定された。アンソニー・アルバニージ首相は「野心的だが達成可能な範囲であり、投資と技術革新を加速させる国家利益にかなうものだ」と強調した。
ネットゼロ計画は、電力の脱炭素化、電化と効率化、クリーン燃料拡大、新技術の導入に加え、「ネット炭素除去の拡大」を5つ目の優先分野に掲げた。植林や土壌炭素貯留に加え、直接空気回収(DAC)や炭素回収・貯留(CCS)の商業化支援が含まれ、オーストラリアの農業・土地利用部門に新たな収益源をもたらす可能性がある。
特に農業・土地部門計画では、生産性向上と同時に「自然修復と炭素蓄積」の促進を打ち出した。地域経済に利益をもたらすとともに、国際的なカーボンクレジット市場に向けた供給拡大を見据えている。
電力・エネルギー計画では、2030年までに再エネ比率82%を達成する方針を維持。送電網強化「Rewiring the Nation」や投資促進スキームにより、再エネ供給の拡大を進める。資源部門では、重要鉱物の供給強化に加え、炭鉱でのメタン排出削減やCCS導入を進める。
また、産業部門では脱炭素化のための新技術投資を促進し、輸出競争力を維持する「Future Made in Australia」戦略と連動。これにより低炭素製品を国際市場へ展開する狙いがある。
オーストラリア財務省の試算によれば、秩序立った移行は経済成長や雇用維持に資する一方、遅れれば電力価格の上昇や投資機会の喪失を招くと警告する。ネットゼロ計画は、パリ協定の国別目標(NDC)を履行するのみならず、「国際的な投資誘致と輸出競争力維持の鍵」と位置付けられている。
今後は、2030年の再エネ比率82%達成に向けた進捗と、CDR技術の商業展開が成否を左右する。政府は今後数年で具体的な炭素除去プロジェクトや市場制度設計を進める見通しだ。
参考:https://www.dcceew.gov.au/about/news/setting-2035-target-path-net-zero#toc_0