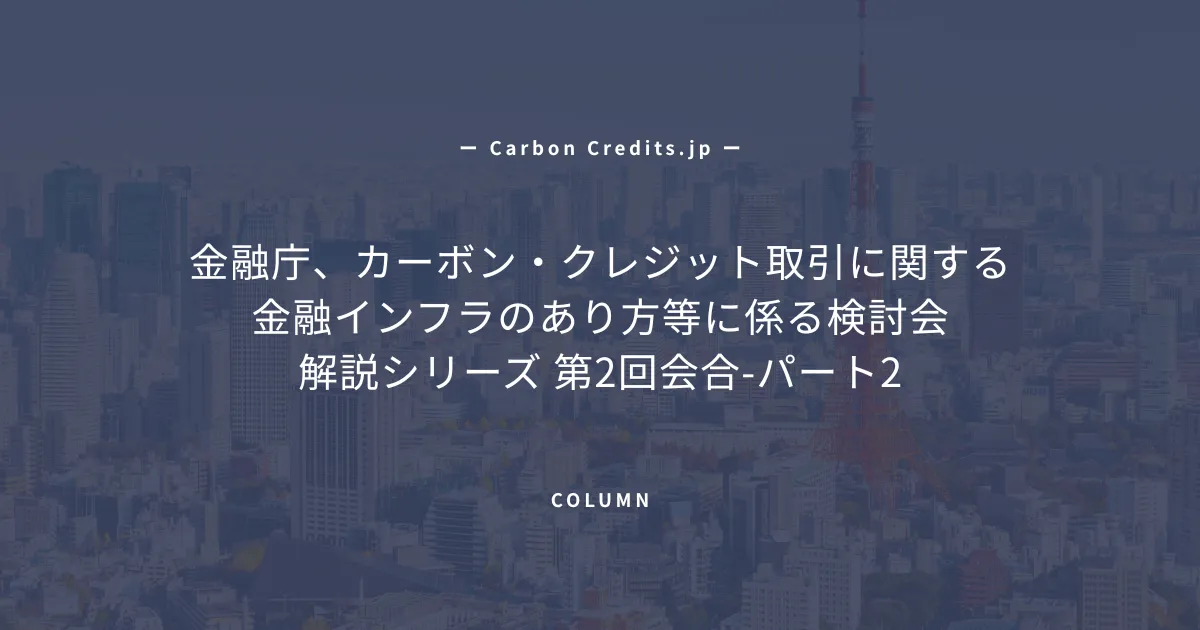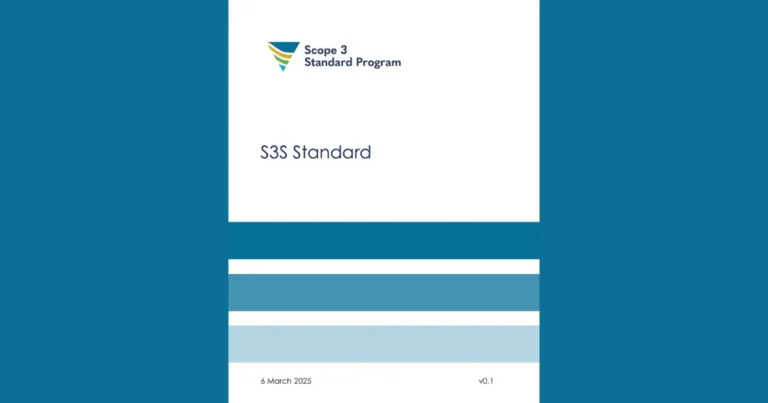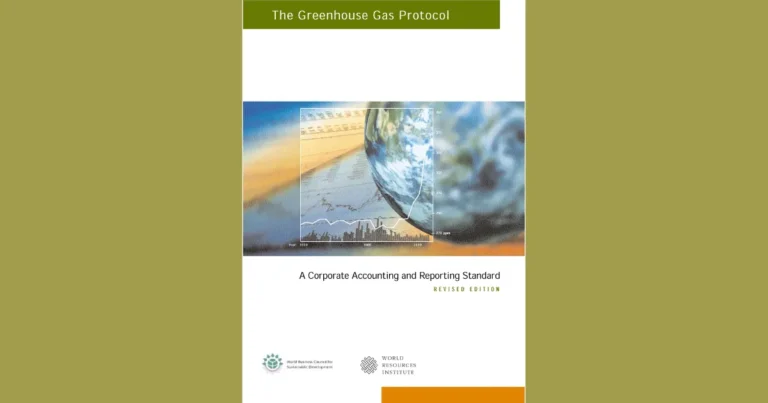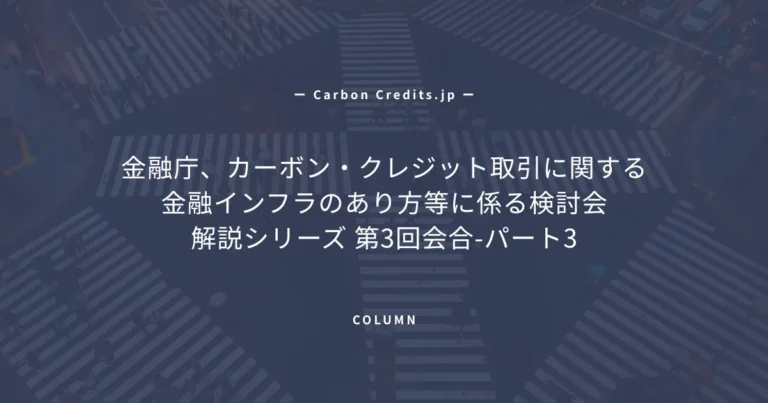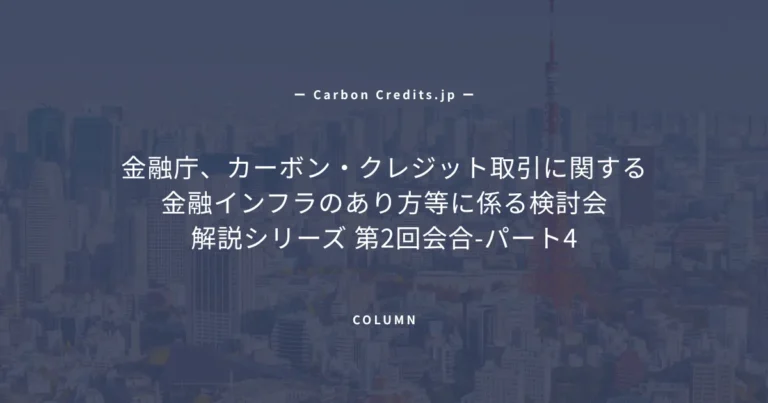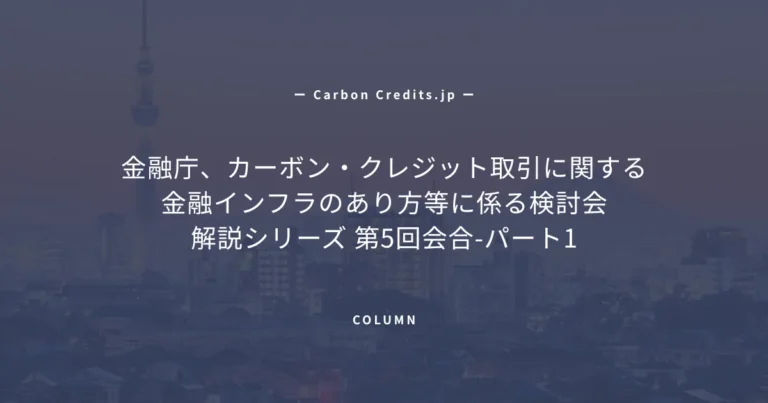金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第2回パート2
2024年9月10日、金融庁と環境省の共催による第2回検討会が開かれ、山陰合同銀行、中国銀行、横浜銀行という3つの地域金融機関が、各自のカーボンクレジット関連ビジネスを発表した。
座長の根本氏は冒頭、「地域での取組実態をきめ細かくストックテイクすることが、金融インフラ整備の第一歩だ」と強調。
プレゼンテーションと質疑応答では、森林由来カーボンクレジットや再エネ由来カーボンクレジットの創出から、非化石証書を組み込んだローン商品、プログラム型の小規模プロジェクト運営、さらには自動車サプライチェーンの移行金融まで、多層的な実践例と課題が浮き彫りとなった。
地銀3行の取り組み紹介
山陰合同銀行「仲介から創出・融資へ 「地域一体モデル」の進化」
山陰合同銀行(ごうぎん)は、2009年に鳥取県と協働でJ-VER(現J-クレジット制度)普及を始めて以来、森林由来カーボンクレジットを中心に「地産地消」を推進してきた。2023 年度までの販売仲介は376件、1万2,104t-CO2に達し、特に2021年以降は気候意識の高まりを追い風に件数・量とも急伸している。
昨年からは「創出支援業務」を立ち上げ、自治体・森林組合と組んでプロジェクト登録書類の作成から販路までワンストップで支援しており、奥出雲町との協定では570haの森林で2.9万t-CO2を創出予定とした。
更に、電力子会社ごうぎんエナジーと連携し、非化石証書を寄贈する「カーボンオフセットサポートローン」を商品化し、短期間で19件を実行し、中小企業に「まず体験してもらう」導入口を設けたと説明した。
中国銀行「太陽光のプログラム型で裾野拡大を狙う」
中国銀行は 2024年1月、全国の銀行で初となるプログラム型J-クレジット事業「ちゅうぎんカーボンクレジットクラブ」を始動。自家消費型太陽光発電を導入した個人・法人を束ね、総量2万3,948t-CO2の排出削減を8年間で達成する計画を掲げた。
入会者の削減量を取りまとめてカーボンクレジット化し、売却益を参加者へ還元するインセンティブ設計が特徴で、8月末時点で25件、年間205t-CO2削減量が集まっており、クラブ外では、森林組合と組んだ約5.5万t-CO2の創出案件や、水稲栽培の中干し延長法を農家へ紹介するなど、農業・林業分野のカーボンクレジット供給源を着々と育成中。
また私募債手数料を活用したJ-クレジット寄贈スキームも打ち出し、239t-CO2の販売を実現していることを説明した。
横浜銀行「啓発から移行金融へ、都市型モデルの挑戦」
横浜銀行は2019年から段階的にSDGs融資を展開し、2023年以降は脱炭素を本格化。法人3万社を35人の渉外担当でカバーするため、「啓発→可視化→開示→削減」のステップを設計し、事業性評価を軸にエンゲージメントを進めている 。
地域への入口商品として、私募債発行額の0.1%でJ-クレジットまたは非化石証書を購入・無効化し、神奈川県や横浜市の公共施設・イベントをカーボンオフセットする「カーボンオフセット型私募債~横浜ゼロ~」を全国に先駆けて導入。
さらに、道銀や七十七銀など6行と組む「MEJAR サステナビリティ連携」で共同セミナーやアンケートを実施し、J-クレジット創出ノウハウの相互補完を図っていると説明。自動車サプライヤー向けには、神奈川産業振興センターと協働した中小版トランジション・ファイナンスを構築し、EV化やカーボンニュートラルへの対応設備への資金需要を掘り起こしている。
質疑応答で浮上した5つの論点
- 地域性とスケーラビリティ
参加メンバーからは「地域連携による横展開」の重要性が指摘され、横浜銀行のMEJAR連携や中国銀行のクラブ方式が拡張可能な雛形として注目された。 - カーボンクレジットの品質とグローバル基準
グローバル企業が海外基準のボランタリーカーボンクレジットを選好するケースとのギャップが話題に。横浜銀行は「現時点で具体的な要望はないが、次のステップとして議論が必要」と応答し、標準化議論の深化が宿題となった。 - 価格形成と地産地消
メンバーからの「地域プレミアムをどう設定するか」と質問に対し、山陰合同銀行はストーリー性を重視した高値形成、中国銀行は東証市場価格を参考に中立なプライシング、と対照的なスタンスを示した。 - 収益機会と顧客保護
各行とも「短期的な直接収益より、融資・ソリューションの入口」と位置づける一方、優越的地位の濫用回避や過大購入防止などリスク管理策を説明。特にプログラム型では「創出リスク」のモニタリングが必須との認識で一致した。 - 行員リテラシーと外部ガイドライン
メンバーからの「行員教育は不可欠か」との問いに、3行はいずれも環境省の脱炭素アドバイザー資格取得や階層別研修、アンバサダー制度で底上げを図ると回答。
見えてきた政策的示唆
議論を通じ、金融インフラ整備の鍵は「地域金融の自律的イノベーション」と「品質・価格・リスクを担保する共通ルール」の両立にあることが鮮明となった。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第2回)議事録.令和6年9月10日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第2回)議事次第.令和6年9月9日