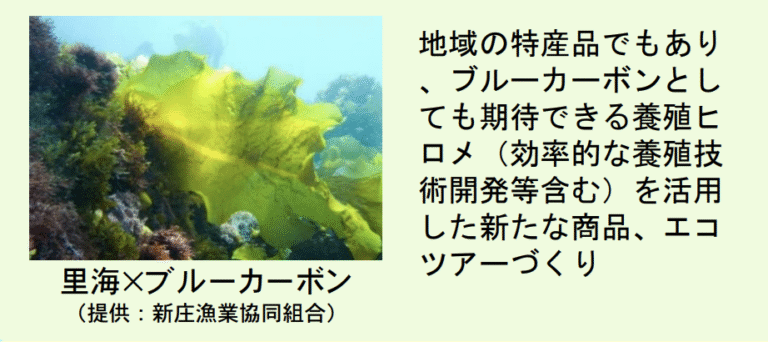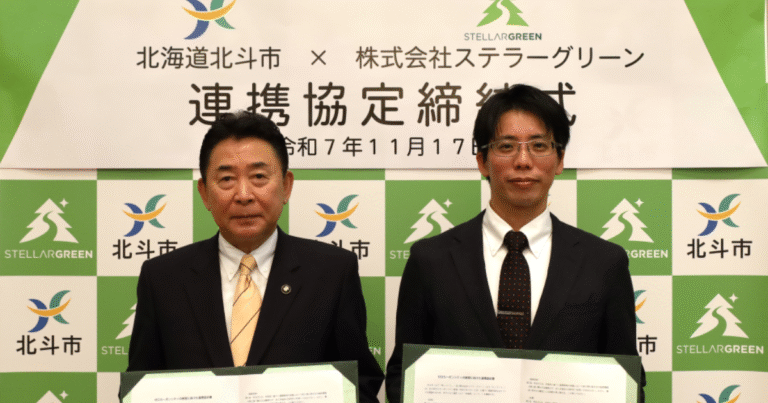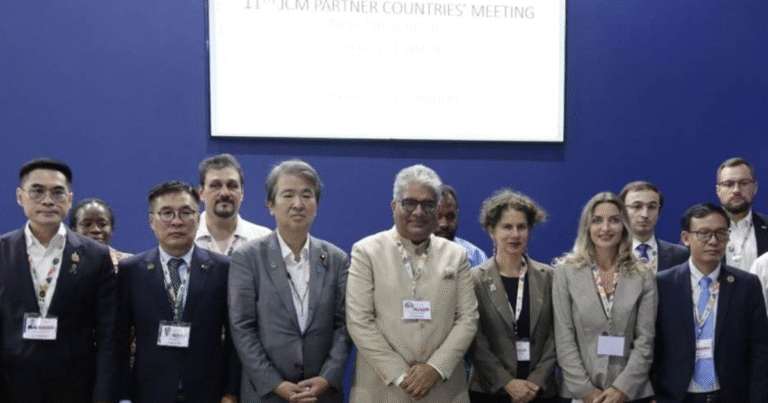一般社団法人日本ガス協会は、再生可能エネルギーへの移行と同時に、現実的かつ柔軟なアプローチを模索している。
2025年6月、日本ガス協会は「ガスビジョン2050」と「アクションプラン2030」を発表し、天然ガスとCCUS(炭素回収・利用・貯留)を組み合わせる方針を明示した。本コラムでは、こうした方針が意味するものと、e-メタンを中心としたカーボンニュートラル戦略との関係を整理する。
天然ガスの「脱炭素対応エネルギー」としての再定義
第7次エネルギー基本計画において、天然ガスは「カーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー」と明記された。日本ガス協会によれば、2050年時点の都市ガス供給の構成は、e-メタンやバイオガスによるものが50〜90%、残りの10〜50%は天然ガスとされている。

ただし、この天然ガスは単体で使用されるのではなく、必ずCCUSやオフセットなどと組み合わせて使用されることが前提とされる。
e-メタンの供給限界と現実的な補完策
e-メタンは、水素と回収したCO2を反応させて生成される合成メタンであり、既存のガスインフラがそのまま利用可能である点が強みである。
政府やガス業界は2030年にe-メタンおよびバイオガスの供給量を1%、2050年には最大で90%まで高める目標を掲げている。
一方で、e-メタンの製造には高コスト・高エネルギー消費が伴い、技術的・経済的な制約からその普及速度には限界がある。これを補完する手段として、CCUSやネガティブエミッション技術(NETs)の利用が組み込まれている。
段階的移行を支える社会的・制度的インフラの構築
都市ガス業界は、e-メタンを用いたカーボンニュートラル化を進める一方で、既存インフラの有効活用による移行コストの低減を重視している。LNG受け入れ基地や導管網、利用機器などがそのまま使用可能であることは、社会全体の追加的負担を抑える上で重要である。
さらに、日本ガス協会は、国際的なCO2カウントルールの整備やクリーンガス証書制度の活用を通じて、物理的にはe-メタンが届かない地域にも環境価値を供給できる体制を構築している。
まとめ
本コラムでは、都市ガス業界が掲げる「e-メタン中心、天然ガス補完型」のカーボンニュートラル戦略について整理した。現時点ではe-メタンへの完全移行は困難であり、CCUSと天然ガスの組み合わせが不可欠な過渡期的対応となる。
今後は、供給技術・制度整備・経済性の3点を支えに、脱炭素とエネルギー安定供給の両立を目指す道が現実解といえる。