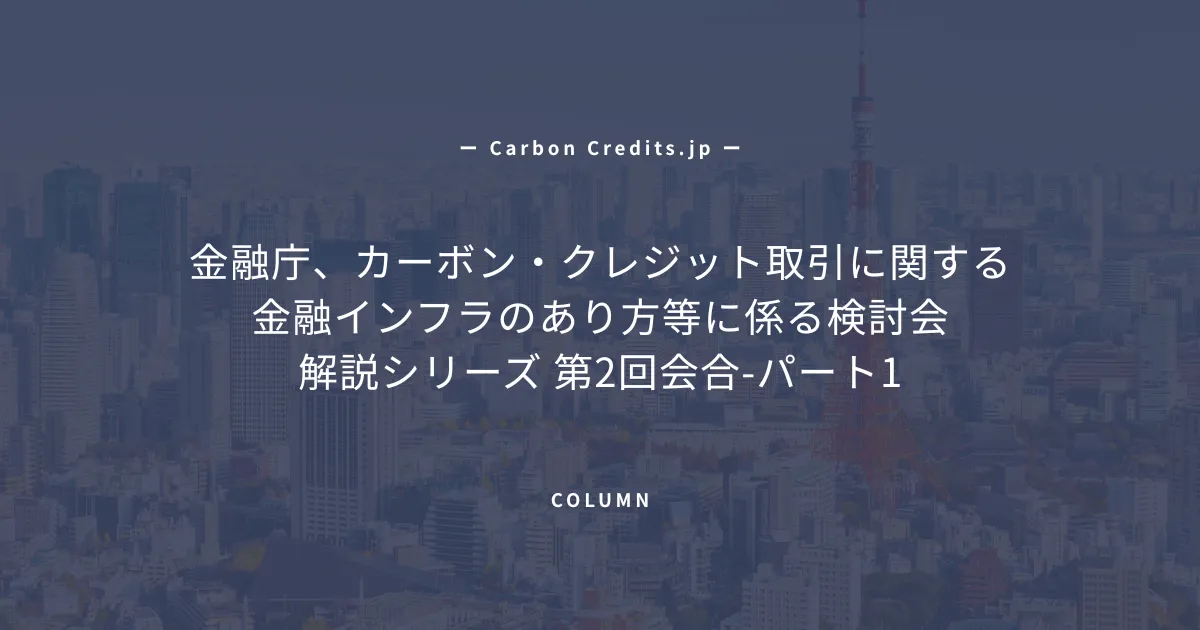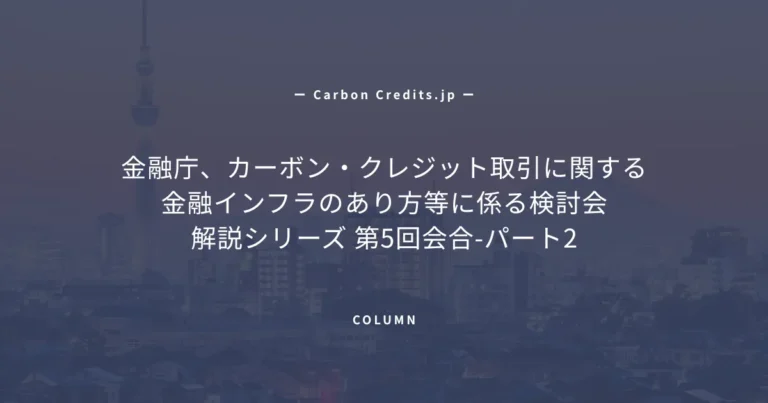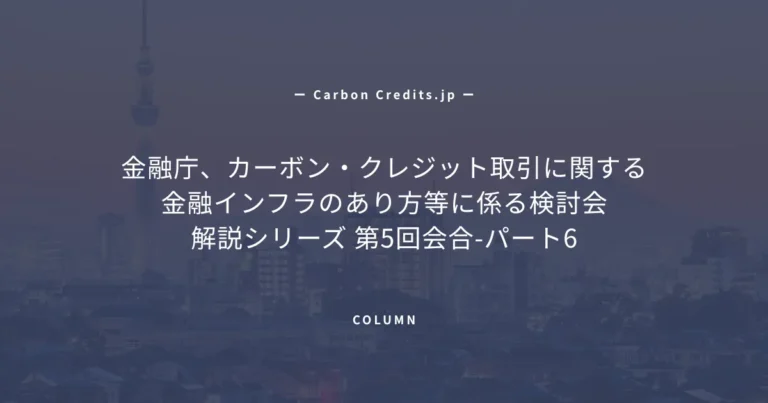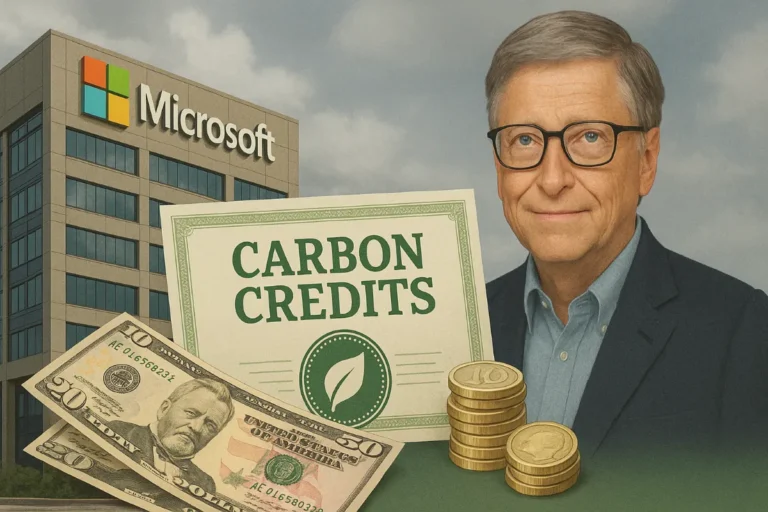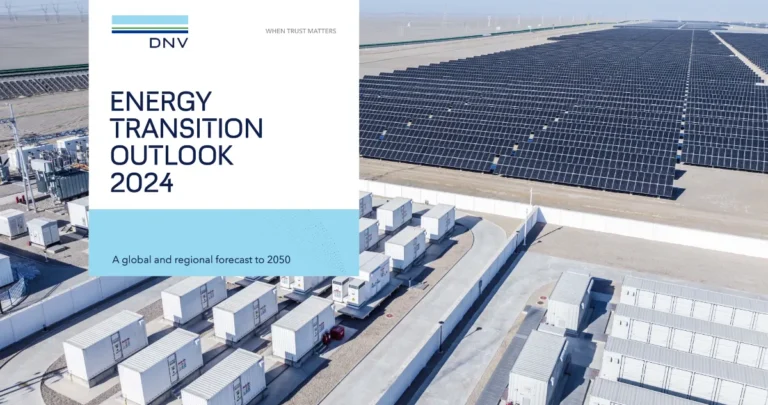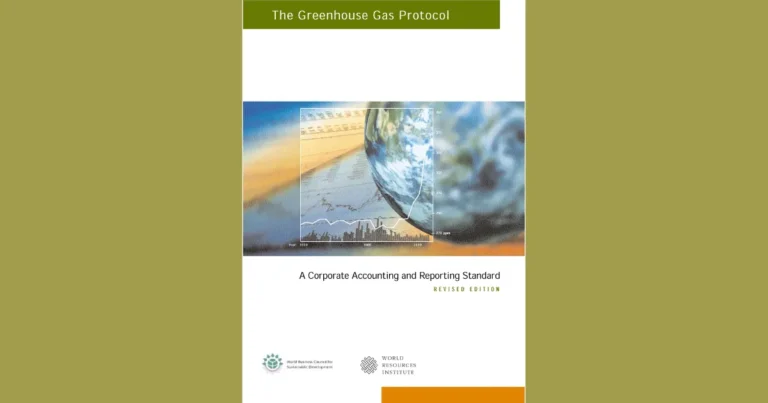金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第2回パート1
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、カーボンクレジット市場は国内外で急速に拡大している。一方で、市場の拡大に比例して、取引の透明性や健全性、投資家保護といった課題も浮き彫りとなった。そこで金融庁は2024年6月より「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(以下、検討会)を立ち上げ、金融実務家・有識者とともに論点整理を進めている。
本コラムでは、2024年9月10日に開催された第2回検討会の冒頭部分を中心に概要を整理し、今後の議論に向けたポイントを提示する。
検討会の位置づけ
検討会は、カーボンクレジット取引の「インフラ」と「市場慣行」を俯瞰的に検証する場として金融庁が主催。第1回では、メガバンク3行の取組事例を踏まえ、市場全体の課題感を共有した。
第2回からは論点を深掘りするフェーズに入り、地域金融とテック活用という2つの視点から議論がスタートしている。
開会挨拶にみる基本方針
開会挨拶では、カーボンクレジット市場の健全な発展を促すうえで「取引の透明性・健全性の確保」が不可欠であると、改めて強調された。カーボンクレジットは国内排出削減だけでは賄えない残余排出を埋める「最後の一手」として期待されている一方で、投資家保護の視点で、需要の拡大とともに、カーボンクレジット品質やダブルカウント(二重計上)リスクなどの情報開示が求められる。
2026年度に本格稼働予定のGXリーグ排出量取引制度「GX-ETS」を見据え、いま議論を開始することの意義を強調した。
第1回の振り返り
事務局は、第1回で提起された論点を「需給構造」「品質評価」「国際連携」「顧客説明」の4点に整理した。
- 需給構造:メガバンクはカーボンクレジット調達ネットワークを構築しつつあるが、中小企業の取引参加は限定的。
- 品質評価:技術系・自然系双方で国際的な認証基準の比較検討が必要。
- 国際連携:IOSCO報告書案ではメタレジストリ構想が示され、グローバルな相互運用性が課題。
- 顧客説明:投資家のリスク理解を支える開示フォーマットの整備が不可欠。
第2回の進行と論点設定
根本座長は、第2回の目的を「地域金融の実践事例の共有」と「テック活用の可能性評価」と位置づけた。
地域金融の役割として、地方銀行が地域内でカーボンクレジットを組成・利用し、付加価値として「地産地消」を訴求する動きが生まれている。
またテック活用の観点では、ブロックチェーンによるトレーサビリティ向上や二重計上防止の期待がある一方、トークン化による商品複雑化リスクも指摘されている。
まとめ
本コラムは、第2回検討会の冒頭部分を概観し、議論が向かう方向性を整理した。次回の「パート2」では、地域金融機関3行による具体的プレゼンテーションの内容と示唆を詳しく解説する。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第2回)議事録.令和6年9月10日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第2回)議事次第.令和6年9月9日