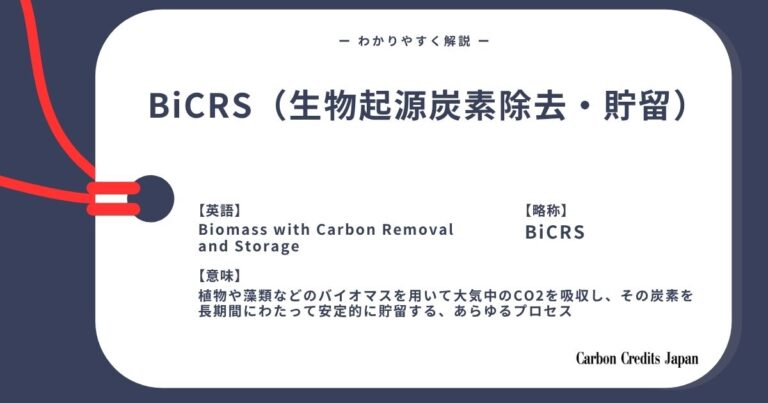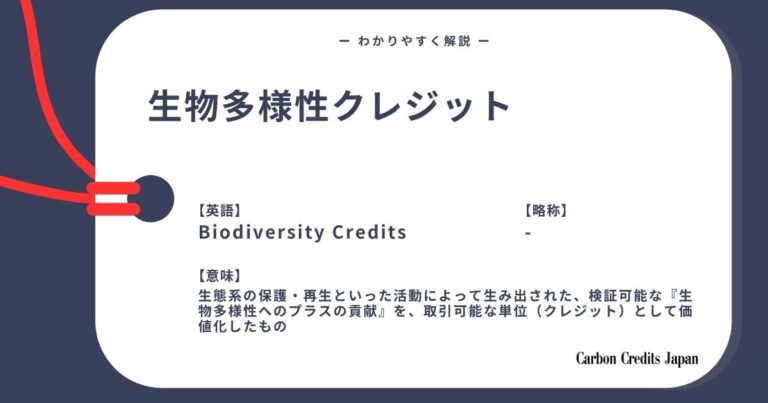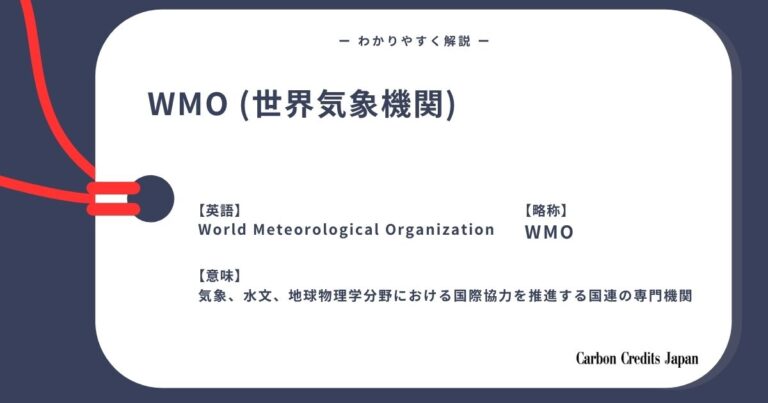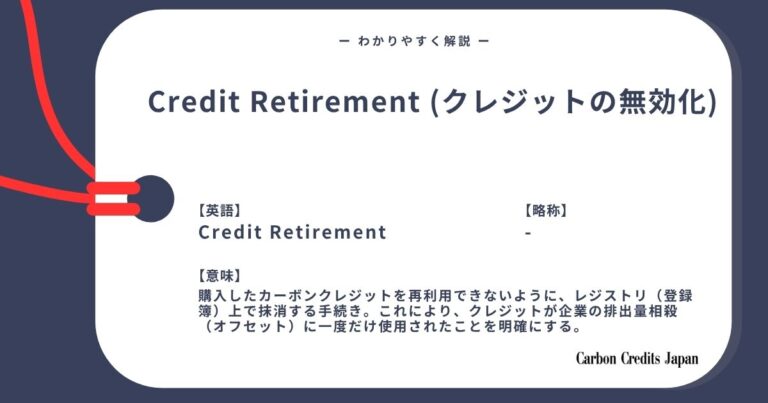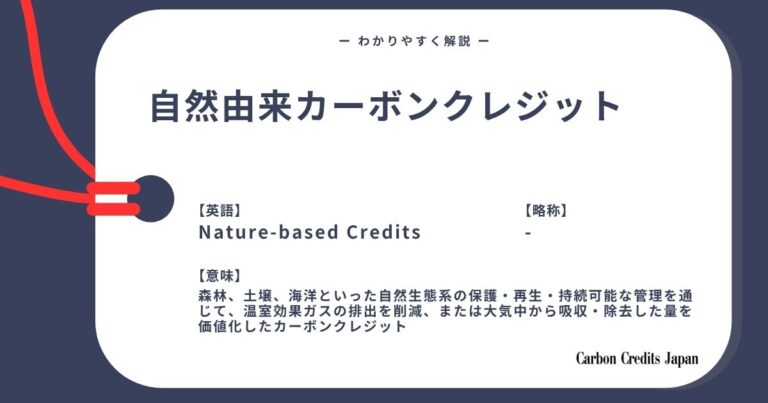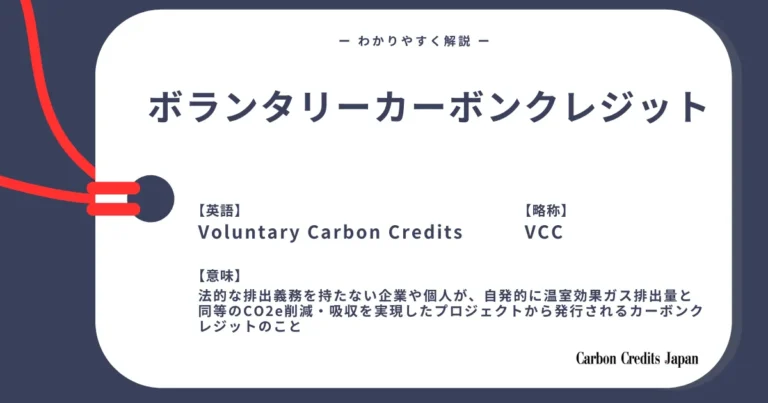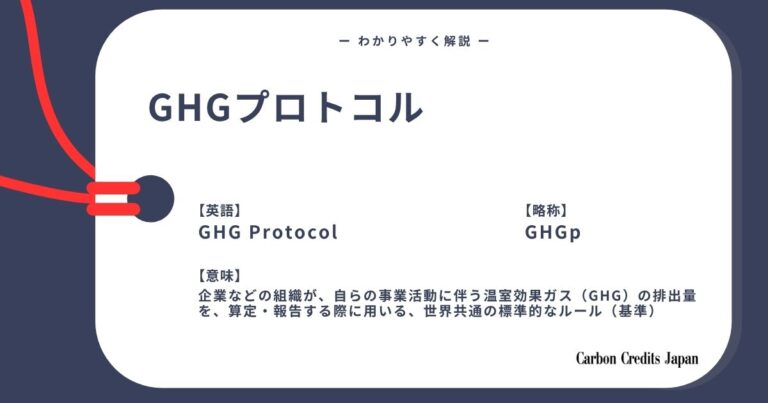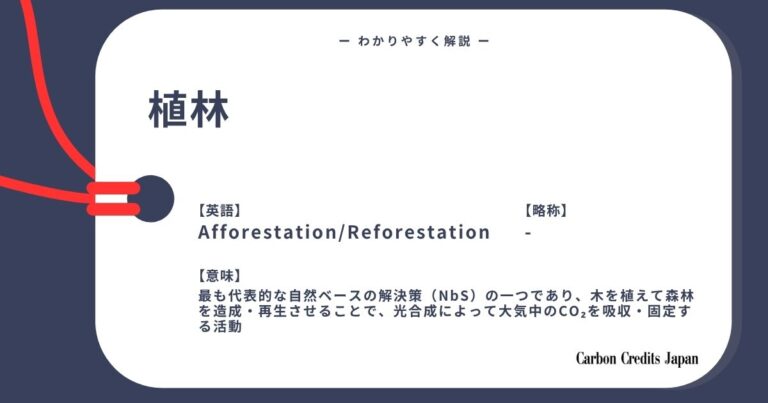気候変動対策は、現在の二酸化炭素(CO2)排出量を「削減(Reduce)」する段階から、過去に排出したCO2を大気中から積極的に「除去(Remove)」する段階へと移行している。この除去技術の究極の切り札として期待されるのが、「DAC(Direct Air Capture)」、すなわち「直接空気回収」である。
DACは、特定の排出源からではなく、どこにでもある「空気」そのものから、薄く広がったCO2を直接回収する革新的なカーボンリバース技術だ。
本記事では、このDACを「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から深く分析する。DACがいかにして気候変動対策における「最後の砦」となり、その高い信頼性が新たな気候変動ファイナンスを動員しているのか。そして、この最先端技術が、将来的に途上国の開発機会や公正な移行にどのような影響を与えうるのか。その壮大なポテンシャルと巨大な課題を、包括的に解説する。
DACとは
DACとは、「大気中からCO2を直接分離・回収する技術」のことである。いわば「空気のための巨大な浄化装置」のようなものだ。
発電所や工場の煙突など、高濃度で排出されるCO2を回収するCCS(炭素回収・貯留)とは根本的に異なる。大気中のCO2濃度はわずか0.04%(400ppm)程度と非常に薄いため、DACには、その中からCO2だけを選択的に、かつ効率的に集めるための高度な化学技術が必要となる。
回収されたCO2は、地中深くに貯留され(この場合DACCSと呼ばれる)、大気中から永久に隔離されるか、有効活用(DACCU)される。
気候目標達成に不可欠な除去技術
IPCCの報告書は、世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えるためには、排出削減を最大限に進めた上で、さらに数十億トン規模のCO2を大気中から除去(ネガティブ・エミッション)する必要があると結論付けている。DACは、この不可避な除去を実現するための、最も確実で信頼性の高い選択肢の一つだ。
その役割は主に以下の二つである。
- ネットゼロの達成
航空や重工業など、どうしても排出をゼロにできない部門の「残余排出」を相殺する。 - 気候の修復
もし気温上昇が1.5℃の目標を超えてしまった(オーバーシュートした)場合に、大気中のCO2を減らして、気候をより安全な状態に戻す。
仕組みや具体例
DACの技術は、主に以下の2つのアプローチで開発が進められている。
固体吸着法(Solid DAC)
CO2とのみ選択的に結合する特殊な固体吸着材(フィルター)に大量の空気を通過させてCO2を捕捉する。その後、フィルターを加熱(約80〜100℃)することで、純粋なCO2を分離・回収する技術である。スイスのクライムワークス(Climeworks)などが代表的な事例だ。
液体吸収法(Liquid DAC)
CO2を吸収しやすい水酸化カリウムなどのアルカリ性液体に空気を通し、CO2を化学的に吸収させる。その後、いくつかの化学プロセスを経て、高温(約900℃)で加熱することでCO2を分離・回収する技術である。カナダのカーボンエンジニアリング(Carbon Engineering)(2023年にOccidental Petroleumが買収)などが代表される。
貯留プロセス(DACCS)
回収されたCO2は、CCSと同様に、パイプラインなどで輸送され、地下1000メートル以上の深部にある帯水層や枯渇した石油・ガス田に圧入され、数千年以上にわたって安定的に貯留される。
事例、Climeworksの「マンモス」プラント
アイスランドにあるClimeworksの「マンモス」プラント(2024年稼働)は、世界最大規模のDACプラントである。アイスランドの豊富な地熱エネルギーを利用してプラントを稼働させ、年間最大3万6000トンのCO2を大気から回収する。回収したCO2は、現地のパートナー企業によって地下の玄武岩層に注入され、数年で鉱物化(石化)することで、漏洩リスクが極めて低い、非常に永続性の高い貯留を実現している。
メリットと課題
DACは、他のいかなる気候変動対策とも異なる、ユニークな利点と、巨大な課題を併せ持っている。
メリット
- 場所を選ばない
バイオマスを必要とするBECCSなどと異なり、基本的にはどこにでも設置可能である(ただし、再生可能エネルギーと貯留サイトへのアクセスは重要)。 - 高い信頼性と測定容易性
除去したCO2の量を正確に測定・検証できるため、クレジットとしての信頼性(Integrity)が非常に高い。 - 土地利用効率
同じ量のCO2を除去するために必要な土地面積が、植林に比べて格段に小さい。
課題
- 極めて高いコスト
現在の除去コストは1トンあたり数百ドルと、他のどの緩和策よりも高価である。 - 莫大なエネルギー消費
大量のクリーンな熱と電力が必要不可欠だ。DACの大規模な展開は、再生可能エネルギーの供給拡大が絶対条件となる。 - モラルハザード
「将来、DACで回収すればよい」という考えが、現在の排出削減努力を遅らせる「言い訳」に使われるリスクがある。
まとめと今後の展望
DAC(直接空気回収)は、気候変動との長期的な闘いにおける、人類の最も強力なツールの一つであるが、それは万能薬ではなく、莫大なコストとエネルギーを必要とする「最後の切り札」である。
要点
- DACは、大気中から直接CO2を回収する「炭素除去(ネガティブ・エミッション)」技術である。
- ネットゼロ達成後の「気候修復」にも貢献できる、ユニークかつ不可欠な役割を持つ。
- 非常に高コストだが、企業の先行購入契約や政府の支援によって、市場と技術開発が急速に進んでいる。
- その大規模な普及は、抜本的なコスト削減と、再生可能エネルギーの爆発的な拡大にかかっている。
今後の展望
DACのコストは技術革新と規模の経済によって着実に低下していくと見られる。その未来は、気候変動ファイナンスのあり方を大きく変える可能性がある。高品質な炭素除去が、信頼性の高い資産として市場で取引されるようになれば、それは新たなグリーン産業を世界中に生み出す。
その時、この技術がもたらす恩恵を、先進国だけでなく、豊富な再生可能エネルギー資源を持つ途上国も享受できるような、公正で包摂的な国際協力の枠組みを構築できるかが、DACを真に地球全体の解決策とするための大きな挑戦となる。