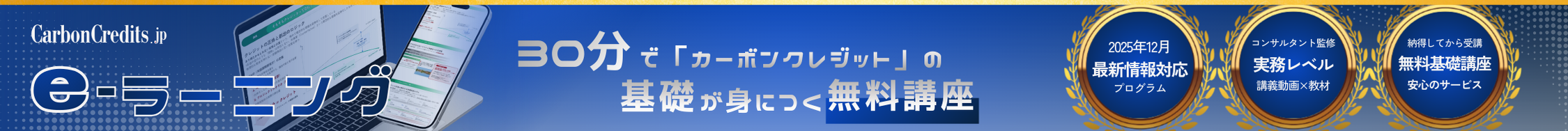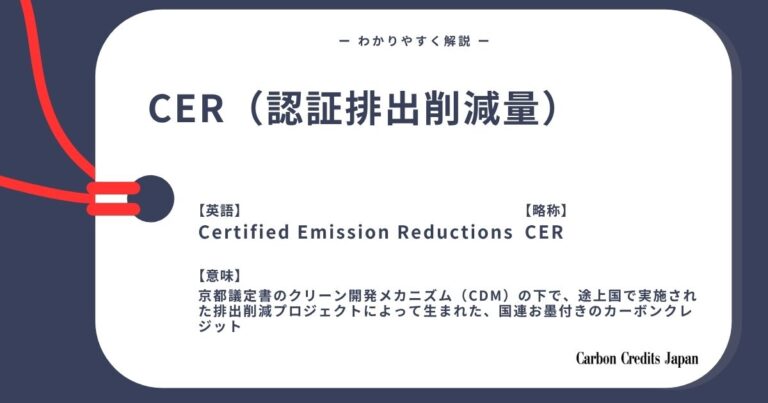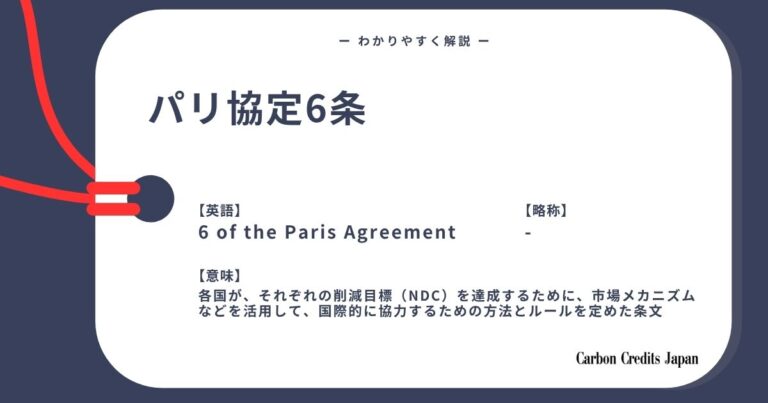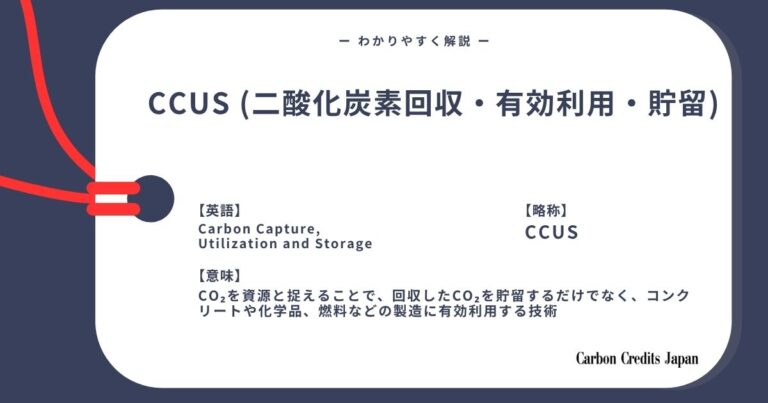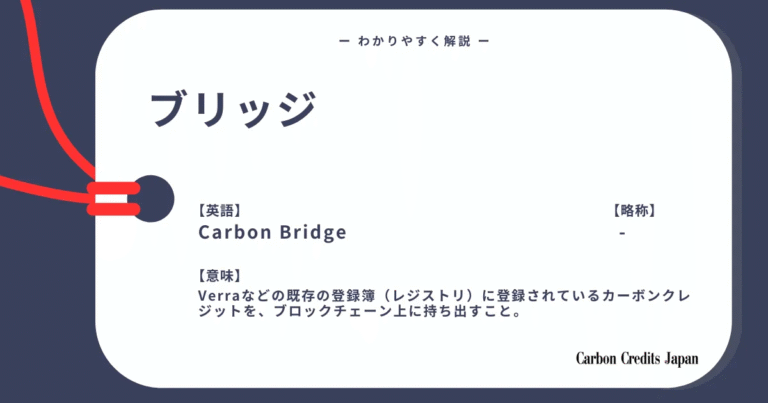EU ETS(European Union Emissions Trading System、欧州連合排出量取引制度)は、世界の気候変動政策とカーボンプライシングの中核に位置する、最も巨大で影響力のある制度である。2005年に世界で初めて導入されたこの多国間かつ強制的なキャップ・アンド・トレード制度は、欧州の脱炭素化を牽引し、その後の世界各国の気候変動政策のモデルとなってきた。
一言で言えば、EU ETSとは、「EUが、域内の主要な産業施設や航空会社などからの温室効果ガス排出量に、全体としての上限(キャップ)を設け、その排出枠を企業間で売買(トレード)させる制度」である。これは「キャップ・アンド・トレード」の典型であり、カーボンプライシングの最も代表的な手法である。
仕組みの基本構造
EU ETSの仕組みは以下の通りである。
- キャップの設定
EUが科学的知見に基づき、域内全体の排出許容総量(キャップ)を決定する。この総量は年々厳しく設定され、排出削減を確実にする。 - 排出枠の割当と取引
キャップの範囲内で、対象となる約1万の施設に排出枠(EU Allowances, EUAs)が割り当てられる。企業は、自社の排出実績に応じて、枠が不足すれば市場から購入し、余れば売却することができる。 - 単位
1 EUAは、1トンのCO2排出許可量に相当する。
EU ETSの重要性と経済的効率性
EU ETSの重要性は、環境目標の達成を確実にしながら、経済への影響を最小限に抑える「経済的効率性」を両立させる、強力な政策ツールである点にある。
排出枠の価格という明確なシグナルが、全ての企業に対して「炭素を排出することはコストである」という強烈なインセンティブを与え、以下の効果をもたらす。
低炭素技術への投資促進
排出枠の価格が上昇すると、企業はコスト削減のため、より積極的に最新の省エネ技術や低炭素技術への投資を加速する。排出削減を効率的に達成した企業は、余剰排出枠を売却することで利益を得る一方、削減に遅れる企業は不足分を購入することでコスト増を負う。この市場原理が、域内全体のイノベーションを牽引する。
大規模な資金創出と活用
排出枠の配分は、現在、企業が入札形式で購入するオークションが主要な方法となっている。これにより公平性が担保されると共に、EUおよび加盟国に年間数百億ユーロ規模の歳入がもたらされる。この歳入は、気候変動対策のために使途が定められている。
- イノベーション基金(Innovation Fund)
革新的な低炭素技術(例:グリーン水素、CCUS)の実用化を支援するための大規模な資金動員ファンドである。 - 近代化基金(Modernisation Fund)
所得水準の低い中・東欧の加盟国における、エネルギーシステムの近代化や、石炭からの公正な移行を支援する。 - 社会気候基金(Social Climate Fund)
ETS2(建物・道路輸送向けの新制度)導入による燃料価格上昇の影響を受ける、脆弱な世帯や零細企業を支援するための基金である。
EU ETSの対象セクター
EU ETSは、複数のフェーズを経て進化し、その対象範囲を拡大している。
固定施設と航空
以下のエネルギー集約型産業の施設や、EU域内を飛行する航空会社が主要な対象である。
- 固定施設
発電所、製鉄所、セメント、化学、製紙、ガラス、セラミックス、アルミニウム製造など。 - 航空
EU域内を飛行する航空会社。
新たな対象セクター
- 海運
2024年から、EUの港に寄港する大型船舶が対象に追加されている。 - 建物・道路輸送
ETS2として、燃料供給業者を対象とする新しい制度が導入される予定である。
メリットと留意点
EU ETSは、世界で最も成功した気候変動政策の一つと見なされているが、留意すべき課題も存在する。
メリット
- 確実な排出削減
キャップにより、対象セクターからの排出総量が確実に削減される。過去の実績として、対象セクターの排出量を大幅に削減した実績がある。 - 経済的効率性
市場原理に基づき、最も低コストでの排出削減を促し、低炭素技術へのイノベーションを牽引する。 - 大規模な資金創出
オークション収入を通じて、グリーンなイノベーションや公正な移行のための巨額な財源を生み出す。
課題
- 価格の不安定性
排出枠(EUA)の価格は、経済情勢や政策変更によって大きく変動し、企業の長期的な投資計画に不確実性をもたらすことがある。 - 公正な移行の複雑さ
ETS2などの導入による燃料価格の上昇が、低所得者層の生活に影響を与える逆進性の問題をどう緩和するかが、重要な課題となる。
国際的な波及、炭素国境調整メカニズム(CBAM)
EU ETSは、その影響力を域外へと拡大しており、世界の貿易と気候変動政策のあり方を大きく変えようとしている。
CBAMの概要
最大の要因は、EU ETSと完全に連動する「炭素国境調整メカニズム(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)」の導入である。
これは、EU域外の国で、EUほど厳格なカーボンプライシングが導入されていない場合に、そこからEUに鉄鋼、セメント、アルミニウムなどを輸入する際、EU域内の炭素価格(EUA価格)との差額を実質的に支払わせる炭素の国境税である。
CBAMの目的と国際的な影響
CBAMの主な目的は、EU域内の企業が、規制の緩い域外国に生産拠点を移してしまうカーボンリーケージを防ぐことである。
しかし、これは事実上、EUの貿易相手国に対してカーボンプライシングの導入を促す強力な圧力となる。これにより、EU ETSの価格水準や制度設計は、日本のGX-ETSなど、世界の国々のカーボンプライシング政策に大きな影響を及ぼすことになる。