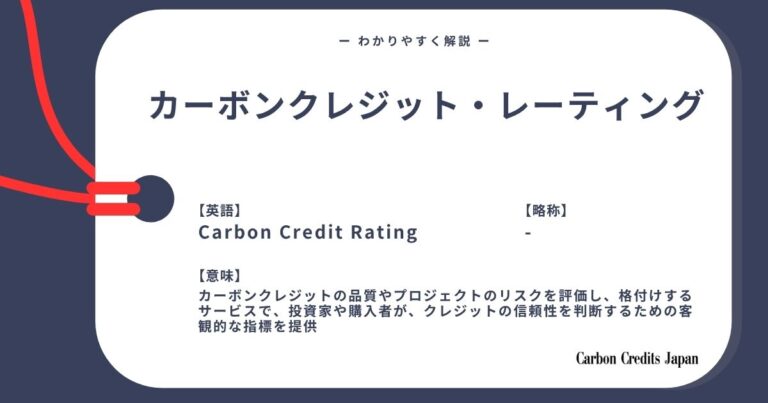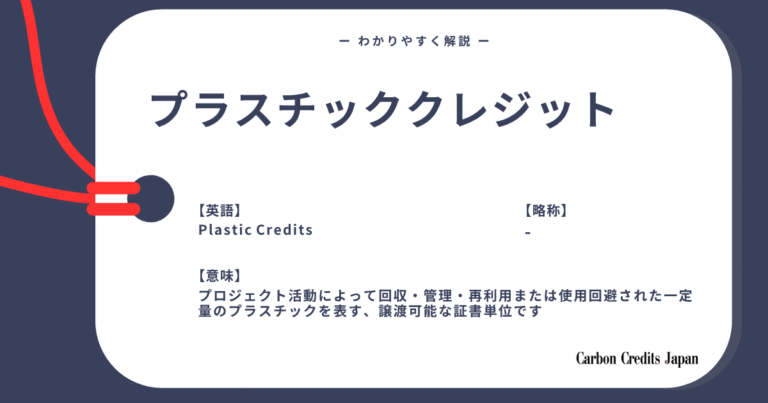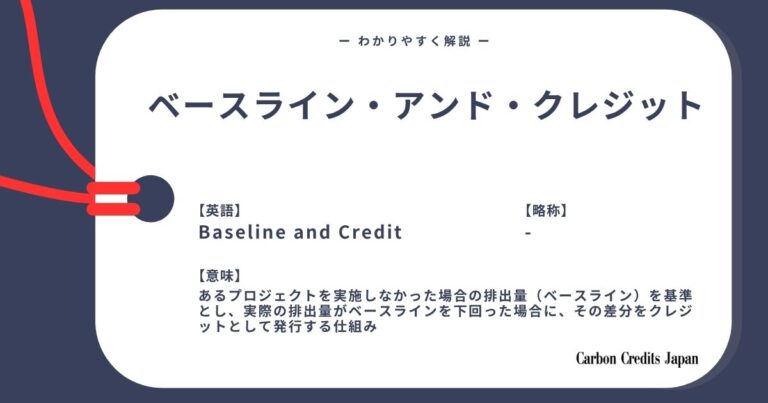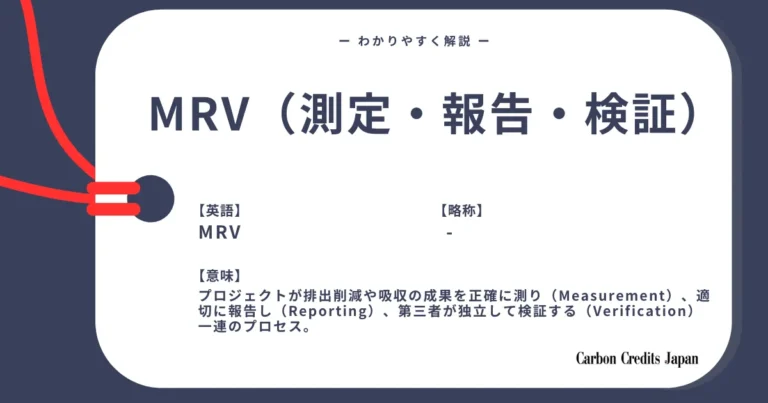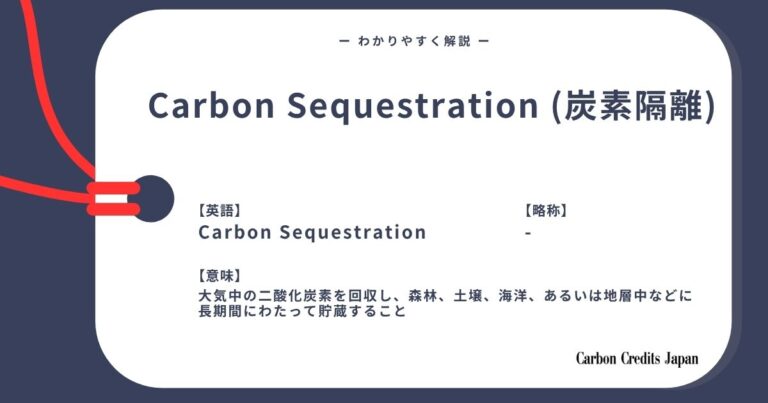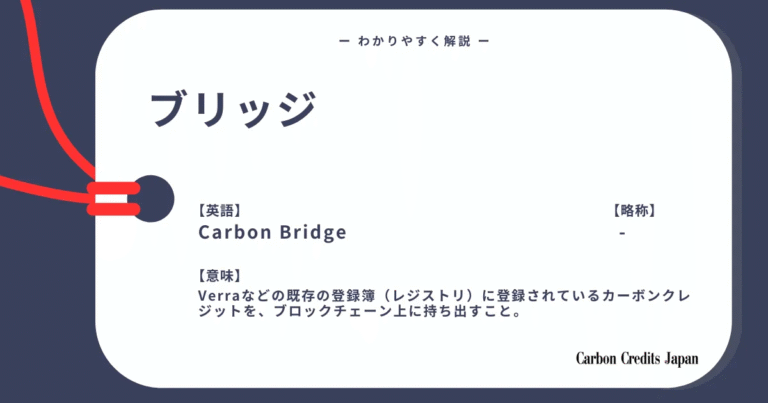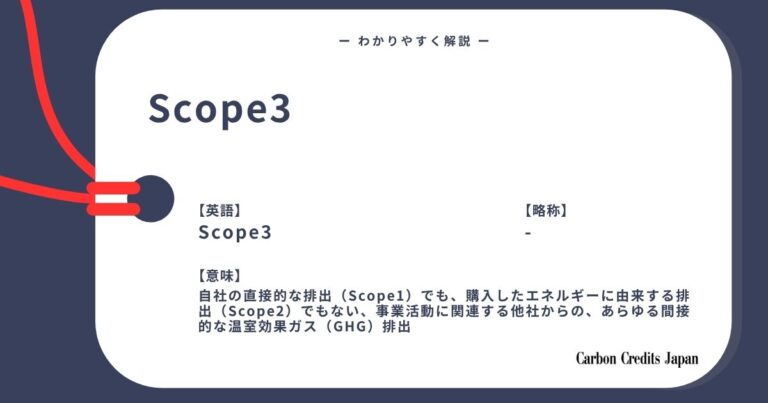京都議定書によって創設された国際炭素市場のポートフォリオにおいて、工場や発電所での排出削減プロジェクトとは一線を画す存在があります。それが自然の力、特に森林などが持つ二酸化炭素(CO2)の吸収能力を、初めて国際的な目標達成の計算に組み込んだ単位、「吸収単位(Removal Unit, RMU)」です。
これは、先進国の国内における土地利用・土地利用変化及び林業(LULUCF)活動から生まれた、極めて重要かつ複雑なクレジットでした。本記事では、このRMUについて国際開発と気候変動ファイナンスの視点から解説します。RMUがいかにして自然の役割を国際ルールに組み込んだのか、そしてその運用から得られた教訓が、現代の自然由来の解決策(Nature-based Solutions, NbS)にどう繋がっているのかを紐解きます。
RMUとは
RMUとは、京都議定書の下で先進国(附属書I国)が、自国内の森林管理や植林といった土地利用活動を通じて吸収した温室効果ガス(GHG)の量を認証したクレジットのことです。1 RMUは、1トンの二酸化炭素換算(tCO2e)の純吸収量に相当します。
他のクレジットと比較すると、その特異性が際立ちます。例えば、途上国での削減プロジェクトから生まれるCERなどは、特定のプロジェクト単位での排出削減量を認証するものです。対してRMUは、国全体のLULUCFセクターにおける排出と吸収を差し引きした「ネット(純)の吸収量」を国家レベルで算出し、クレジット化したものです。
また、国に事前に割り当てられる排出枠(AAU)が「予算」であるのに対し、RMUは約束期間中の実績に基づいて事後的に算出され、国の総排出枠に追加される「ボーナス」のような役割を果たしました。
歴史的意義、炭素会計への「シンク」の導入
RMUの最大の歴史的意義は、気候変動の緩和策として産業部門での排出削減だけでなく、生態系による「炭素の吸収・貯留(シンク)」という側面を、初めて国際的な法的枠組みの中に明確に位置付けた点にあります。
これは、国家の「炭素会計」に新しい勘定科目を追加する試みでした。各国は、工場などからの排出という「支出」を減らす努力に加え、自国の森林を適切に管理・育成することで「収入(炭素吸収)」を得て、国家全体の炭素収支を改善できるようになったのです。
この仕組みは、日本、カナダ、ロシア、北欧諸国といった広大な森林を有する先進国にとって、京都議定書の厳しい削減目標を達成するための重要な柔軟性措置となりました。国内の林業政策や土地管理に「気候変動対策」という新たな価値を与え、持続可能な森林経営へのインセンティブを生み出す可能性を示したのです。
発行の仕組みとルール
RMUの創出は、京都議定書の第3条3項および3条4項に定められた厳格な会計ルールに基づいて行われました。
対象となる活動は大きく分けて二つありました。一つは第3条3項に基づく義務的な活動で、1990年以降に行われた新規植林、再植林、および森林減少によるGHGの変動が対象です。もう一つは第3条4項に基づく任意的な活動で、各国が選択した森林管理、耕作地管理、牧草地管理などが含まれます。
算定においては、約束期間中にこれらの活動によるGHGの総吸収量から総排出量を差し引き、国としての「純吸収量」を導き出します。この計算結果に基づき、同量のRMUが国の登録簿(ナショナル・レジストリ)に発行されます。発行されたRMUは、国の総排出枠(AAU)に加算され、自国の目標達成に使用したり、排出量取引を通じて他の先進国へ売却したりすることが可能でした。
日本の事例、目標達成への貢献
日本におけるRMUの活用は、京都議定書の第一約束期間(2008-2012年)における目標達成戦略の核心部分でした。当時、日本は基準年比マイナス6%という削減目標を課されていました。
この達成のために、日本政府は国内の森林吸収源を最大限に活用する方針を採りました。議定書のルールに基づき、適切に管理された国内の森林(主に人工林)によるCO2の純吸収量を算定し、これをRMUとして計上したのです。結果として、森林吸収による貢献は、産業界の省エネ努力や海外からのクレジット購入と並び、日本の目標達成において極めて大きな役割を果たしました。
制度が抱えていた課題と教訓
RMUは画期的な制度でしたが、その運用を巡っては激しい議論や批判もありました。特に問題視されたのは、科学的な不確実性と環境十全性への懸念です。
広大な森林の炭素蓄積量を正確に測定・報告・検証(MRV)することは技術的に困難であり、数値の正確性に疑問が呈されることがありました。また、森林火災や病虫害によって森林が失われた場合、一度計上した吸収量が再び大気中に放出されてしまう永続性のリスクも大きな課題でした。
さらに、森林管理の会計ルールが政治的な交渉の結果として決定された経緯から、一部の国に有利な「抜け穴」となっているのではないかとの批判も存在しました。実質的な追加努力を伴わない吸収量が計上されているという懸念は、環境NGOや途上国からの不信感を招き、先進国が産業部門での厳しい削減を避けるための手段としてRMUを利用していると見なされる一因となりました。
メリットとデメリットの総括
RMUという制度がもたらした影響は、メリットとデメリットの両面から評価する必要があります。
メリットとしては、生態系が持つ炭素吸収の役割を国際的なコンプライアンスの枠組みに組み込んだ点が挙げられます。これにより、先進国に対して持続可能な森林管理や土地利用への関心を高めるインセンティブを提供しました。また、排出削減義務を負う国々に目標達成のための柔軟な手段を与えたことも、制度上の利点でした。
一方でデメリットとしては、前述の通り信頼性の問題が深刻でした。科学的な不確実性と政治的な妥協が入り混じったルールは、環境十全性に対する根強い疑念を生みました。また、先進国が国内のRMUに依存することで、途上国での排出削減プロジェクト(CER等)への資金や技術の移転が鈍化するという間接的な負の影響も指摘されました。
まとめ
RMUは、気候変動対策の歴史において、自然の役割を経済的な枠組みに統合しようとした、野心的かつ不完全な最初の試みでした。
国際的な気候変動レジームに初めて「シンク(吸収源)」の概念を導入した功績は大きいものの、その会計ルールや科学的な裏付けには多くの課題が残りました。しかし、RMUを巡る論争と経験は、決して無駄にはなっていません。
現在、パリ協定の下で議論されている森林保全や自然由来の解決策(NbS)においては、いかに信頼性が高く透明なモニタリングシステムを構築するかが最重要課題とされています。これは、RMUが残した「科学的基盤の頑健さと会計ルールの透明性が、市場の信頼性を支える生命線である」という教訓に基づいています。私たちが今日、衛星技術やAIを駆使して森林炭素の測定精度を高めようとしているのは、RMUが残した歴史的な宿題に対し、より誠実な答えを見つけようとする努力の表れなのです。