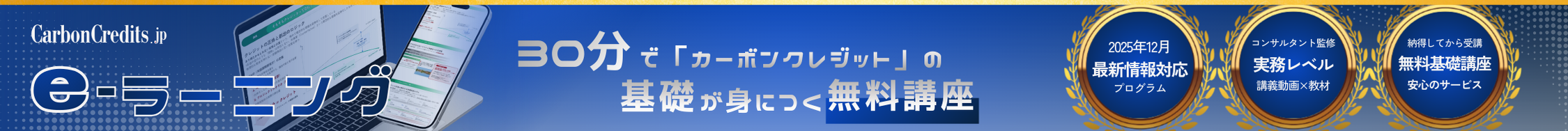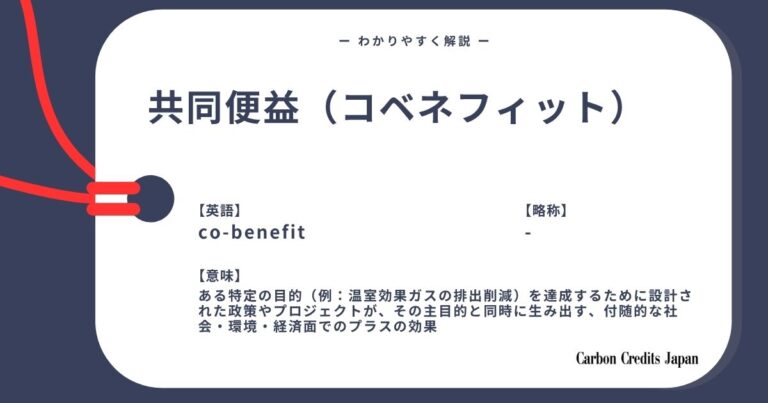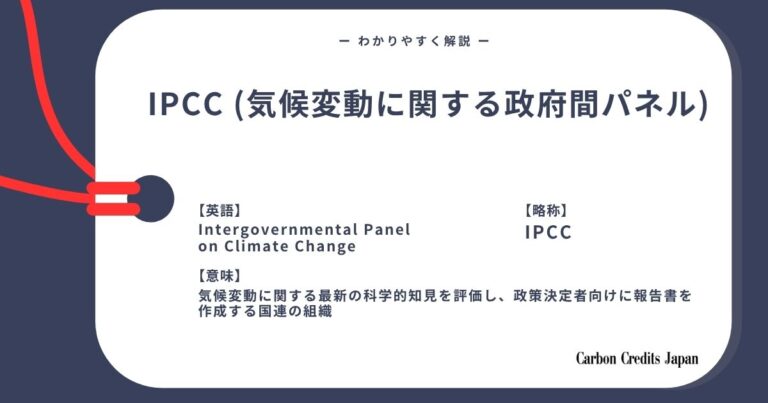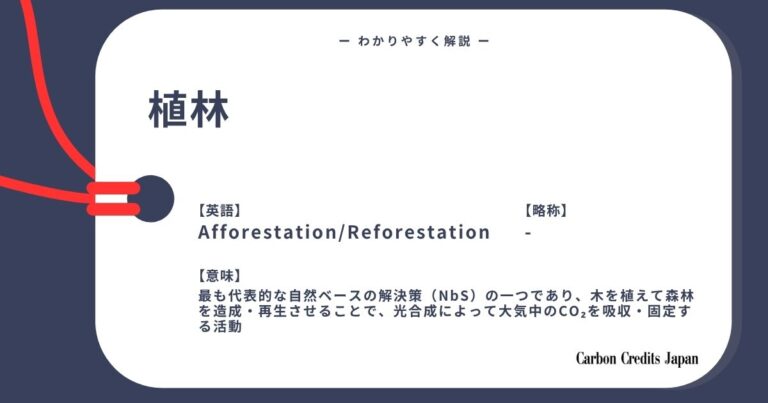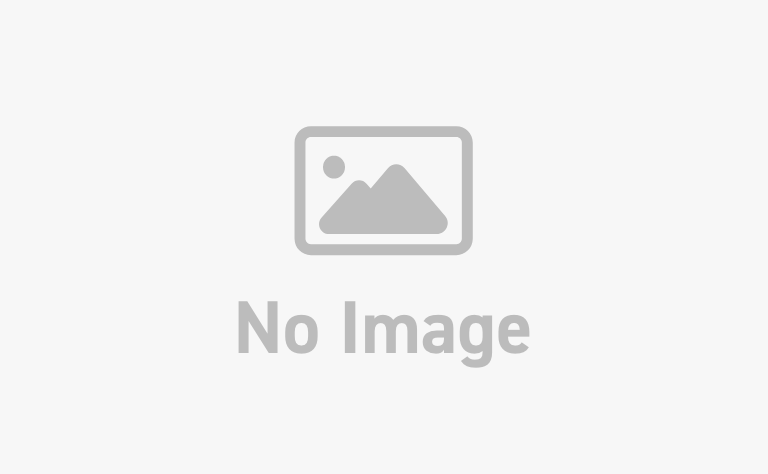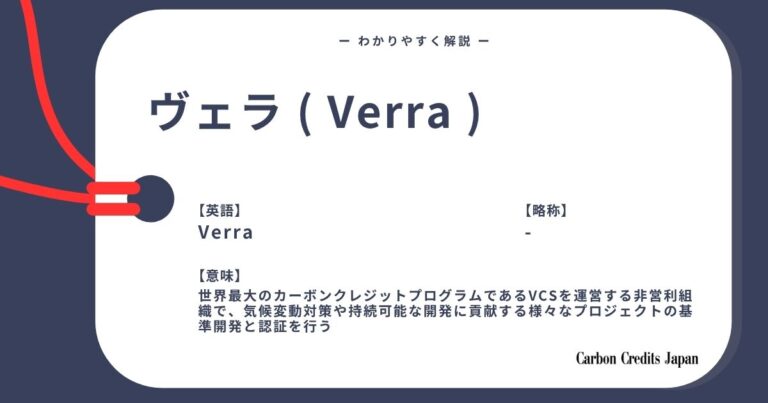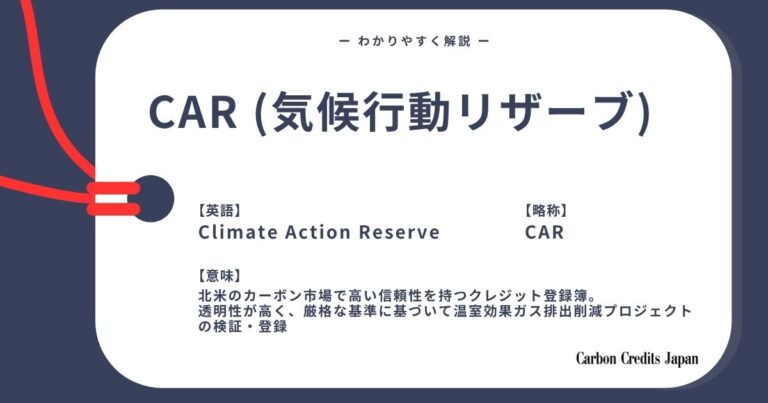京都議定書が創設した国際炭素市場を理解する上で、クリーン開発メカニズム(CDM)から生まれるCERと対をなす、もう一つの重要なクレジットが「排出削減単位(Emission Reduction Unit, ERU)」である。これは、京都議定書の第6条に定められた「共同実施(Joint Implementation, JI)」という枠組みから創出され、先進国間の協力に特化したメカニズムであった。
本記事では、このERUを「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から分析する。ERUがいかにして、特定の先進国ブロック内、特に市場経済移行国(旧ソ連邦・東欧諸国)への技術移転と資金動員を促したのか。そして、その運用を通じて明らかになった市場の信頼性を巡る課題が、今日の国際協力と市場メカニズムの議論にどのような教訓を残しているかを深く掘り下げていく。
ERUとは
ERUとは、京都議定書の下で、先進国同士が共同で実施した温室効果ガス排出削減プロジェクトから創出された、カーボンクレジットである。
- 単位
1ERUは、1トンの二酸化炭素換算(t-CO2e)の排出削減量に相当する。 - 最大の特徴
参加国が両方とも京都議定書で排出削減義務を負う先進国(附属書I国)である点にある。 - 活用例
主に、日本や西欧諸国といった投資国が、ロシアやウクライナ、ポーランドといった市場経済移行国(Economies in Transition, EITs)でプロジェクトを実施し、その成果であるERUを獲得するという形で活用された。
ERUの重要性
ERUは、先進国ブロック全体として、最もコスト効率の高い場所で排出削減を実現するための「内部的な最適化ツール」として機能した点に重要性がある。
コスト効率の追求
ある企業グループ全体のコスト削減目標に例えることができる。グループ内の各社が画一的にコストを削減するよりも、本社(投資国)が、設備が古く改善の余地が大きい子会社(ホスト国、特にEITs)の工場を近代化するために投資する方が、グループ全体としてはるかに安く、大きなコスト削減効果(=排出削減)を達成できる。共同実施(JI)は、この近代化投資によって生まれた削減効果(ERU)を、投資した本社が自国の業績として計上できる仕組みである。
地政学的な側面
このメカニズムは、冷戦終結後の東欧諸国などが抱えていた、非効率なエネルギーインフラを近代化するための、西側諸国からの民間資金動員を促すという地政学的な側面も持っていた。それは、気候変動対策と経済の近代化を結びつける、実践的な国際協力の形であった。
仕組みと具体的なプロセス
ERUの創出プロセスは、ホスト国(プロジェクト実施国)の制度的な成熟度に応じて、2つのトラック(経路)で進められた。
トラック1(ホスト国の裁量)
ホスト国が、排出量を追跡し検証するための国内制度を完全に確立している場合、このトラックが適用された。ホスト国自身の責任でプロジェクトを検証し、ERUを発行できるため、プロセスが迅速であった。
トラック2(国連の監督)
ホスト国の国内制度がまだ不十分な場合、このトラックが適用された。国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下に設置されたJI監督委員会(JISC)が、プロジェクトの妥当性確認や検証を監督するという、より中央集権的な手続きが取られた。これは、市場の信頼性を担保するためのセーフティネットの役割を果たした。
ERU創出の核心、AAUからの「変換」
ERUを理解する上で最も重要な点は、それがCDMのCERのように「ゼロから新たに創出される」のではなく、ホスト国が既に保有する排出枠(AAU:割当量単位)から変換されるという点である。ホスト国は、プロジェクトによって達成された排出削減量に相当する自国のAAUを、ERUという別の種類の単位に変換して、投資国に移転した。これにより、先進国ブロック全体の排出枠の総量(キャップ)は変わらず、キャップ内での効率的な再配分が行われる仕組みであった。
遺産と教訓
ERU/JIメカニズムは、先進国間の協力を促進したが、CER/CDMと同様、あるいはそれ以上に深刻な信頼性の課題に直面した。
追加性の問題
追加性とは、「プロジェクトによる収益がなければ実現しなかった削減であること」を意味する。多くのプロジェクトが、市場経済への移行に伴う必然的なインフラ更新であり、「ERU収入がなくても、いずれ実施されたのではないか」という強い疑念が常につきまとった。
「ホットエア」との関連
ERUの主要なホスト国であったロシアやウクライナは、経済停滞により、排出枠が自国の排出量を大幅に上回る余剰AAU(ホットエア)を保有していた。JIプロジェクトが、このホットエアをERUという形で「洗浄(ロンダリング)」し、市場価値を与えるための手段として使われたのではないか、という批判が絶えなかった。
これらの信頼性を巡る課題は、国境を越えた排出削減プロジェクトの成果を取引する際には、厳格な会計ルールと、透明性の高いガバナンスが不可欠であることを国際社会に痛感させた。この教訓は、パリ協定6条2項における、二重計上を厳格に防ぐための対応調整というルールの導入に直結している。
まとめ
ERU(排出削減単位)は、京都議定書の時代における、先進国間の協力という特定の文脈で機能した、歴史的なカーボンクレジットである。
- ERUは、京都議定書の共同実施(JI)の下、先進国間の共同プロジェクトから生まれたクレジットである。
- 途上国を対象とするCERとは異なり、ホスト国の排出枠(AAU)からの変換によって創出された。
- 市場経済移行国への投資を促進したが、追加性やホットエアを巡る深刻な信頼性の課題を抱えていた。
- その失敗の教訓は、現在のパリ協定6条における、厳格な会計ルールやガバナンスの重要性へと繋がっている。
ERUの歴史は、気候変動ファイナンスのメカニズムが、その意図とは裏腹に、実質的な排出削減を伴わない「抜け穴」を生み出してしまう危険性を、強く警告している。