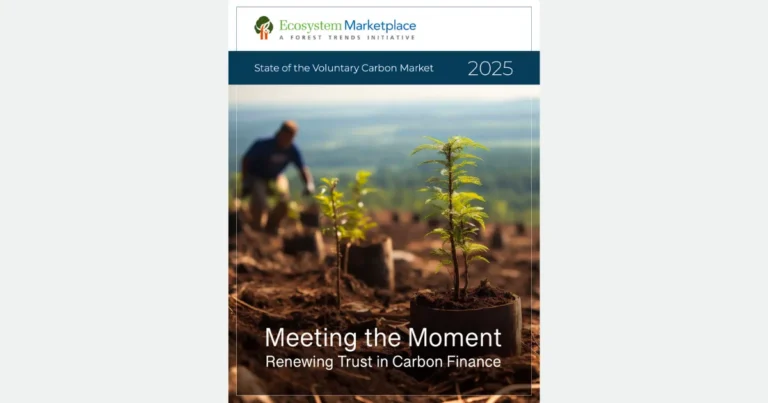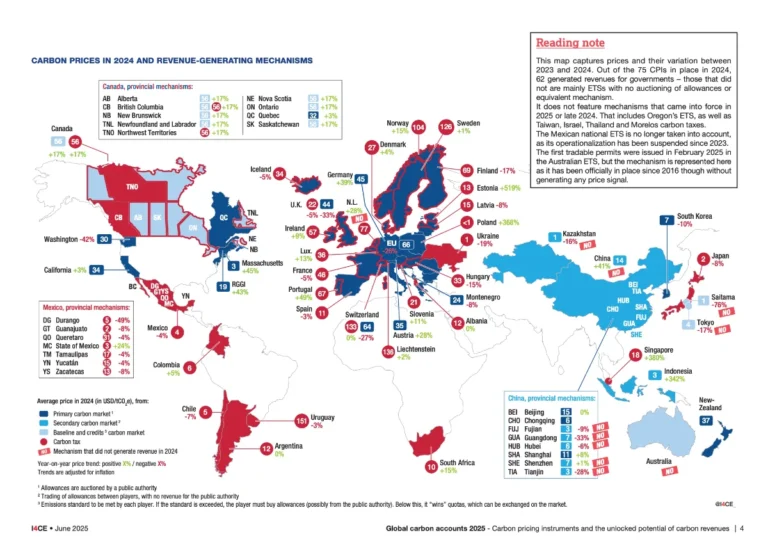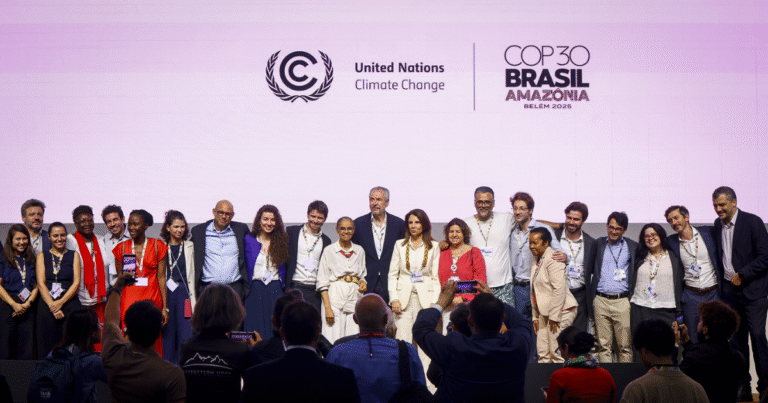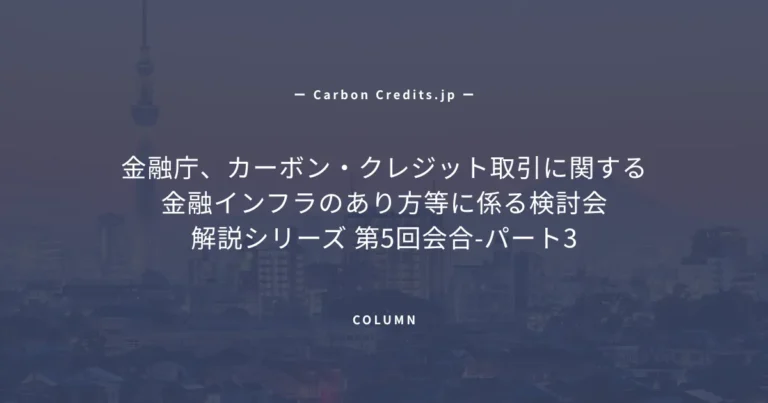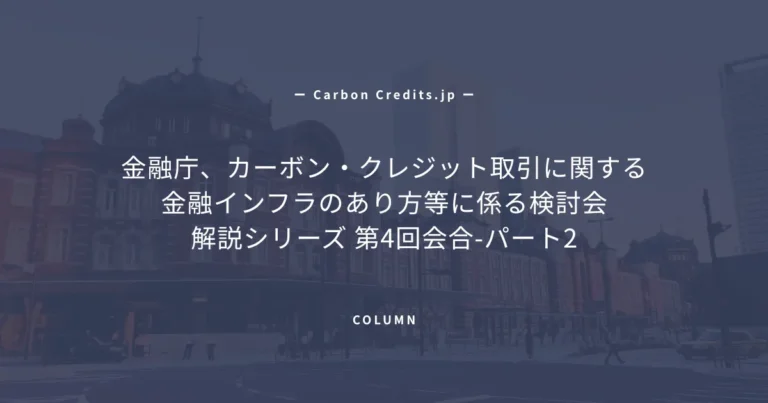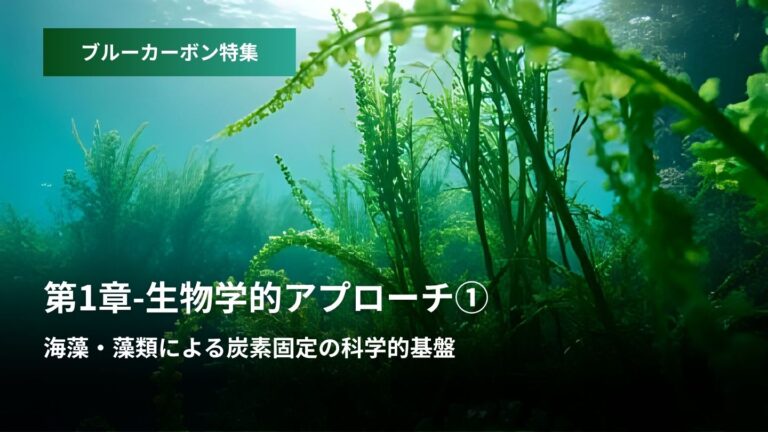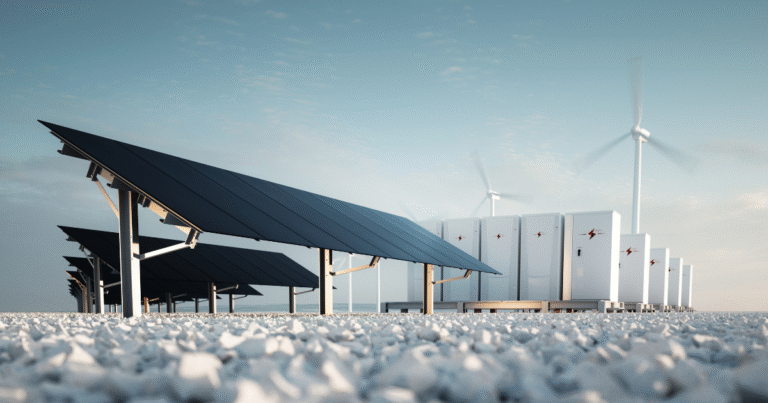脱炭素経営の新たな焦点として注目される「カーボンインセッティング」。
その制度化を本格的に進める枠組みが、2025年5月にSOCIALCARBONから発行された「Insetting Framework」だ。本制度は、サプライチェーン内の介入によってもたらされる温室効果ガス(GHG)排出削減・除去を、科学的・制度的に評価・認証する包括的なフレームワークの一つである。
カーボンインセッティングとは?
オフセットとの違い
カーボンオフセットが「サプライチェーン外部のプロジェクトによるクレジット購入」で排出を相殺するのに対し、インセッティングは「自社のサプライチェーン内」での直接的な排出削減活動を指す。

具体的には、以下のような介入が対象となる。
- 森林再生・保全(Reforestation, Conservation)
- アグロフォレストリー導入
- 水管理型稲作の展開
- 土壌炭素の増進を目的とした再生型農業(Regenerative Agriculture)
- 乳牛の飼育管理最適化やメタン削減技術(特にFLAG領域で顕著)
SOCIALCARBONのInsetting Frameworkは、これらを「定量的に評価・報告・主張する」ためのルールを提供する。Insetting Frameworkが対象とするのは、企業のバリューチェーン内またはその周辺で実施される排出削減・除去プロジェクトだ。
森林再生やアグロフォレストリー、持続可能な農業といった「土地由来」の介入を通じて、Scope3に関連する排出原単位を改善することを主眼としている。
フレームワークの核心「設計と制度的特徴」
①バリューチェーン内の削減・除去を制度的に認証
Insetting Frameworkは、これまで曖昧だった「Scope3排出の削減証明(≒インセッティング)」を明文化。対象は、あくまで企業のサプライチェーンに直接関連する活動に限定されており、「排出の削減・除去を介入(Intervention)によって実現した場合にのみ認証対象」となる。
② サプライシェッド(Supply Shed)という柔軟な単位
直接的なトレーサビリティが困難な農業・林業分野では、介入地点と供給先が必ずしも一致しない。これに対応するため、フレームワークでは「サプライシェッド(地域単位の供給圏)」という概念を導入。これは、地理的または経済的に一体とみなされる供給エリアを、排出原単位の改善単位として定義できるものである。

これは、実際のトレーサビリティが限られる農業・林業領域において、企業の介入と成果を制度的に認証するための現実的な設計である。

技術的要件と検証方法
①Scope3排出係数(EF)の改善を中心に設計
介入の効果は、該当製品の「排出原単位(Emission Factor:EF)」の変化として捉える。たとえば、同一のコーヒー豆100kgを調達していても、土壌管理・日陰樹導入・堆肥活用といった介入が加われば、EFが低下し、Scope3排出削減としてカウントできる。

②バリデーションとベリフィケーション
プロジェクト文書(PDD)の作成時点で、介入の対象範囲、既存の排出量(ベースライン)、予想される改善量を定量化する必要がある。その後、最低3年に1度の第三者による検証(Verification)が必要とされる。ただし、現場の負担を鑑み、5年に1度までの柔軟な適用も今後検討されている。
「因果性(Causality)」と「帰属の透明性」
SOCIALCARBONが重視するのが、企業の介入と排出削減との因果関係の証明だ。これは、企業が削減成果を「主張」できるかどうかの根拠になる。
- 資金拠出:農家に対する技術支援・補助金
- 購入コミットメント:介入条件付きでの長期契約(AMC)
- インセンティブ設計:成果に応じたプレミアム支払い
これらがなければ、Scope3削減として主張できない。また、成果を主張できるのは原則として「介入主体に相応のリスクやコストを負担した者」とされており、サプライヤー(例:農家)による共主張(co-claim)も可能である。
パブリックコメントから見る社会的論点
2024年末~2025年初に実施されたパブリックコンサルテーションでは、以下のような意見が多数寄せられた。
- すでに気候スマート農業を実施している農家への報酬を認めるべき(先行実践者の除外回避)
- 小規模農家による自主的介入にもクレジット的報酬が必要(追加性がないと排除される懸念)
- 地理的な供給圏(サプライシェッド)定義の曖昧さの解消
- 異なる国・地域にまたがる介入プロジェクトの一括認証可否(現状は制限あり)
特に「第一波の変革者(first movers)」のインセンティブ設計は、多くの現場実務者が共通して指摘している課題だ。
今後の展望とインプリケーション
SOCIALCARBONのInsetting Frameworkは、Scope3削減を制度的に認証可能とする枠組みの一つであり、CDPやSBTi、IFRS(ISSB)の開示基準とも親和性を持つ可能性がある。一方で、VerraのS3Sなど、同様のフレームワークが混在する懸念も指摘されている。
クレジット発行・販売ではなく、「事業と一体化した削減主張」に活用できるこの枠組みは、今後のネットゼロ達成、気候開示において極めて実践的なツールになると考えられる。